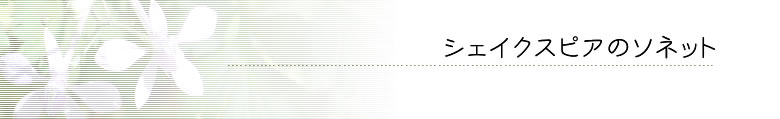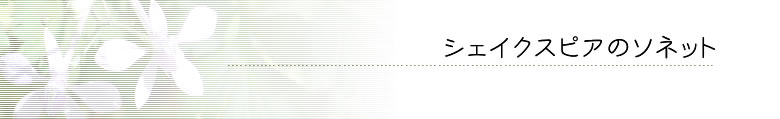過ぎゆく年の悦びであった君から
離れて過ごす私はまるで冬のよう。
凍える思いで暗い日々を過ごす
老いたる十二月のなんと荒涼たることか。
君と離れていたその時節は夏だった、
実りの秋が豊かな収穫に身を膨らませ
春の好色が産み出す実りのさまは
夫を亡くした未亡人が孕んだ子宮のよう。
だがこの豊かな実りも私が思うには
父無し子か、孤児のはかない定めでしかない。
夏も、夏の喜びも君に仕える従者であり
君がいなければ、小鳥たちさえも沈黙したまま。
たとえ小鳥たちが歌おうとも、暗い調子なので
木々の葉は、冬が近いのを恐れて青ざめている。
【私の鑑賞】
君と出会った初夏は、実りの秋を約束するはずであった。
だが、悦びである君との出会いも夏の間の一瞬の出来事でしかなかった。
実りの秋を一人で迎えるのは、夫を亡くした後に子供ができるようなもの。
悦びであるはずの子供も、父無し子として生まれてくるしかない虚しさ。
君がいない時は冬の季節のようなもの。
小鳥も歌わず、木々の葉も青ざめ、あたり一面荒涼たる風景で私は一人凍えて震えている。