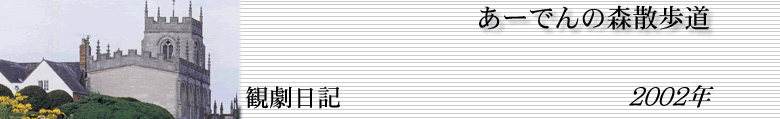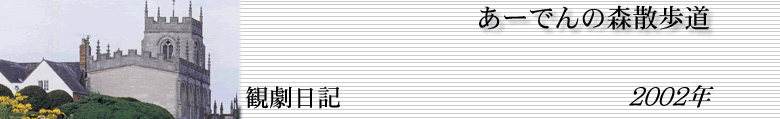〜 アジアの伝統芸能と融和したシェイクスピア 〜
8月18日(日)から23日(金)まで「アジア舞台芸術祭2002東京」が開催され、そのうちの演劇部門の一つに、赤坂の国際交流基金フォーラムにおいて、台北からは京劇とシェイクスピアを融合した『リア王』が上演され、日本からは世田谷パブリックシアターで上演中の『まちがいの狂言』が参加作品として扱われた。その両作品がともに、アジアの伝統芸能に融和させたシェイクスピア作品ということで、強い関心を引き起こす。さらに興味深かったのは、この両作品がともにアイデンテイテイをテーマとした問題として取り扱っている偶然の一致であった。
◆ グローバル・バージョン『まちがいの狂言』 ◆ 一人二役・二人二役・二人一役
この作品は昨年4月、今回と同じく世田谷パブリックシアターで公演され、その後ロンドンのグローブ座に招待され、現地でも大好評を博した(ロンドンでのこの作品の評判と関心については、鈴木真理さんの01.07.24付けのホームページ「ロンドン通信・18」の「狂言とシェイクスピアの舞台」に詳しく報告されているので参照されたい)。今回はそのグローブ座公演の演出を再構成し、グローバル・バージョンとしたものであるという。また今回は、演出の野村萬斎が、この世田谷パブリックシアターの芸術監督に就任した披露公演ともなっている。また、この作品の作者である高橋康也が今年の6月24日に亡くなっており、奇しくもその追悼公演の形ともなっている。
昨年の公演は、世田谷パブリックシアター会員の優先予約でもチケットが取れず、残念ながら見逃してしまっているので、今回はなんとしても観たいと思っていた。幸いチケットは取れたものの、公演パンフレットは売り切れの状態で後日郵送の予約となった。平日(火曜日)の夜ということもあって、いつもながらに観客は女性がほとんどで、しかも若い女性が大半であり、野村萬斎への人気のほどが伺える。日本の伝統芸能である狂言への関心とシェイクスピアへの興味を持ってもらえるようであれば、これは素晴らしいことでもあり、すごいことでもあると感じた。
舞台は開演の前から、面を被った黒装束の役者達が観客席に散って、「ややこしや、ああ、ややこしや」という台詞とも掛け声ともつかぬ声であたりを賑わしているが、その「ややこしや」という言葉を繰り返すことによって、観客の脳裏に一種の「刷り込み効果」を働かせることにもなっている。開演までの役者の装束は黒で、2階席から舞台を見下ろすと、舞台の床の両側前方にはおたまじゃくしが描かれていて、舞台上を動き回る黒装束の役者が、おたまじゃくしの運動を連想させて、可愛い滑稽味を覚える。
今回、グローバル・バージョンということで英語の字幕付となっていて、それが舞台両袖の2箇所に設置された大きな文字の電光掲示板なので、非常に見やすいだけでなく、しかも簡潔な英語なので、狂言の台詞を聞く楽しみだけでなく、時にはその字幕の訳を追いかける楽しみもある。字幕の英訳は作者である高橋康也と河合祥一郎の共訳となっている。
物語の設定を瀬戸内海の架空の島「黒草」(クロクサ=エフェサス)におき、その島に過って上陸した商人直介(=シラキュースの商人イージオン)の出身を「白草」(シラクサ=シラキュース)とすることで、原作のもつ音感のイメージを残しているだけでなく、すぐそれと分かる工夫がされている。二組の主人公、黒草・白草の石之介(アンテイフォラス兄弟)に石田幸雄、召使役の黒草・白草の太郎冠者(ドローミオ兄弟)に野村萬斎が、それぞれ二役を演じる。つまり一人二役だが、この二組の兄弟が同時に出る場面では、この二人に別の役者が扮する。ということで、一人二役もあれば、二人が二役の時もあり、二人が一役のこともある。「ああ、ややこしや、ややこしや」。そのややこしさを解く鍵として、演出家としての野村萬斎は次のような演出の法則を立てている。「黒草の主従は舞台左手の黒い幕から、白草の主従は舞台左手の白い幕の方から登・退場する。」(そこで、舞台左右の白・黒の幕の意味が分かる仕組みともなっている)
この一人が二人、二人が一人、二人が二人を演じることで、白草・黒草の主従は自己喪失を表象することにもなり、アイデンテイテイの問題と、自分探しというテーマを観るものをして感じさせる。という見方で観ることも興味を誘う。日本の伝統芸能である狂言と西洋の古典であるシェイクスピアとを融和させた見事な佳作である。
(作/高橋康也、演出/野村萬斎、世田谷パブリックシアターにて、8月20日夜観劇)
|