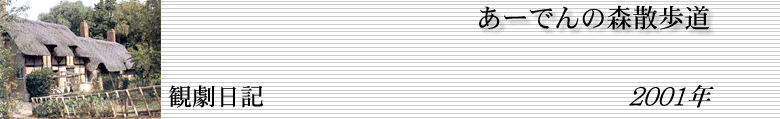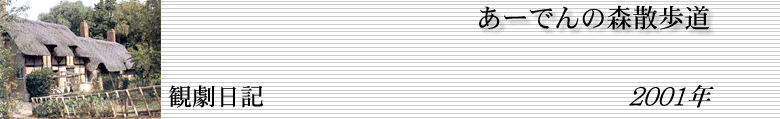〜可哀想に、俺の阿保が絞め殺された!〜
その時、僕は強い衝撃を抑えることができなかった。
「リア王」は、幾重にもテーマ性に富み、その切り込みをどのように演出するのか、観るものを期待させるものがあるのだが、この度のグローブ座カンパニーの来日公演では、なぜか僕は道化のことが気になっていた。
リアは、娘達については執拗なまでに語るのに、道化が消えてしまった後、なぜ問題にしないのか。
これまでにも「リア王」は数え切れないほど観てきているのに、今回こんな気持を持ったのは、虫の知らせとでも言うのであろうか、バリー・カイルの演出は、コーデリアが絞め殺された後、「可哀想に、俺の阿保が絞め殺された!」というリアの台詞をショッキングに具象化する。
嵐の場面で、リアはコーンウオール公爵の追っ手から逃れるために、グロスターの導きでドーヴァーに向かう。リア、ケイアスに変装したケント、グロスターが去った後、後を確かめるようにして、気違いの振りをしたエドガーが、舞台中央奥の観音開きの戸を大きく開く。
と、そこには赤い紐で首を吊ってぶら下がっている、道化の姿。
これを見たとき、僕は強い衝撃を感じて、震えをさへ感じた。
それは、一つには僕が気にしていた道化はどうなった?という気持のもやもやを一挙に吹き飛ばしたことにある。グローブ座カンパニーの「リア王」には何の予備知識も持たずに見たのに、僕の疑問を予見するかのようにその疑問の答えを差し出してきた、という偶然性からくる驚きであった。
リアの狂気の前では、道化の<戯れ言>は卑小化され、道化は居場所を失ってしまったのだ。
グローブ座カンパニー、バリー・カイル演出による「リア王」には、多くの仕掛けがある。
大きなモチーフは、<円>である。
舞台に、様々な<円>があることにまず気が付く。
舞台中央には、直径にして2m、高さ50cmほどの円形の台がある。その台の上には、旗をなびかせたミニチュアの城が点在している。開演の場では、その円形の台はブリテンの地図を具象している。
舞台天井には、大きな鉄の輪に草花、木の実(というより、林檎であるが)で装飾された花冠。これはリアが狂気に落ちたとき頭 上に被る手作りの花冠を象徴しているのだと知れる。
そして最も象徴的なのが、舞台上手の観客席の手前にある支柱の天辺に取り付けられた、運命の女神の車輪。これは舞台の外にあることから、二重の意味を帯びる。<運命の車輪>は、舞台の手の届かない所にある、ということは人の手の及ばないことを表象することにもなる。
これら三つの大きな<円>と、リアの王冠、花冠、そして狂人を装うエドガーが手にし、頭に被る小さな縄の輪。
バリー・カイルはこれらの円形は<命のイメージ>であると解説する。そして、「輪」のイメージが<命の動き>であるのと同時に、存在するが故の苦悩や悲痛でもあると語る。
その命を結ぶものが、赤い紐。赤い紐は、嵐の場面でリアと道化を結びつける役目をし、道化は赤い紐で首を括られて命が絶たれ、コーデリアの絞殺には、赤い紐が象徴的にコーデリアの首に結びつけられる。
赤い紐だけが、その<円>への入口であり、<円>からの出口であるとも解説している。
<円>と<赤い紐>については、パンフレットにあるバリー・カイルの解説でより鮮明に理解できるが、その解説がなくとも、それらが何かを表象していることが掴める構成となっている。
演出家の意図は、舞台の上ではもう観客の想像に道を譲るしかないわけだが、<意味>を感じさせるという点においては、この演出の意図は十分果たせていると思う。
エドマンドは、開演と同時に観客席から立ち上がって、その舞台上手に立つ運命の車輪を天辺に付けた支柱に上って登場する。つまり、舞台の外である。このことは、エドマンドが私生児であり、これまで舞台の上の人物と<場>を共有していなかったことを表すことにもなっている。それ以外にも大きな意味を持たせているのは、エドマンドが観客との<架け橋>の役割を負っていることである。
ロンドンのグローブ座では、エドマンドはヤード(立ち見席)から登場することになっている。
また、リア王とその従者の騎士達がゴネリルの館に狩りから戻ってくるときも、観客席後方から舞台へとやってくる。
これらは、みな舞台と観客席をつなぐ<橋>の役割を担っている。
そのことをより強調するためにエドマンド役のマイケル・グードは、時折日本語を入れるというサービスをする。それによって観客の笑いを誘い、舞台に近づけさせるという効果を生みだしている。
エドマンドが「ゴネリルをとるかリーガンをとるか」という場面では、ロンドンのグローブ座でも観客席から「両方」という声が飛んだりしたそうであるが、この日本の舞台では「こっちを取るか、あっちを取るか」とまるでハムレットの 'To be, or not to be'を思わせる台詞を日本語でやったので、大いに笑いを呼んだだけでなく、「両方」という声まで出て舞台に親密感が拡がった。
ポスト・パーフオーマンス・トークで、このマイケル・グードがこのことについて語った観客との「橋」の役目は十二分に達成されていたように思う。
グローブ座の芸術監督を兼ねるジュリアン・グローバーが演じるリア王は、<剛>の暴君である。しかし、剛であるが故に、不条理に導かれる狂気、そして末娘コーデリアとの再会の良心の呵責と法悦にも似た喜悦、コーデリアの死による法悦からの転落、それを嘆く慟哭の<吼え声>'howl, howl, howl'の叫びは、剛のリアが招いた痛烈な<業>として、観る者、聞く者の胸を打たずにはおかない。特に、コーデリアを腕に抱いてではなく、肩に背負って、絞るような吼え声で「吼えろ、吼えろ、吼えろ!」と叫びながら登場する場面では、観る者を心底から痛ましくさせ、思わず目頭が熱くなってしまった。この場面で泣けるには、リアの納得させる演技がなければあり得ない。そこまでに至るプロセスが感情の頂点に達するようでなければ、感動として伝わらない。僕にとっては、このジュリアン・グローバーのリア王は、忘れることの出来ない一人となるだろう。
ポスト・パーフォーマンス・トークでの質問で、蜷川幸雄の舞台についての率直な感想を求められたことに対して、グロスター伯爵役のホワイトヘッドは、「夏の夜の夢」の舞台の、竜安寺の石庭を模した一面の白い砂と、森の中で糸のように流れ落ちてくる白い砂のイメージが素晴らしかったと語った一方、リア王役のジョン・グローバーは、蜷川の「リア王」で、天井から岩が落ちてくる演出を危険だと批判的に評した。ジョン・グローバーのリア王の自信を伺わせるのに十分な発言であった。
10月7日観劇
(Shakespeare's Globe Theater Company来日公演、演出/バリー・カイル、美術/ヘイドン・グリフイン、東京グローブ座) |