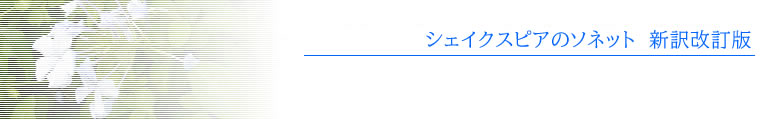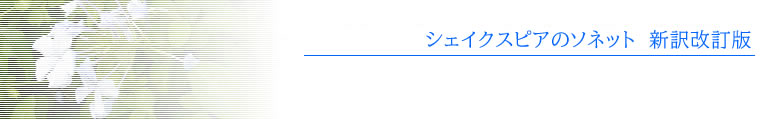早咲きの菫の花にこう言って叱ってやった
「美しい盗人よ、その芳しい香りをどこから盗んだのか
わたしの恋人の息からでないと言うのなら。その高貴な深紅の色は
わたしの恋人の血管に宿る色だが、お前はその色で
そのしとやかな頬を、けばけばしく染めている」
百合の花にはきみの手から白さを盗んだのだと咎め
マヨナラの蕾にはきみの髪から薫りを盗んだのだと責めた
刺の上で震えて立つ薔薇の花は
一つは罪を恥じて赤く、もう一つは絶望に青ざめている
三つ目の薔薇は、赤でもなく白でもない両方の色を盗み
色だけでなく、きみの息まで盗んだ
だが、その盗みのせいで、花の盛りに
青虫の復讐で食い荒らされてしまった。
さらに多くの花に眼を向けてみたが、眼にすることができたのは
どれもこれも、きみから色や香りを盗んだものでしかなかった。
The forward violet thus did I chide:
‘Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells,
If not from my love’s breath? The purple pride
Which on thy soft cheek for complexion dwells
In my love’s veins thou hast too grossly dyed.’
The lily I condemned for thy hand,
And buds of marjoram had stol’n thy hair;
The roses fearfully on thorns did stand,
One blushing shame, another white despair;
A third, nor red, nor white, had stol’n of both,
And to his robb’ry had annexed thy breath;
But for his theft, in pride of all his growth,
A vengeful canker ate him up to death.
More flowers I noted, yet I none could see,
But sweet, or colour, it had stol’n from thee. |