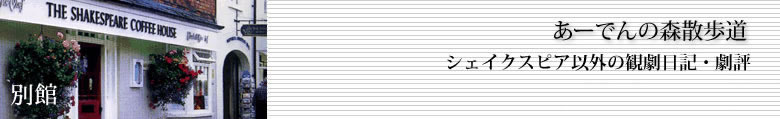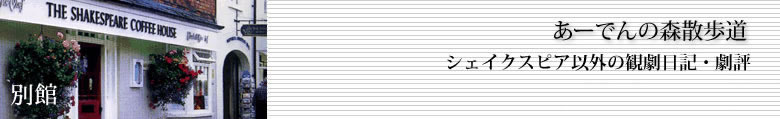|
公演日はちょうど長男の誕生日に当たっており、長男の嫁と自分も同じ5月生まれのため毎年一緒に誕生祝をしているので予約できずにいた。今回、この日での誕生祝を外したのだが神田香織一門会は何時も満席となっているので予約をあきらめていた。
ところが前日に伊織さんからメールが入ったので早速予約を申し込んだ。
今回、この一門会の講談会を聴くことが出来て本当に良かった、というのが一番の喜びであった。
演目は、前座のおりびあの『扇の的』に始まって、二つ目伊織の『七宝焼きの由来』、続いて真打織音の『出世の高松』、そして中入り後、一門の師匠香織の『石川一雄~塀の中の学び』で、いずれも人情的・心情的に感動を誘うものであった。
●おりびあ、『扇の的』
『太平記』から、壇の浦の合戦の場、平家が船上でかざした扇の的を那須与一が射る話であるが、これは彼女の先輩である伊織の講談で二度ほど聴いたことがある。前座の講演なので那須与一が的を射る場面を中心に10分ほどに凝縮されたコンパクトなものであったが、おりびあの成長ぶりを見ることが出来た。
●伊織、『七宝焼きの由来』
いつものことながら、この人のマクラを聴くのが楽しい。
講談を通して知識が広がるということを喧伝されたが、全くその通りである。
「講談師、見てきたように話をし」と言われるが、事実と事実の間に知られざる空白があり、そこをうまく脚色して話を作り上げるというのは、評伝劇を多く創作した井上ひさしの言葉であるが、講談もまた然りである。
この演目は長く講ぜられることがなく埋もれた作品で、話の内容も残っていないところが多く、それを伊織が新たに創作して起こしたものである。
マクラから入っていく「七宝焼き」の歴史の話から、はや目を開かせてくれる。
七宝焼きは、古くは古代エジプトで生まれ、シルクロードを伝って日本へやって来た。日本最古の七宝は、古墳時代末期の古墳から発見された「七宝亀甲型座金具」で、奈良時代にはもうすでにその製法は忘れられ、室町時代の勘合貿易で明から入ってきた七宝器を七宝瑠璃と呼ぶようになったという。
「七宝」とは、仏教における特別の価値があるとする七種の宝石「七宝」に由来し、その七種とは、「金・銀・玻璃・瑪瑙・瑠璃・珊瑚・シャコ(蝦蛄)」をいう(なお、これらのことは、この講談を聴いた後、ブリタニカ国際百科事典で調べたことである。
話はそれるが、講談を聴いた後、その話に触発されて関連の書物を読んだ経験は、香織師匠のチェルノブイリ原発事故の講談を聴いたとき、その話の元になったノーベル賞作家、スベトラーナ・アレクシエービッチの『チェルノブイリの祈り』ほか数冊を立て続けに読んだことがある。
講談は知識を広げてくれるだけでなく、関心と教養を深めてもくれるという好例であった。
肝心の講談の内容であるが、七宝焼きの失われた製法を、江戸時代後期、尾張の飾り職人、梶常吉が七宝焼き再生の志を立て、それを完成させるまでの苦心談で、そこに女房の援助という人情噺を加えて話の内容を豊かに膨らませ、波乱万丈の話にワクワク感を持って聴き入った。
●織音、『出世の高松』
今回初めて聴くことが出来た話で、「水戸黄門外伝」ともいうべき話で、光圀の兄、頼重の出生にまつわる話である。
家康の十一男鶴千代(後の徳川頼房)が17歳の時、京にいた時分、屋敷奉公をしていた「おしま」という女中に手を付けて懐妊させ、証拠の品として備前友成の短刀と香木「蘭奢待(らんじゃたい)」を残して京を去る。
おしまの両親が相次いで亡くなり、おしまは叔父の宗右衛門夫婦に引き取られ、そこで出産するがそのまま亡くなってしまう。生まれたのは男の子で、宗右衛門夫婦はその子に「寅松」と名付けて育てる。しかし、宗右衛門は日雇いの仕事で、雨降りが続くと途端に干上がってしまう。
寅松が13歳の時、食べる物も底をついた時、おしまから託されて天上裏に吊るしていた風呂敷包みを解いてみると、そこから鶴千代が残した「生き形見」が出て来る。
宗右衛門が見つけた香木を焚いているのを同じ長屋の道具屋の七六が嗅ぎつけ、短刀を見て相当の品であることを見抜いて、親子を江戸へと連れて行く。
そこで親子の対面を果たすが、頼房には千代松(後の光圀)という男子がいるため、寅松を頼重と名を改めさせて常陸・下館五万石の大名とし、頼重はそこで功績をあげ、3年後に讃岐高松の十二万石の藩主と出世する。
後日談として、光圀は本来長男である頼重が水戸家を継ぐべきであると考え、お互いの子を養子として頼重の子に跡を継がせるようにする。光圀公の美談で、人情噺に通じる感動がある。
●香織、『石川一雄~塀の中の学び』
狭山事件発生から今年で63年となるが、無実を訴える石川一雄の再審はいまだ始まらないまま、今年3月13日に、86歳の無念の生涯を終えた。
冤罪事件の再審のハードルは高く、つい最近、2024年10月に事件から58年目にしてやっと無罪判決を得た袴田巌さんに続いて、再審を待ち望んでいた矢先の無念の死であった。
神田香織の『石川一雄~塀の中の学び』は、黒川みどりの『被差別部落に生まれて―石川一雄が語る狭山事件』(岩波書店、2023年5月刊)を元にして語られる。
その作者黒川さんも会場に姿を現していて、香織師匠から紹介された。
常々、講談はマスコミの先駆けだと思っているが、テレビやラジオの無かった時代、庶民は講談を通していろいろな情報を得ていた。講談に限らず芝居などもそうであった。事件をそのまま伝えることは時の権力に差支えがあり、時代や名前をこそ変えているが、『忠臣蔵』などもそのよい例である。
死刑囚石川一雄は文字が読めず、書けなかった。それを刑務所の中で教えたのは、石川一雄を担当していた看守である。この読み書きが出来なかったという事実を知るだけで、脅迫文など書けるはずもない事は明らかであるが、取り調べ時における刑事の卑劣な誘導尋問など、この講談を聴いている間にも怒りが湧いてきた。
神田香織の講談は、社会批判や社会への告発の内容が多く語られ、その都度、自分の関心度の低さを反省させられるだけでなく、啓蒙されることが多い。まさに伊織が語るように、学ぶべきことが多く、自分の知識や教養が広がる。そのために聞いているわけではないが、話の面白さに加えて、目を 開かされることが多い上に、いつも大きな感動を与えてくれる。
報道は事実を述べるだけであるが(時にその事実は、これらの冤罪で知られるように大いに誤っている場合が往々にしてある)、講談はそこに血の通った人間味を添えてくれる。
講演時間は全部で2時間15分であったが、心を豊かにしてくれるひと時であった。
予約番号は77番と最後の方であったが、当日、予約番号1番の河上さんのおかげで前列から2場列目の席で聴くことが出来た。感謝!感謝!!
5月4日(日)14時開演、なかの芸能小劇場、木戸銭:3000円
|