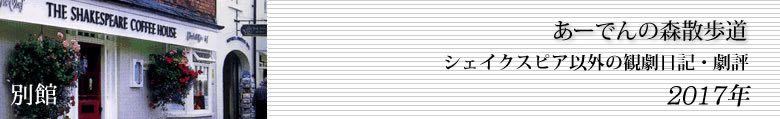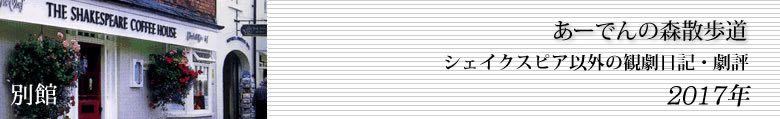原作/ヴァージニア・ウルフ、翻案・脚本/サラ・ルール、
翻訳/小田島恒志・小田島則子、演出/白井晃
美術/松井るみ、音楽/林 正樹、衣装/伊藤佐智子
出演/多部未華子、小芝風花、戸次重幸、池田鉄洋、野間口徹、小日向文世
演奏/林正樹、相川瞳、鈴木広志
KAAT神奈川芸術劇場<ホール>、チケット:(S席)8500円、座席:1階7列6番 |
【観劇メモ】
観劇予定にまったく入れていなかったが、高校の同期生I君の誘いで、急遽チケットを手配。
シルバー席チケットは既に完売であったが、幸い、S席で比較的前方の席が二つ並びに空いていた。
ヴァージニア・ウルフの作品に『オーランドー』なるものがあったとは全く知らなかったので、アマゾンで原書を取り寄せ予備知識的に読んでみたが、あまり面白いとは思えなかったが、映画になった翻案の脚本が面白いのであろう、その映画を観たことがあることからI君が誘ってきたのだった。
実際の舞台を観ての感想は、この舞台を観たことで、皮肉にも原作の面白さの方が浮き上がってきた。
オーランドーを演じる多部未華子の台詞が、舞台のどこにいてもマイクを通した声で下手側から聞こえてくるので、台詞に臨場感がなく平板であった。
小芝風花がロシアの美姫サーシャーを演じ、小日向文世がエリザベス女王、戸次重幸、池田鉄洋、野間口徹の3人はオーランドーの召使いなどを演じ、役柄としてはむしろコロス風で、説明役的で、全体的にも物語が説明的に展開されていく。
時代は、16世紀末のエリザベス朝から21世紀の現在までのオーランドーとして描かれる。
小説では、この作品が書かれた時点の現在、1928年までであったが、映画では上演時までが現在として扱われ、舞台ではこの公演の現在時までで、21世紀を表象して、オーランドーはタブレットを手にしている。
最後の場面は、そのオーランドーが、海辺を映し出したホリゾンとの前の舞台奥中央部に立ち、エリザベス女王を演じた小日向文世が、上手側の舞台前方にはす向かいに立って対峙して幕となる、象徴的な印象を感じさせる演出であった。
舞台背景としては、最初と最後の海辺の風景と、オーランドーが詩人たらんと欲して書く、詩句の中の樫の木がホリゾンとに大きく映し出されるのが印象的であった。
舞台上の生演奏の方がむしろ楽しめた。
上演時間は、途中20分間の休憩を入れて、2時間15分。
映画版の『オーランドー』
1992年、サリー・ポッター監督・脚本、オーランドー役はティルダ・クリスプ
|