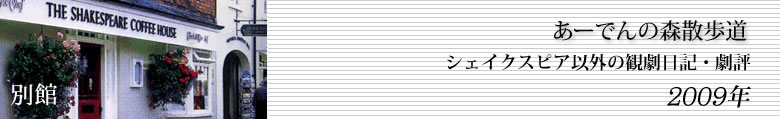
| 009 11日(土) シリーズ・同時代 【海外編 No. 2】 『シュート・ザ・クロウ』 | |
|
|
【観劇メモ】 終演後に原作者のオーウェン・マカファーティーを招いてのアフタートークが非常に参考になった。 まずタイトルの「シュート・ザ・クロウ」(Shoot the crow)はスラングでto goの意味で、使われ方としては、仕事が終わったあとにちょっと一杯行こうかとか、この舞台では映画に行く、という使われ方をしているということであった。 翻訳者の一人、小田島恒志はロンドンでこの舞台を見た時、話していることがさっぱり分からなかった、台本を読んだらもっと分からなかったと述べている。 アイルランドの方言や特殊な言い回しがあって辞書にも載っていない単語の使い方があって、翻訳者泣かせだったということである。 またこの舞台はタイル職人たちの仕事場風景で成り立っているが、オーウェン自身が10年間このタイル職人の仕事についていて、このドラマを書いたときは本職がタイル職人でドラマを書くのはパートタイム・ジョブだったということである。 しかし彼が描こうとしているのはタイル職人ということではなく、仕事そのものについてであるという。 この日、タイル職人のディン・ディン(平田満)は社長からの紙切れ1枚で退職となる。 彼の年齢設定が65歳であるから定年を迎えての退職ということになるが、やりきれないのはたった1枚の紙きれで長年務めてきた職場を去らねばならないということ。 仕事一筋に生きてきたディン・ディンは仕事がなくなることに耐えきれない。 それで彼は窓ふき仕事の権利を買おうとしている。 そのためにはまとまった金がいるために、彼は相方の若者ランドルフ(柄本佑)に職場のタイルを盗んで売り飛ばす相談をもちかける。 ところが別の部屋で仕事をしているピッツイ(阿南健治)も娘がフランス留学することになり、そのための金が必要になり、彼も相棒のソクラテス(板尾創路)に同じようにタイルを盗んで売り飛ばす相談をかける。 この二組の計画はお互い同士秘密にしておくことになっているのが、ソクラテスが途中抜けたために慌てたピッツイがランドルフに相方をつとめるように持ちかけたために、ソクラテスが戻ってきてこの計画がお互いにばれてしまうだけでなく、秘密だと言っておきながら話を別にもちかけたことで、お互いの信頼関係が崩れてしまう。 そこから彼らの本音の言い合いが始まる。 実はお互いが本当は一緒に仕事をするのがいやでならないのに、我慢してやっていたことが暴露される。 肝心なのはこのことだと思う。 誰もが自分の仕事を本当に好きになれることなどまれなことだと思うし、また職場の人間関係においても大半が我慢しながら適当に合わせてやっているのが実態だと思う。 しかしながらいざ仕事をやめるとなると、ディン・ディンのように明日から仕事がないということに耐えられなくなる。 何か仕事をしていなくては自分という存在の価値観を失ってしまいそうで不安になるのだ。 その日、最後の仕事が終わったと思ったら、実はまだもう一部屋のタイル貼りが残っていた。 ピッツイは仕事を続けていくためには断ることはできないとその仕事を受けるが、ソクラテスはその日の出来事の中で目覚めて、仕事より家族との約束だと、息子と映画に行くことを選んで仕事を放棄して帰って行ってしまう。 ピッツイは社長に言いつけると罵りながらも、彼が行ってしまうと、ソクラテスの言うことが正しいと、彼の仕事まで引き受け、おまけに残業代も彼がやったようにして支払われるように取り計らう。 お互い罵り合った後でも、仕事を続けていく以上、最低限必要なことがある、そんなことを訴えてくる作品でもある。 ロンドンの舞台では、この二組の現場は回り舞台にしてあって、表に出ているのは一組だけで、もう一組はその間タイル貼りの仕事を休んでいられるのに対し、田村孝裕演出の舞台では、二つの部屋、背景もすべてセットが見えており、役者は休む間もなく動いていなければならない。 また、このドラマはオーウェンの地元であるベルファストでは上演されていないのに、東京で上演されたということでもオーウェンにとっては感慨深いものであったようだ。
(アフタートークには、司会を平川大作、翻訳者の小田島恒志と浦辺千穂、演出家の田村孝裕、新国立劇場芸術監督の鵜山仁、そしてオーウェンとその通訳が参加)
|