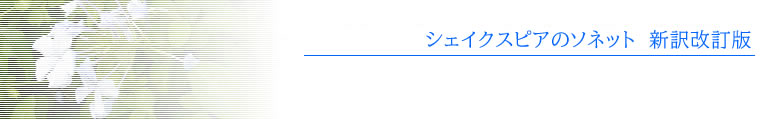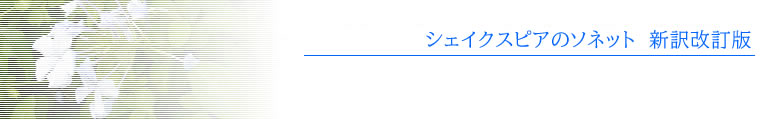過ぎゆく年の悦びであったきみから
離れて過ごすわたしはまるで冬のよう
凍える思いで暗い日々を過ごす
老いたる十二月のなんと荒涼たることか。
きみと離れていたその時節は夏だった
実りの秋が豊かな収穫に身を膨らませ
春の好色が産み出す実りのさまは
夫を亡くした未亡人が孕んだ子宮のよう。
だが、この豊かな実りもわたしが思うには
父無し子か、孤児のはかない定めでしかない
夏も、夏の喜びもきみに仕える従者であり
きみがいなければ、小鳥たちさえも沈黙したまま。
たとえ小鳥たちが歌おうとも、暗い調子なので
木々の葉は、冬が近いのを恐れて青ざめている。
How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days seen,
What old December’s bareness everywhere!
And yet this time removed was summer’s time,
The teeming autumn big with rich increase
Bearing the wanton burden of the prime,
Like widowed wombs after their lords’ decease:
Yet this abundant issue seemed to me
But hope of orphans, and unfathered fruit;
For summer and his pleasures wait on thee,
And thou away, the very birds are mute;
Or if they sing, ’tis with so dull a cheer
That leaves look pale, dreading the winter’s near. |