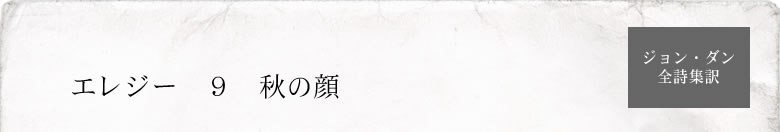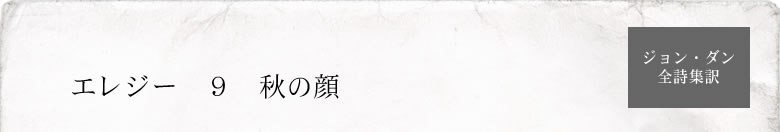春の美しさも、夏の美しさも、
秋の顔の優雅さには及ばない。
若さの美は愛を強いるが、それは暴虐、
秋の顔は相談ずくだが、逃れられない。
愛することを恥とするなら、ここでは恥ではない、
愛情はここでは尊敬の名を得る。
彼女の若き日は黄金時代であった、それは本当だ、
だが今は精製を重ねた黄金で、常に新しい。
かつては灼熱の燃える炎であったが、
今は穏やかな温帯気候である。
美しい瞳、そこから生じる熱を求める者は、
熱病の苦しみの中で疫病を求めるに等しい。
この顔のしわを墓場と呼んではならない。それが墓場なら、
愛の墓場となろう。愛には他に居場所はないのだから。
愛はここで死んでいるのではなく、隠者のごとく
その塹壕から離れないと誓いを立てて座っている。
彼女が死ねば愛も死ぬ、それまでは愛はここで
墓を掘るのではなく、記念碑を建てるのだ。
愛はどこにいても住めるのだが、
今はここを定住の住処(すみか)にしている。
ここは、いつも夕暮れ時、昼でもなく、夜でもない。
官能の悦びこそないが、悦びに満ちあふれている。
彼女の言葉はことごとく、それを聞く人達にとってふさわしく、
饗宴に与ることもできれば、相談に乗ってもらうこともできる。
これこそ愛の樹であり、青春は愛の下生えに過ぎない。
そこでは六月のワインのように、愛は血をたぎらせる。
その時こそ愛の季節の到来、他のものには
味覚も食欲も失せてしまう。
クセルクセス(注:1)は珍しいリディアのスズカケの木を愛したが、
それは古きがゆえであったし、他にはそんな大きな木がなかったからでもある。
また、若くても、自然の恵みによって
若さとともに年寄りの栄誉である不毛でもあったからでもある。
長い間求めていたものを愛すというのなら、老いこそ
五十年かかってやっと到達するものである。
束の間のものを愛するなら、それはすぐに朽ち果てるものでしかなく、
老いこそ最後の日に最も愛おしいものとなる。
だがそれを肌のたるんだ冬の顔と呼んではならない。
それは浪費家の財布のように凋んだ、魂の袋でしかない。
冬の顔の眼はこの世のすべてが陰と見えるので、内に光を求める。
その口は、造作であるというより、すり減ってできた穴である。
歯はことごとく四散(注:2)してしまったので、
復活の日には魂を困らせることになるだろう。
そんな生きながらにして死んだ顔を僕に向かって口にしてくれるな、
そんなものは老いたというより骨董品だ。
僕は両極端を嫌う。だが、僕は一日を過ごすのに
揺籠よりは墓を選ぶ。
愛の自然な作用もそのようなものだから、
僕の愛もひたすら下っていくものであり、丘を下るようでありたい。
上り坂の美人を喘ぎながら追うのではなく、
家路に向かう人達とともに、潮の引くように引き下がっていきたい。
【訳注】
この詩は稿本によっては『唄とソネット』に入れられている。1633年の版では『エレジー』として入れられたが、主要部の『エレジー』とは別の小グループに分けられていた。1635年の版で『エレジー 9』となった。
題名については、稿本により『ハーバート、後のダンヴァーズ夫人』『シャンドイズ夫人の秋のエレジー』『老婦人のパラドックス』『未亡人』などと題されている。
ダンの伝記作者であるアイザック・ウォルトンによれば、この詩は1600年作、タイトルとなっているダンの友人ジョージ・ハーバートの母マグダレン・ハーバートは当時33歳であった。
注:1 クセルクセスが愛したスズカケの木=ヘロドトスによれば、アケメネス朝ペルシアの王クセルクセスはリディアで見つけたスズカケの木の大きさと美しさを熱烈に愛したが、その木は実を結ばない木でもあった。
注:2 最後の審判の日には、人の魂は、復活してバラバラになった体の部分と一体になると思われていたので、身体の一部である歯が四散してしまうと魂と一緒にすることができなくなる。
|