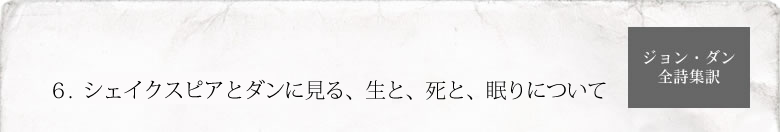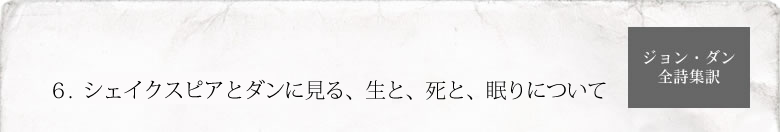はじめに
シェイクスピアの死生観、生と死と眠りについては、ハムレットの有名な独白に集約されてしまいそうである。
ダンの詩においても、随所にその死生観、生と死と眠りについては触れられている。
しかしながら、この両者は同時代に生きていたとはいえ、二人のその表現は似ているところがありながらも、根本的なところで異なるものがある。
その違いを一口で表現するなら、シェイクスピアのそれは具体的、肉体的、世俗的であるのに対して、ダンのそれは、観念的、精神的、宗教的な感じのするものである。
死とは眠りであるというのは聖書にも見受けられる。
『ヨハネによる福音書』には、<「わたしたちの友ラザロが眠っている。しかし、わたしは彼を起こしに行く。」弟子たちは、「主よ、眠っているのであれば、助かるでしょう」と言った...そこでイエスははっきりと言われた。「ラザロは死んだのだ。」...イエスは言われた。「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。」(11章11−25節)とあって、死とは眠りであると述べられているが、それは復活を前提にしているからである。イエスがラザロの死を「眠り」と言ったのは、眠りの後に寝覚めがあるように、死の後に復活があることを前提にしているからである。(注1)
ルネサンス期においては、レオナルド・ダ・ヴィンチがその手記の中で、<おお寝坊ものよ、眠りとは何であるか?眠りは死に似たものである。おお、それではなぜおまえは、生きながらいやな死人に似た眠りをむさぼるのをやめて、死後に完全な生き姿を残す作品をこしらえないのか?>と記している。(注2)
「眠り」について言うならば、ダンは聖書の考えに近く、シェイクスピアはダ・ヴィンチの考えに近いと言えるだろう。
ダンの見方が聖書に近いのは、彼が世俗にある時から聖職の道を勧められていたほど聖書に関する知識が豊富で、後半生が聖職であったことからも頷けることである。
シェイクスピアの作品中における死と眠りについては『ハムレット』でほとんど集約できると思うが、「生」(生まれてくること)についてはリア王の台詞、「人間、泣きながらこの世にやってくる」がその代表格だろう。
ダンにおける「生」は、これもまた宗教的、聖書的である。
1590年代半ばに書かれた『諷刺詩1』の、「生まれた時も、死ぬ時も、僕らは裸ではないか」(At birth, and death, our bodies naked are)は、『ヨブ記』の「わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう」(1章21節)に通じる。ダンは、後に説教集の中でもこの考えを、聖書を引用して説いている。
(注1)Wikipedia「死の説教(1)病、眠り、そして死」より引用。
(注2)杉浦民平訳『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』(岩波文庫)上巻の「人生論」の中の1節(p.56)。
その1 「生まれる」ということについて
シェイクスピアの作品とダンの詩から「生まれる」ということに関しての見方をみてみよう。最初にシェイクスピアの『リア王』から。
‘Thou must be patient. We came crying hither.
Thou know’st the first time that we smell the air
We warl and cry.’ (King Lear 4.5.170-2)
‘When we are born, we cry that we are come
To this great stage of fools.’ (4.5.174-5)
「忍耐せねばならぬぞ。人間、泣きながらこの世に
やってくる。そうだろう、初めて息を吸いこむとき、
おぎゃあおぎゃあと泣くだろう」
「人間、生まれてくるとき泣くのはな、この
阿保どもの舞台に引き出されたのが悲しいからだ」
次にダンの詩を引用する。
‘At birth, and death, our bodies naked are;
And till our souls be unapparelled
Of bodies, they from bliss are banished. (Satire 1, 42-3)
「生まれた時も、死ぬ時も、僕らは裸ではないか。
それに、僕らの魂も、肉体という衣裳を脱ぎ捨てるまでは、
神の祝福から追放されたままだ」(『諷刺詩1』)
‘We are born ruinous: poor mothers cry,
That children come not right, nor orderly,
Except they headlong come, and fall upon
An ominous precipitation’ (An Anatomy of the World, 95-8)
「我々は破滅に向かって生まれてくる。哀れ母親は、
赤ん坊が、頭から先に生まれるという
不吉な前兆の落下の出生でなければ、
無事、正常に生まれないことを嘆くのだ」(『この世の解剖』)
ここでは何も付け加えて説明することはない。ただこの章の「はじめに」で述べた、シェイクスピアとダンの考え方について見てもらうだけでよい。
その2 死と眠りについて
少し長くなるがハムレットの有名な’To be, or not to be’の独白における死と眠りについての台詞を引用する(原文は省略)。
「死ぬ、眠る、それだけだ。眠ることによって終止符はうてる、心の悩みにも、肉体につきまとうかずかずの苦しみにも。それこそ願ってもない終わりではないか。死ぬ、眠る、眠る、おそらくは夢を見る。そこだ、つまずくのは。この世のわずらいからかろうじてのがれ、永の眠りにつき、そこでどんな夢を見る?それがあるからためらうのだ、それを思うから苦しい人生をいつまでも長びかすのだ」(3幕1場、60-9)
次にダンの詩に現れる「死と眠り」の変遷を見てみる。
1597年7月にエセックス伯のアゾレス遠征に参加したときの書簡詩『嵐』から。
‘Sleep is pain’s easiest salve, and doth fulfil
All offices of death, except to kill’(The Storm, 35-6)
「眠りは苦痛を和らげる最も手近な薬であり、
殺すことなく、死の効用をすべて果たしてくれる」
次に、エリザベス・ドルリーの死を悼んでの『挽歌』と『二周忌の歌』から。
‘And the world’s busy noise to overcome,
Took so much death, as served for opium’ (A Funeral Elegy, 79-80)
「この世の雑音を乗り越えるため、
眠りを誘う阿片のかわりに死を選んだのだった」
‘Think that they bury thee, and think that rite
Lays thee to sleep but a Saint Lucy’s night’
(Of the Progress of the Soul, 119-120)
「彼らがおまえを埋葬していると思うなら、それは
聖ルーシーの夜におまえをひと眠りさせているだけだと考えよ」
最後に宗教詩の中の『神に捧げる瞑想』のソネット6番から。
‘And gluttonous death, will instantly unjoint
My body, and soul, and I shall sleep a space,’ (Divine Meditations 6, 5-6)
「そして、貪欲な死が、直ちに私の肉体と
魂を切り離し、私はしばらくの間、眠りにつくことになるだろう」
ダンの詩では年齢とともに現世的な考え方から、宗教的な考え方への変遷が感じられる。
3 人生観、あるいは死生観
「この世界はすべてこれ一つの舞台、人間は男女を問わずすべてこれ役者にすぎぬ、それぞれ舞台に登場してはまた退場していく、そしてそのあいだに一人一人がさまざまな役を演じる、年齢によって七幕に分かれているのだ」に始まる『お気に召すまま』のジェークイズの台詞は、「波乱に富んだ奇々怪々の一代記をしめくくる終幕は、第二の赤ん坊」と続いて、人生が円環構造で閉じることを示唆して閉じられる。
シェイクスピアにおいても、ダンにおいてもこの世が舞台であり、劇場であることは再三にわたって語られるが、それを通して見られる人生観、あるいは死生観は、シェイクスピアの場合、このジェークイズの台詞に集約されているといってもいいだろう。
ダンの詩では、『魂の遍歴』や『二周忌の歌―魂の遍歴について』において、人生の、というより人類の、長大な人生観、死生観が繰り広げられる。
ここでは視点を変えて、ダンが聖職についてからの説教集の中で語っていることについて見てみたい。
‘Take a flat Map, a Globe in plano, and here is East, and there is West, as far asunder as two points can be put: but reduce this flat Map to roundness, which is the true form, and then East and West touch one another, and are all one: So consider mans life aright, to be a Circle, Pulvis es & in pulverem reverteris, Dust thou art, and to dust must return; Nudus egressus, Nudus revertar, Naked I came, and naked I must go; In this, the circle, the two points meet, the womb and the grave are but one point,(注1)
イタリック体の文は、『創世記』3章19節、および『ヨブ記』1章21節からの引用である。ここでダンが語っているのは、地図を広げてみると、平面では東と西は離ればなれであるが、丸にすると一つになる。同じように人生も円と考えれば、生と死は二つの点が合わさって一つの点となり、誕生と死はまったく一つとなるということである。
『創世記』の「塵に過ぎないおまえは、塵に帰る」は、ダンの詩では『諷刺詩5』の中で、「人間はみな塵に過ぎない」(All men are dust)と歌われ、『ヨブ記』の「わたしは母の胎を出た。裸でそこに帰ろう」はすでにこの章の「その1」でみたように、『諷刺詩1』で歌われている。ダンは世俗にある時から、すでに宗教的な諦観を抱いていたかのようである。
ダンはこの同じ説教の中で、こうも言っている。
「人生の年月は七十年ほどのものです。健やかな人が八十年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。またたく間に時は過ぎ、わたしたちは滅び去ります」。
この章の「はじめに」で、シェイクスピアの人生観は具体的、肉体的、世俗的で、ダンのそれは観念的、精神的、宗教的と述べたように、こうやって比較して見ると、そのことを改めて感じる。
シェイクスピアは舞台の人、劇場の人であり、ダンは本質的には宗教的な人、という風に感じる。
(注1) John Donne’s Sermons on the Psalms and Gospels, Edited by Evelyn M. Simpsonより
ページトップへ |