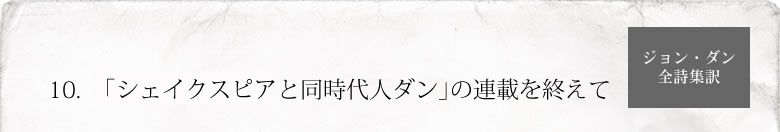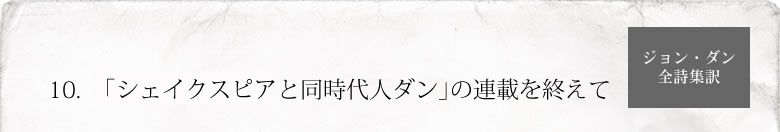僕にとっての詩の歓びとは
ジョン・ダンの詩を読み、訳していくうちにシェイクスピアと似た表現にいくたびも出会い、気付いた箇所に附箋を付けていった。ホームページに、ダンの全詩集訳を掲載するかたわら、そこで思いついたことなど記していくつもりで「ダン談話室」の部屋をこしらえた。
そこへ「シェイクスピアの森通信」への連載の話をいただき、「談話室」に気楽に書いていくつもりのものを少しばかり系統的にまとめて連載を始めることにしたのだった。
自分にとって詩を読む楽しみは、感動、驚き、共感、そして発見にあるが、なによりもこころが豊かになることが一番である。
ダンを読んでいて感じたことの一つが、シェイクスピアと似た表現が結構多くあることであった。その発見が一つの楽しみとなり、シェイクスピアと同時代人としてのダン、あるいはダンと同時代人のシェイクスピアを考えることにつながった
シェイクスピアもダンも、イギリス・ルネサンス期の詩人であり、古典再発見からくる共通性は同時代人として当然のことかも知れない。
たとえばシェイクスピアによく出てくる死と眠りの関係については、この連載のはじめの方でも触れたが、レオナルド・ダ・ヴィンチの「手記」にもあったことを発見し、また世界の関節が外れたという表現は、この連載中に読む機会があった岩波文庫の『ローマ諷刺詩集』のユウェナリスの「諷刺詩」第6歌の中に、「全世界は炎上し、骨格を崩し、倒壊した」(国原吉之助訳)の中に発見した。
そのようにしてみれば、シェイクスピアもダンも特別な新規なことを言っているのではなく、新たなシチュエーションの中で先人の言葉を甦らせていることが分かる。それらの言葉が、シェイクスピア、ダンというフィルターを通して固有なものとして新しく生まれ変わっている。そのことを発見していくプロセスに、詩を読む楽しさの一つがある。
中学時代から詩を読み始めて、詩に対する「驚き」を感じたのは萩原朔太郎であり、高校生の時にふれた西脇順三郎の詩と詩論には驚きと感動と共感で圧倒される思いであった。
発見ということについては、T. S. エリオットの『荒地』の冒頭の詩、「死人の埋葬」(The Burial of the Dead)が、僕にとっては鮮烈であった。周知の通り、それは次のような言葉で始まる。
April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain. (1-4)
初めてこの詩を読んだ時には、ただわけもなく興奮したように記憶している。
なぜ四月が最も残酷な月であるのか、四月は日本では春、優しい季節である。その逆説的な表現に驚かされたのだと思う。
だが、翻訳でチョーサーの『カンタベリー物語』を読んだ時、さらに驚かされた。そこには、冒頭に次のようなことが書かれている。
甘露のような四月の雨がひとふりすると、かわききっていた三月の大地が底までうるおい、 木々は生気をとりもどし、つぼみもほころびかけてきた。(金子健二訳)
エリオットはチョーサーの本歌取りをし、それをパラドックスに表現したアイロニーだということを発見して驚くとともに、その発見を喜んだ。
これを注釈で知ってエリオットを読んでいたとしたら、その感動は多分なかったかもしれない。驚きがなく、ましてや発見の喜びもないからだ。
同じような経験を日本の詩、宮沢賢治の「永訣の朝」でも味わっている。
宮沢賢治は中学時代から愛読してきた詩人であるが、なかでもこの「永訣の朝」は忘れ難い詩である。それは次のように始まる。
けふのうちに
とほくへいってしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふっておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゅとてちてけんじゃ)
この「あめゆじゅとてちてけんじゃ」という言葉は中学生の僕には何の事だかはっきりとは分からなかったが、詩の中でいくたびも繰り返されるこの言葉が何かとても親しく響いて忘れることができなかったし、切なくも感じられたのだった。
しかしながらこの言葉が「あめゆき(雨雪)とってきてください」と表現されていたら、その感動はおそらく薄れていただろう。この呪文のように響く言葉を口ずさむことで僕は、そこはかとない悲しみを感じていたと思う。
発見ということについて言えば、詩人自らの発見を詩にした例がある。
― I was bornさ。受身形だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ。自分の意志ではないんだね―(「I was born」吉野弘)
この少年の発見は詩人の発見でもある。
詩の読み方には人それぞれにあると思うが、僕にとっては二通りの読み方をしてきたように思われる。
ひとつは、こころ、感情で読む詩。
もうひとつは、頭脳、知性を働かせて読む詩。
この二つは厳密に区別されるものではないが、大まかに言えば、僕にとってシェイクスピアの詩は前者に属し、ダンの詩は後者に属している。
そのどちらにも、驚き、感動、共感、そして発見の喜びはある。
僕は振り子のように、そのどちらにも振れながら、そのときどきに応じて読み分け、楽しんでいる。そしてこれからも、色々な詩を読む楽しみの歓びを生きがいとしたいと思っている。
森通信の連載への感謝と、これまでつきあっていただいた読者の方にお礼申し上げます。
ページトップへ |