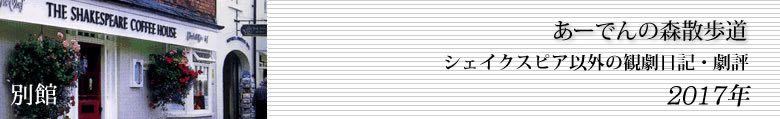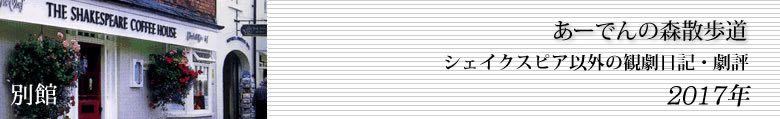作・演出/つつい きえ
出演/(チームみかん)石井麻衣子、石渡未紀、かくたなみ、和海アキ+山本恵太郎
中野新橋プライムシアター、料金:2800円(前売り)
|
【観劇メモ】
退屈紛れにトランプ遊びなどで時間をつぶしている4人の魔女が、聖域として守っている「土地」に一人の男が引っ越してきたことから始まる。
男の招待で一番年下の魔女が偵察目的でその招きを受けて男の家みちを訪問するが、男は人を殺したい欲求から人の多く住む都会から逃れて来たのだが、その魔女が自分の欲求を満たしてくれそうだと、眠り薬の入ったお茶を出し、眠ったと思ったところで魔女の首を絞めて殺す。
ところが魔女は死なないことになっていて、いくら殺してもすぐに生き返ってしまうことから、男は彼女を自分の欲求を満たしてくれる女神として不眠不休で殺しを続け、最後にはそのために男自身が死んでしまうという話。
その間、他の魔女たちは『マクベス』の魔女の台詞をそのまま語って暇を興じる。
そして、ちょっぴり緊張感を感じさせるのは、一番年長の魔女が秘匿していた魔女を殺すことをできる魔法の短剣が紛失していたのに気づき、魔女の一人がネットのオークションで売っていたことが分かる。
それを買った者は、なんとその引っ越して来た男であったが、何事もなく取り返してしまうので少し拍子抜け。
作者によれば、タイトルにあるスティルネセは、フィンランドにあるスティルネセ・メモリアルという美術館に由来し、17世紀の魔女裁判で処刑された犠牲者を弔う記念慰霊碑だという。
そうであれば、その話に関連した物語であればもっと違った面白い話になりそうだと思い、残念な気がした。
上演時間は、45分。
|