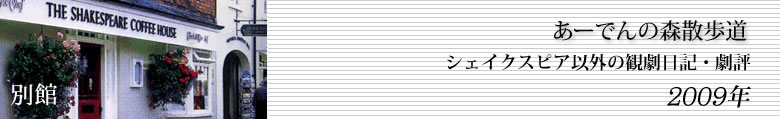
| 013 7日(火) 『現代能楽集 鵺』 | |
|
|
【観劇メモ】 鵺を通して、「平家物語」の源頼政から現代まで突き抜ける。 「平家物語」に登場する鵺は、崇徳院の御霊ともいわれる。 鵺を恐れるのはそこに故人の恨みを見るからであり、その恨みは実は、己が写す鏡。 鵺を退治した源頼政もまた、鵺の預言に従って果てていく。 そして場所と時代は、現代のとある川辺へと移る。 逃げた犬を探して鎖をつけた首輪を引きずって男が雨の川辺を歩いていて、昔の恋人に出会う。 女は自分が捨てた女。女は鵺となって男の心の鏡となり、男はやがて女と川に消えていく。 次なる場所は東南アジア。 そこは、(はっきりとは主張されないが)ヴェトナムの空港。 消えた男を追う女。 男は村上という名前のパスポートを無数に持つ。 男は人買い。 人買いの目的はいろいろ。 臓器移植のための人買いは、今国会で臓器移植法の法案提出とからめてみれば、きわめて時事的。 鵺は、猿の顔、狸の体、蛇の尾、そして虎の手足をもつ。 鵺は、これまでのひとりの女から、ここに至って4人の人物が一体となって国家という比喩の鵺となる。 村上という謎の男、その妻と思われる女、村上の勤めていた会社の同僚(?)で女を愛している男、そして村上の人身売買のビジネスのライバルである現地の青年の4人。 それまで、鵺は個人の怨霊であったものが、国家という体制の鏡としての鵺となるとき、坂手洋二の寓意を見る。 鵺は醜いもの、しかし己を写し出す鏡、とするならば、この国(=日本)の醜さを映し出すアレゴリー感じる。 プログラムにある坂手洋二と鵜山仁の対談が面白い、痛快である。 「芸能が国家に管理されていくというプロセスにも共通性がある。劇場の有様も当然それに応じて変わる、観客の質も変わってくる。でもそんな「国家の劇場」で、芸能が演ずることはというと、勝った人より負けた人の物語の方がはるかに多い」。 新国立劇場の人事の問題の不透明性さに一矢を報いた発言として痛快である。
|
| 014 10日(金)夜、韓国国立劇団公演 『胎(て)―The Life Cord』 | |
|
|
|
| 015 28日(火)昼、『現代能楽集 イプセン』 | |
|
|
【観劇メモ】 イプセンの作品4編からなる構成。 「ノーラは行ってしまった」(『人形の家』)、「ぶらんぶらん」(『ブラン』)、「野鴨中毒」(『野鴨』)、「ヘッダじゃない」(『ヘッダ・ガブラー』)を、休憩なしで約2時間半の上演。 この中でまったく読んだことがない作品は『ブラン』。 『人形の家』はこの劇を見るにあたって再読していたので、やはり一番すんなりと入ってきたし、改作された部分との整合性もとりやすかった。 ノーラの家出の物語が展開されたテスマン家を、毎年クリスマスの日、つまりノーラが家を出て行ってしまった日、別のノーラが訪れるという物語で、そこにいるのは、かつて存在したノーラの夫ヘルメル、医者のランク、そしてノーラの家出の原因をなしたニルス・クロクスタの亡霊。 そのノーラがテスマン家を初めて訪れたのが、ノーラがヘルメルと結婚した時の年齢で21歳の時。 そして今それから8年の歳月が過ぎていて、ノーラはこの日を最後の訪問と決めている。 別のノーラが亡霊たちと、ノーラが家出をした時の状況を再現させながら、現在と過去の時間が交錯して展開していく。 作品として印象に残ったのは、馬淵英俚可がノーラを演じた「ノーラは行ってしまった」と、紺野美沙子がヘッダを演じた「ヘッダじゃない」の2作。 終演後、作・演出の坂手洋二とノルウェーナショナルシアター・フェスティバル・ディレクターのバー・クレメトセン女史とのアフタートーク。 短い時間ではあったが、ノルウェーにおけるイプセンの地位や、演劇の状況をよく知ることができた。 イプセンは、いうなればノルウェーのシェイクスピアで、彼の作品の台詞はシェイクスピアのそれと同じく、一般の人々の生活の中で格言のようにして生きていて、その譬え話として、イプセンの劇を見た子供が、その感想として、諺ばかりで面白くなかったという小話がバー女史から紹介された。 質問役の坂手洋二の海外の演劇状況に対する関心と、その幅広い知識にも感心させられた。
|
|