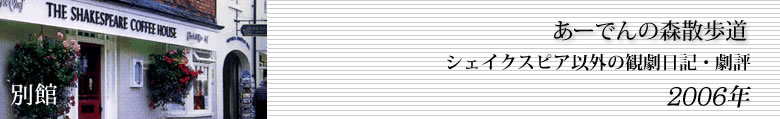
|
|
【感想】 震災後、崩壊した二階家の二階だけが残っていて危険地域で立ち入り禁止の区域であるにもかかわらず二人の兄妹が暮らしている。 震災の前には妹麻希子(富田靖子)が精神を病んでいて、兄晃郎(近藤芳正)が面倒を見ていた。そして震災の後には、兄はアル中となり、酒ないでは過ごせなくなり、食料の配給チケットまで酒に変えてしまう。 麻希子は、日陰に作った土の代わりに砂利でこしらえた菜園に、食料とするために何かの種を植えて、毎朝貴重な水を与えるのを日課としている。そして夕方には麻希子に思いを寄せる警察官村田(菅原永二)が届けてくれる配給のわずかな食料をさいて、潰れてしまった一階に埋まっている父に与える。父が生きているということは幻想でしかないのだが、麻希子には砂利の菜園から植物の芽が出てくるという期待(あるいは希望と信念)と同じくらい真実なことである。 そこへ一人の小説家一ノ瀬(岩松了)がやってくる。一ノ瀬にはどうやら見えない虫がとりついているようだ。一ノ瀬は才能がないのに、編集員であった晃郎の上司であった一ノ瀬の父親の願い(指示)で、一ノ瀬の文作を手伝い作品を掲載するが、ついに見限ってしまう。そのことに怒って一ノ瀬は晃郎を訪ねてきたのだった。そしてそれから3人の奇妙な共同生活が始まる。 麻希子は一ノ瀬の兄への怒りを抑えるために、一ノ瀬が冗談半分に言ったタバコとチョコレートを求めて、外の世界へと初めて一人で出て行く。そのことを知った晃郎は気が狂ったようにして、妹を探しに行くように一ノ瀬に頼む。麻希子はせっかく落ち着いてきているのに、外へ出て行くことは非常に危険だというのだ。しかし本当に外に出て行けないのは、実は晃郎だということが分かる。 外に出て行った麻希子は、そこでボランテイア活動しているという鳥居(峯村リエ)と出会い、ボランテイアの仕事を引き受ける。そのボランテイアとは淋しい思いをしていて話し相手を求めている人の相手をすることだという。それがどんな仕事であるかは容易に想像できることなのだが、麻希子にはそれが本当にボランテイアの仕事だと思っている(あるいはそのフリをしている?!)。しかし麻希子は別の自分に目覚め、配給や待遇に差別を受けている中国人や韓国人の子供たちへの相手をするという本当のボランテイア活動も始める。 このドラマでは、特に鳥居の台詞においてであるが、中国人や韓国人への差別的表現が多発される。それは関東大震災の後のような状況を髣髴させるものだった。 麻希子は事件に巻き込まれ、そのことを村田が泣きながら晃郎に伝えにくるが、「麻希子さんが、・・・・・」のあとの言葉が出ない。 一ノ瀬は、晃郎に促されて自分で小説の筋を考えていく。 一人の女がいて、砂利の菜園に一生懸命水をやっている。女は何の種を植えたのだろうか?その解決を求めて考える。そして一ノ瀬は考えつく。植えるべき種などなかったのだと。かわりに女は土に手紙を植えた。そしてその願いが届くようにと土の奥深く埋め込んだ。 その女は、「アジアの女」だと一ノ瀬は叫ぶ。 そして恐れていた余震が突然襲ってくる。 闇が晴れて、明るい光が燦然と輝いている。 女の願いが届いて、そのあたり一面に草が芽を出しているのだった。しかし、もうそこにはいるべき人がいない。虚無だけがある。真空地帯のようにして。そしてそれがこのドラマの終結―。観客のかすかなとまどい。 話の筋を追っても何にもならないが、虚無的な不条理を感じるドラマである。 (休憩なしの約2時間の上演時間) |
|
|
|
【感想】 今回の演出では「荒唐無稽なブラック・ユーモア」として兄弟の謝罪ゲームに主眼が注がれているようだった。 場所はアイルランドの西部の片田舎、リーナンが舞台。この村では殺人が起こっても事故死として誰も逮捕されずにいる。コナー兄弟の父の葬式が終わった日から舞台は始まるが、その父親は銃の暴発による事故死ということになっているが、実はコナー兄弟の兄のコールマン(石住昭彦)が撃ち殺したのだった。 コナー兄弟は絶えず兄弟喧嘩ばかりしており、このままではいつか二人は殺しあうことになると、この村の神父ウエリシュ(上杉陽一)は、自分の死をかけて二人が仲良くするように遺書で説得しようとする。 神父の葬儀を終えてコナー兄弟は仲良くしていくことを試みようと、お互いが相手にした罪の告白と謝罪をあたかもゲームのように交互に行う。 しかし兄コールマンが弟ヴァレン(吉見一豊)の犬の耳を切って殺したことの告白で、ヴァレンは包丁で兄を殺そうとするが、コールマンはいち早く銃を身構え、弟の大事にしていた電子レンジや磁器製のミニチュアマリア像を粉々に砕く。ヴァレンは兄の撃った弾の数でもう銃には弾が残っていないはずだとおもうが、兄との心理戦で負け、包丁を投げ出す。喧嘩の後コールマンは酒屋へと飛び出して行く。ヴァレンは銃を調べてみて弾が残っていたことで、コールマンが本気であったことに慄然として憤りを感じる。しかし実の父親を銃で撃ち殺したこと、その原因も髪型にけちをつけられたことがきっかけであったことを考えれば、コールマンが本気で弟を撃ち殺すこともありえたことは想像がつくことである。 印象的なのは、神父の遺書にガーリーン(冠野智美)のことがひとこともふれられていなくて、彼女が絶望的になるところである。彼女が父親の酒をかすめてその酒を売って回っていたのは、その金で神父にマリア像のペンダントを贈るためだった。リーナンの村では良心というものがまったくないように思われる中で、唯一の救いであったかもしれないのに、神父はそのことを知らないまま死んでしまった。ガーリーンの本名がマリアだというのも象徴的である。 胸に異物を吸い込んだような暴力的な違和感を感じる作品である。
|