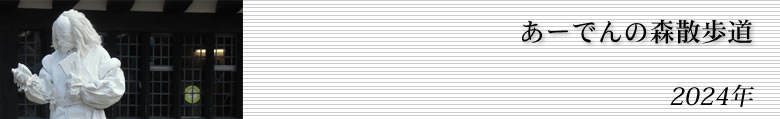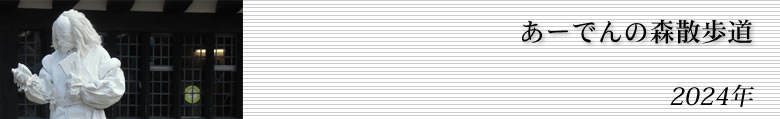チラシには「シェイクスピア・シアター創立45周年記念公演」とあるが、45周年は実は4年前の2020年であった。この時はコロナ禍で中止を余儀なくされ、また同年暮れには劇団主宰者で演出家の出口典雄が亡くなるという不運が重なった。
その後、劇団の中堅俳優であった高山健太を中心に、2022年から新生シェイクスピア・シアターとして新たなスタートを切ったが、再生スタートのメンバーが意見の相違もあって数名が抜けていった。
残ったメンバーにより、今年5月に早稲田小劇場どらま館にて『ペリクリーズ』を上演し、今回は来年のシェイクスピア・シアター50周年記念を前にして、残されたメンバーにとって「素通りできない大切な公演」である幻に終わった45周年記念公演『十二夜』に再チャレンジすることになった。
『十二夜』は1975年に渋谷ジャンジャンでシェイクスピア・シアター旗揚げ公演で上演された作品である。
開演とともに柔らかく響いてくる音楽をバックにして、「音楽が恋の糧であるなら、つづけてくれ」という高山健太が演じるオーシーノ公爵の台詞で始まり、その瞬間から出口典雄が大切にしていた小田島雄志の台詞の口調が心地よく耳に響いてきて、ドラマへと引き込まれていった。
何もない空間で演じるシェイクスピア・シアターの劇は、出口メソッドとも言われる台詞の発声・口調が命であるが、それが忠実に再現されていた舞台であった。
シェイクスピアの劇は、少年俳優が女役を演じていたという当時の時代背景もあって女性の登場が少ないが、今日では逆比例するかのように女性の出演者が多数を占める傾向が増えており、この公演でもそれを反映して女優の出演が多い。
公爵に仕えるヴァレンタインやキューリオを演じる加藤真伎、青木茉依をはじめ、双子の兄妹の兄セバスチャンの照屋りこ、オリヴィアの召使フェービアンを蒼谷明依らが本来男性である役を違和感なく演じた。
出演者の中で注目したのが、今年の1月にSophia Shakespeare公演の英語劇『十二夜』でヴァイオラを演じた山口夕稀南がここではオリヴィアを演じたのと、同じく同公演に出演していた加藤真伎がヴァレンタインや神父役を演じていたことである。このような出会いもまたうれしいことであった。
演技や台詞で注目したのは、フェービアンを演じた蒼谷明依と、サー・アンドルー・エーギュチークを演じた加藤拓二。二人の台詞と演技ははじけるような楽しさがあり、何よりも彼らがその役を演じるのを楽しんでいるのが伝わってきて、その気持ちに観ている自分まで楽しくさせてもらった。
マライヤを演じたミノル純も役を楽しんでいる一人であったが、何より感歎させられたのは彼女が楽士として登場し、本来はフェステが公爵の前で歌う歌を、マイクもピンマイクもなしに歌った生の声の素晴らしさに、ずっとそのまま聞き続けていたいと思ったほど聞き惚れた。
この場面は、高山健太が二役演じる公爵と道化のフェステが同時に登場する場面であるので、どうなるのかと思っていたが、フェステの役を楽士に代えての演出で、却ってそれを楽しませてもらうことが出来た。
ヴァイオラには巻尾美優、アントーニオには奥川陽、シェイクスピア・シアター劇団員の一人である三田和慶は船長とマルヴォーリオを演じると共に舞台監督を務め、西山公介はサー・トービーを演じ、劇団の企画制作から宣伝美術、音響操作までこなしている。
一部ダブルキャストで今回自分が観た回はAキャストで、マライヤはミノル純(Bでは住川佳寿子)、A、Bでキューリオとフェービアンを演じる青木茉依と蒼谷明依が、それぞれの班で交互に入れ替わって演じる。
オリヴィアとセバスチャン、公爵とヴァイオラの二組のカップルが生まれて大円団となったところで、高山健太が演じるフェステの唄で締めくくられ、余情が伝わってくる終りであった。
上演時間は、途中10分間の休憩を入れて、2時間30分。
訳/小田島雄志、原案/出口典雄、演出/高山健太
11月7日(木)18時30分開演、吉祥寺シアター、チケット:4500円
全席自由席(最前列の中央の席にて観劇)
|