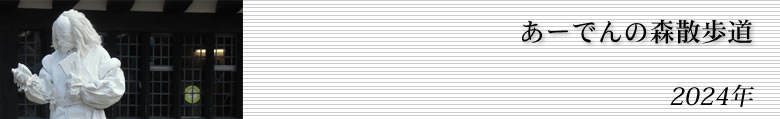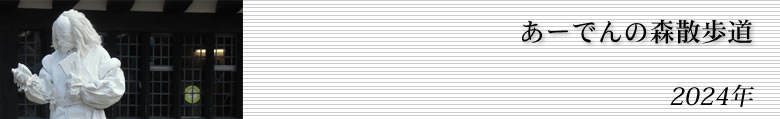昨年は一度もTSC(東京シェイクスピア・カンパニー)の活動を観ることができず、さびしく残念に思っていたが、昨年末にシェイクスピア・カフェでの朗読劇開始を知り、楽しみにしていた。
会場のカフェピカイチは、下北沢の小劇場ザ・スズナリの右隣にあるビルの1階、赤い壁が目印で、ごくごく小さな空間。出演者含めて20名も入れば、というより詰めれば一杯である。
初めての場所ということで早めに行って一番乗りで席を確保。ワンドリンクの赤ワインを味わいながら、出演者で主宰者でもある江戸さんや、ゲスト出演の丹下さんなどと話を交わす。
演目は、『マクベス』と『マクベス裁判』、それに『ヘンリー六世』の第一部と第二部のサフォークとマーガレットの登場する場面で、江戸馨訳の日本語による朗読と、同じ場面の英語での朗読劇で、江戸馨の解説を含めわずか1時間の上演時間であるが、コンパクトながらも充実した中身で、内容的には倍の時間を感じさせる濃密な時間を過ごすことが出来た。
最初の『マクベス』は、楽士として特別参加の奥泉光の横笛の演奏から始まって、「やってしまえばすべてやってしまったことになる」のマクベスの台詞から始まる1幕7場の場面。奥行きと深みのある朗読でマクベスを演じたのは丹下一、対するマクベス夫人は、七色の声を持つつかさまり。英語の朗読は、マクベスに増留俊樹、マクベス夫人を江戸馨。
続く『マクベス裁判』は、1996年が初演で吉田鋼太郎をマクベスにあて書きして書かれたということをはじめて知った。マクベスを丹下一、メフィストフェレスをつかさまり。マクベスを地獄から天国に追放しようとするメフィストフェレを演じるつかさまりの困惑の台詞が面白い。普段は能面のように感情を表に出さないつかさマリの演技は、マクベス夫人の時の台詞の口調とはガラリと趣を変えて、どこかいたずらっぽさを感じさせるような笑みを含んだ表情で、この人の内に秘めた道化的なるものを表出しいたように思えた。
最後の『ヘンリー六世』は、第一部の終わりの部分と第二部の1幕3場の部分で、登場人物はサフォークとマーガレット。第一部の終わりの場面のマーガレットはまだ14歳の初々しさのある可憐な乙女。第二部では、夫のヘンリーの優柔不断さに不満を覚え、すでに鉄の女の片りんを表し始める。マーガレットのこの二つの異なる側面をつかさまりが声を変えて見事に演じるのが聴きどころで、その台詞の妙味を満喫させてくれた。
上演する作品はすべて自分で訳される江戸馨の日本語は、言葉に優しさを感じさせるものがあって、聴いていても心地よく、今回のように一部を切り取っての朗読劇であっても、全体のイメージの想像力を豊かにかきたてさせてくれる。
江戸馨の朗読劇では必ずと言っていいほどエピソードをまじえて劇の解説をしてくれるのも楽しみの一つである。今回、その中で特に印象に残った話が二つある。
ひとつは、『マクベス裁判』を持ってエディンバラ・フェスティバルに参加した時のことで、その時、エディンバラの天気は晴天であったが、突然にわかに雨が降って来たという。会場の観客の一人が、これこそ'Fair is foul, and foul is fair'と言ったという。スコットランドのエディンバラは、一面の荒野を感じさせる風景であるという説明と相まって、『マクベス』の原風景を見る思いであった。
今一つのエピソードは、江戸馨が学会でイギリス訪問時、ちょうど大学の駐車場からリチャード三世の遺骨が発見され、それを無償で見学することができ、リチャード三世を身近に体感することが出来たという話である。
歴史劇としての『ヘンリー六世』の解説も、この劇の魅力をいっそう膨らませてくれるもので、朗読劇を聞く楽しみを倍加させてくれた。
そして、何よりも、4人の声の出演者たちの朗読力の魅力を楽しませてもらった。
構成・演出・訳/江戸馨、『マクベス裁判』作/奥泉光
3月23日(土)15時開演、下北沢・カフェピカイチ、料金/3000円(ワンドリンク付き)
|