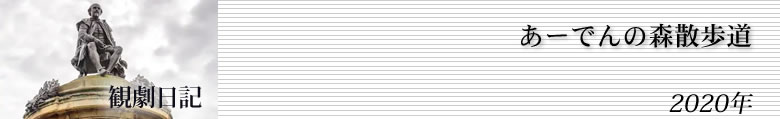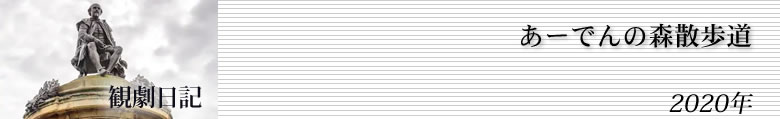|
実に久し振りの本格的舞台の観劇!
チケットの一般発売初日ですでにS席は埋まってしまってA席しか取れなかったのだが、その後、観客席の制限枠が外されたものの、観劇当日、S席をはじめ当初販売されていなかった席の多くに空席が目立った。
2009年から足かけ12年にわたる、新国立劇場での鵜山仁演出による英国史劇8作のシリーズ上演の最後を飾ることになる『リチャード二世』が無事公演されることになったこと自体が嬉しくも、喜ばしい事であった。
『リチャード二世』の原文は全文が韻文でなっており詩劇ともいうべき作品だが、愚王としての不人気と相まってか作品自体もあまり知られていなく、日本で上演されることがほとんどなく、この新国立劇場のシリーズとしての上演は非常にありがたかったし、楽しみでもあった。
鵜山仁の演出は特別に奇をてらうこともなくテキストに忠実で、それだけに原作と並べて鑑賞するに当たっては学習的に観劇することが出来るという利点があるが、いざ観劇後の感想を書こうとすると何から書き始めてよいかいつも迷うことが多い。
開幕の場面と、リチャードがボリンブルックに降伏する場面では、庭師の二人がその場面を傍観するという演出や、ウェールズの隊長とソールズベリーの会話の場面では、ホリゾント上に浮かぶ月が赤く照り輝いている場面などは『ヘンリー四世』に登場するグレンダワーを想起させ、特記すべき感想として印象に残った。
この劇の見どころの一つ、中心はタイトルロールのリチャード二世をどのような人物像として表出するかに興味が向けられる。
本場のイギリスでリチャード二世がどのように演じられ、評価されてきたかをアーデン版のイントロダクションにある上演史から拾ってみると、
「悲しげで、神経過敏、自分の無力さに絶えず動揺するリチャード」(1947年、アレックス・ギネス)
「まぎれもない同性愛者としてのリチャード」(1951年、マイケル・レッドグレイブ)
「冷淡で、知的な鬱状態、空想的で、無関心な性格としてのリチャード」(1953年、ポール・スコフィールド)
「ボリンブルックをマルキストの革命家にして、リチャードを精神病患者の君主にし、ブレヒト的手法でジョーン・リトルウッドが演出」(1954年)
雑司ヶ谷の原書講読会で『リチャード二世』読了後に鑑賞した、2012年のテレビ映画シリーズで制作されたルパート・グールド監督の『うつろな王冠』でベン・ウィンショーが演じるリチャードは「女性性を持つ、受難のキリスト」のイメージが色濃く漂っていたのが印象的であった。
これらのリチャード像に比して、鵜山仁演出で岡本健一が演じるリチャードは一つの型にはめにくいものであった。
岡本健一のリチャードは悪人か?には、見えない。が、善人とも言えない。同性愛者か?この演出ではそのようにも見えなかった。
ボリンブルックの追放を宣告し、ゴーントの死後その財産すべてを没収するまでのリチャードは傲岸不遜であるが、ボリンブルックの前に屈することになると、求められる前に王位を引き渡さねばならぬと思い込み、自ら王位を渡し、自暴自棄というより自虐的となって自己規制喪失に陥っていく。
ポンフレット城の牢獄内で、「牢獄を世界」にたとえる思索の傍白は、母の子宮内に閉じ込められたように、丸くうずくまった状態で語り、リチャードは詩人となっていく。
このように岡本健一が演じるリチャードは多面的顔を持った人物として描かれるが、その人物像評価は受け取る受容者に任せられ、少なくとも自分には女性性や同性愛者的な側面は感じさせないものであった。
リチャードの衣装は純白であったが、振り返ってみると、このシリーズ全作品で担当した前田文子の王の衣装は、浦井健治のヘンリー六世、中嶋しゅうのヘンリー四世、浦井健治のヘンリー五世と、リチャード三世を除いて一貫して純白の衣装であった。
5幕3場で、ボリンブルックが「だれか、私の放蕩息子の近況を知らぬか?」の台詞を聴いたとき、一瞬、『ヘンリー四世』を一部取り込んだのかと錯覚してしまったが、この場面から振り返ってみるに、上演の順序として『リチャード二世』に続いて『ヘンリー四世』を上演するとストーリー的にもつながりやすい感じがしたのも副次的な感想であった。
舞台美術では、このシリーズに一貫して制作してきた島次郎が先年亡くなって、今回は文学座の乗峯雅寛が担当。島次郎の舞台は新国立劇場の拡散的な舞台空間をそのまま生かした美術であったが、乗峯の舞台は対照的に集約的な作りで、舞台演出もその分集約的に感じられた。
出演者もシリーズなじみの俳優が多く出演し、懐かしさとそれぞれの役の違いの演技を楽しむことができたのも、シリーズ作品ならではの醍醐味と言えるだろう。
出演者は、リチャード二世の岡本健一、ボリンブルックに浦井健治、王妃に中嶋朋子、ヨーク公に横田栄司、ノーサンバランド伯の立川三貴、庭師の吉村直、ヨーク公爵夫人に那須佐代子、グロスター公爵夫人に一柳みる、式武官とウェストミンスター修道院長を演じた勝部演之、カーライル司教に田代秀隆など、ほか多数。
キャスティングで個人的な感想を言わせてもらえば、リチャード二世とボリンブルックの役は、王位を簒奪されたヘンリー六世を演じた浦井健治と、王位を簒奪したリチャード三世を演じた岡本健一に、それぞれ逆にした方が自分のイメージに即してした。
最後に、このシリーズで舞台美術を担当した島次郎、出演者でヘンリー四世のタイトルロールを演じた中嶋しゅう、『ヘンリー五世』でハーフラー市長と騎士トマス・アーピンガムを演じた金内喜久夫のご冥福を祈りたい。
翻訳/小田島雄志、演出/鵜 山仁、美術/乗峯雅寛、照明/服部 基、衣装/前田文子
10月6日(火)13時開演、新国立劇場・中劇場
チケット:(A席)6270円(シニア)、座席:2階1列27番、プログラム:1500円
|