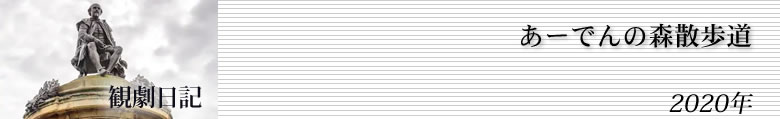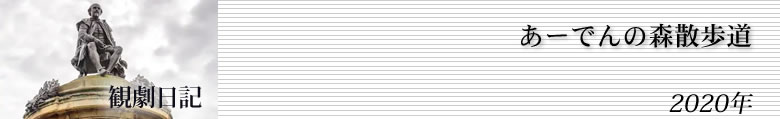|
今回の舞台では美術(装置)と照明のマジックが特に印象深かった。
特に、照明では舞台が照明一つで宮廷の華やかな床から街路の敷石に変じたり、十字架や教会のステンドグラスの模様を描き出すというマジックのような照明の不思議さに感嘆させられた。
開幕の場では、舞台2階のバルコニーの前面に、フランス王とヘンリー八世が和平の握手をしている二人の背後の真ん中の位置に枢機卿ウルジーが立っている姿を描いた大きな垂れ幕が掲げられていて、ウルジーの絶頂期を表象化しており、2幕目ではこの垂れ幕が不安定な状態で吊り下げられた状態で始まり、サリ―伯が投げた礫でこの幕の片方が床面に垂れ落ち、ウルジーの失墜を表示することになる。
これらの美術的な趣向とともに演出面で衝撃的だったのは、1幕の開演時とその終わりの場面と最後のエンディングであった。
1幕の舞台が始まると、キングサイズのベッドにヘンリー八世がベッドに寝ていて、シーツがめくられると3人の女性が共寝をしていた光景が明るみに出され、6人の妻を次々と変えていったヘンリー八世の女性遍歴を表象化するかのようであった。
1幕の終わりは、ウルジーがキャサリン王妃を説得するのに成功した後、その本音を吐露し、着ていた衣裳を脱ぎ捨てベッドに入る。
すると、そのベッドから、彼の忠実な秘書であるクロムウェルが裸の姿で起き上がってくるところでこの1幕が終わる。
エンディングは、エリザベスの洗礼式の華やかな場面が終わった後、エピローグの台詞ではなく、舞台上手の階段の中央にバッキンガム公、下手にウルジー、そして舞台中央の後方からキャサリン王妃が静かに登場してきて、3人がそのままの位置で幕となる。
演出と舞台全体で特に印象深かったところを箇条書きしたが、演出全体を通しての印象は最後のエンディングに表象されているように、吉田鋼太郎が演じる枢機卿ウルジー、バッキンガム公を演じる谷田歩、そしてキャサリンを演じた宮本裕子が軸となっていたように感じた。
特に1幕の前半部までしか登場しないバッキンガム公を演じた谷田歩の台詞力は、ノーフォーク公を演じた河内大和とともに台詞を聴くシェイクスピアとしての楽しみを味あわせてくれた。
タイトルロールで主役のヘンリー八世は、この彩の国シェイクスピア・シリーズで『ジュリアス・シーザー』でブルータスを演じて以来の出演の阿部寛が絶対的な権力者としての王を力強く演じ、黒のロングコートの衣裳が、ウルジーの枢機卿としての赤い色の衣裳と鮮やかな対照をなしていて視覚的な効果を高めていた。
台詞力を楽しむ魅力としては、吉田鋼太郎や谷田歩、河内大和などのほか、シェイクスピア劇を専門に長年演じてきたシェイクスピア・シアター出身の間宮啓行や、アン・ブリンの女官を演じた劇団AUNの沢海陽子などにどうしても耳がいってしまった。
巷の街路でゴシップを交わす紳士役の大石継太も、蜷川カンパニーで長年このシリーズに出演してきているだけに、そのコミカルな一面を楽しませてくれた。
カンタベリー大司教クランマーが裁かれようとする場面で、彼が門の外で待たされ市民らと一緒にされるが、その市民らの猥雑さは、好みの問題でもあるが、蜷川演出と較べると物足りなさを感じた。
蜷川演出での一般市民らを大勢登場させての猥雑さには一種の花があるとともに、スケールが大きく大胆でもあり、その懐かしさがよみがえってきた。
上演時間は、途中15分間の休憩を入れて、3時間20分。
次の予定があったためカーテンコールを見ずに会場を後にした。
訳/松岡和子、演出/吉田鋼太郎、美術/秋山光洋、照明/原田 保
2月17日(月)13時開演、彩の国さいたま芸術劇場の国・大ホール
チケット:(S席)9500円、座席:2階V列34番
|