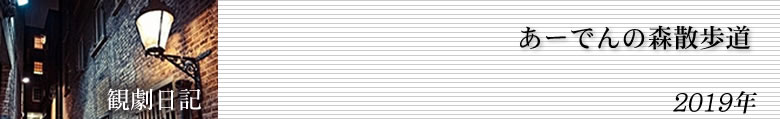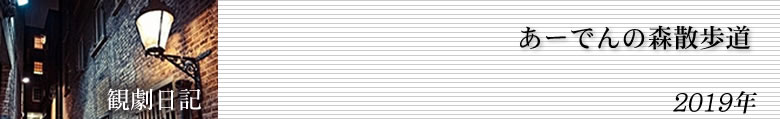|
コンパクトに濃縮された、スピード感のあるスタジオ劇場にふさわしい演出の舞台であった。
開幕はよくある1幕1場と2場を入れ替え、ヴァイオラがイリリアの海岸に漂着した場面から始まる。
ヴァイオラは頭にショールにくるんでひとり舞台中央に立って虚空を見つめる。
船長は舞台に登場せず、声のみがヴァイオラの質問に答える。
この演出は出足として非常に新鮮なものを感じさせ、この舞台のヒロインであるヴァイオラの存在感を強く感じせしめるものであった。
キャステイングもよく、それぞれがその役にふさわし演技と台詞を見せ、聞かせてくれ、楽しませてくれた。
シェイクスピア劇では当時の演劇事情(女優はいなくて女性の役は少年俳優が演じた)から女性の登場が少なく、そのため女優の出番が少ないので女優をいかに多く出演させるかも工夫を要する一つで、男役を女優に演じさせるということも一つの手段だが、登場人物そのものを女性に置き換えるのも結構あり、この演出ではその二つともが取り入れられ、オーシーノー公爵を女優に男役で演じさせ、オリヴィアの召使いのフェービアンの名前をフィービーに変えて女性として登場させた。
キャステイングでの特色を生かすためもあってか、一部台詞を入れ替えて言わせる場面もあり、その一つにヴァイオラがオリヴィアに対して使った言葉がしゃれているということで、原作ではサー・アンドルーが繰り返して言う台詞をサー・トービーに言わせ、しかもその言葉も哲学的な台詞に入れ替えていて、おつな感じがした。
舞台を盛り上げ、楽しませてくれたのは、大酒飲みを感じさせる赤ッ鼻で、頬も赤く染めるメイクしたサー・トービー役の調布大。
意外なキャステイングでは、マルヴォーリオ役を今回が初舞台という今年49歳になった藤田泰介を抜擢していたことで、彼の趣味が「企業研究」という意外な側面も興味深い。原作の内容とは少し異なって、黄色い靴下に真っ赤なブルマ姿で登場する場面などは、初舞台とは思えぬ大胆な演技にも挑戦していたのが驚き。
ヒロインのヴァイオラの鹿目真紀、オリヴィアの君島久子は想定内のキャステイングで、最近ではこの二人はパク・バンイルの舞台によく立っているので、親しみの感じも深く、安心して楽しませてもらった。
女性陣では、他にマライアを演じた熊谷里美も人物のキャラをうまく演じ、高校在学時代から学生演劇に親しんできたまだ20歳の野元結水がフィービーを熱演、女性ながらオーシーノー公爵を演じた大和零河。
サー・アンドルーには長身の市村大輔、アントーニオにいっしー、セバスチャンに畑中謙太郎、オーシーノー公に仕える紳士ヴァレンタインと役人役に21歳の足立晃章。
最後になったが、この芝居の一つの要でもある道化のフェステを務めたのは、15歳から舞台に立っているという大阪出身の中井浩之(54歳)。芝居がはねて一人舞台に残った彼が「おいらが子供であったとき、ヘイ、ホウ」の唄を、ささやくような低い声で歌ったのが非常に印象的であった。
出演者は、以上、総勢12名。他に船長の声として新本一真。
90分足らずの上演時間に前半40分、後半40分と分け、例のマルヴォーリオが偽手紙を読む場面で休憩に入るところから5分間の休憩を入れたのはおそらくマルヴォーリオの衣裳着替えのためでもあったろう。
良質のエンターテインメント劇を味あわせてもらった。
出演者のプロフィールを簡略に紹介したパンフ代りのチラシも非常に役立つだけでなく、出演者に親しみを感じさせてくれ、その情報をこの観劇日記にも一部取り入れさせてもらっている。
翻訳/小田島雄志、台本構成・演出/パク・バンイル
12月19日(木)14時開演、両国、スタジオ・アプローズ

マルヴォーリオが偽手紙を読む場面で、物陰に隠れて見る様子。
左下からフィービー、左上:サー・アンドルー、右側:サー・トービー
(写真:調布大のフェイスブックから)
|