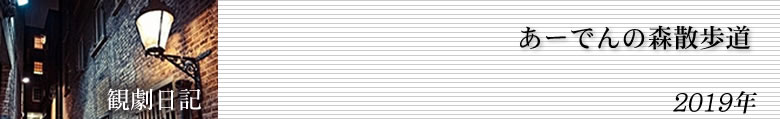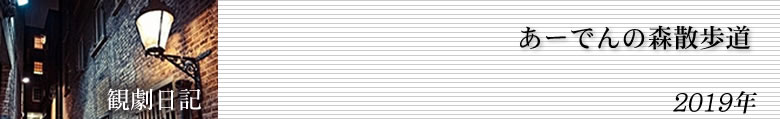|
~エリザベス朝発音によるシェイクスピア劇~
エリザベス朝発音で、9人の俳優(男優7名、女優2名)が14人の登場人物を90分で演じる『ハムレット』劇。
開演前の30分間、俳優たちが舞台上で細長い棒を、薬指、あるいは人差し指に立ててバランスを取る仕草を思い思いにやっていて、それは本番を前にして気分をリラックスさせる、一種のウォーミングアップのように感じられた。(アフタートークの質問で、あるダンスグループが用いていた手法を本番の中にも用いるようになったこのアンサンブル劇団特有の手法だと説明された。)
開演に先立って主催者側の明治大学文学部長の合田正人の挨拶があったが、最後に引用したある哲学者の言葉、「哲学することはシェイクスピアすることである」が印象に残った。
続いてシェイクスピア・アンサンブル主宰者のベン・クリスタルの挨拶と簡単な講演があり、5分間の休憩を入れて本番が開始された。
舞台上には何もなく、細い棒を除いて小道具などもなく、衣裳もTシャツなどのカジュアルでラフなものであり、一人で複数の役を演じる役者はショールを羽織ったり、鉢巻きにして使用することで役の人物を分けた。
開演とともに、役者全員が'Who's there?'とささやくような声を発しながら舞台上をぐるぐると走り廻り、数巡回ったところでクローディアスの謁見の場面となる。
場面展開は台詞の切れ目なくテンポよく進んで行く。
クローディアス、ガートルードをはじめ、多くの登場人物の台詞回しと所作は抑制された感じでクールであるが、一人ハムレットのアクションと台詞だけはパッションがこもっていて、舞台上だけでなく、観客席にまで繰り出し、'To be, or not to be'の独白部分は、なんと、会場の一番奥の隅っこから声がしてきて、前方に座っている自分は思わず後ろを振り返った。
劇中劇は黙劇で演じられ、狂気のオフィーリアはその様態を開演前に練習していた、細長い棒を指にのせてバランスを取りながらの登場で、その心の不安定さを表象していたように感じた。
レアティーズとハムレットの剣の試合は、二人が2本の棒の両端をそれぞれ両手で受けることで表象。
シンプルな舞台で、台詞も全般的にクールであったが、個人的には、期待とともに聴き取りに多少不安のあったエリザベス朝の発音も、それほど違和感なくスムースに聞き取ることが出来たのは意外でもあった。
ただ、ハムレットの第1独白、'O that this too too sullied flesh would melt'や、有名な'To be, or not to be'の台詞などは、これまで聴いてきた発声、台詞回しと随分異なった感じであった(すべてが聴きとれたわけではないが、何度も読んだ箇所でもあり大体のところは記憶しているので聞き取れていなくとも聞き取れたような錯覚で聴いていたが)。
90分という圧縮された舞台であったが、ハイライト部分のほとんどが網羅されていて、それほどカットされたというイメージはなかった。
特にその台詞にクールに感じたのは、男優のアンドルー・コディスポッティが演じたガートルード、女優のエイリアーナ・カープが演じたポローニアスとオズリック、オフィールと墓掘りを演じたアントニィア・ウィアー、それに主宰のベン・クリスタルの演技と発声もクールであった。
一人だけ日本人の俳優(クラタ・ヒロアキ)がいて、彼がハムレットの亡霊、ギルデンスターン、役者、それに墓掘り人を演じたが、墓掘りの場面では日本人の観客を意識したアドリブの台詞と所作で雰囲気を和らげた。
終演後のアフタートークで観客の一人から'To be, or not to be'の解釈をめぐって、明治以来の解釈で、「生きるべきか、死ぬべきか」と「このままでいるべきか、べきでないか」の両義に対して、この公演ではどのような解釈で臨んだかの質問が出された。
それに対して、演じる側よりも受け取る側がどのように感じるかであるという趣旨を、ハムレットを演じたダン・ボーリューが答えたが、自分の持論通りであると思った。
また、別の観客から劇のリアリティについての質問があり、それに対しては、演劇が演じられたその場でしか存在し得ない一過性こそリアリティである主旨で答えられ、これについても大いに賛同するものであった。
エリザベス朝発音でベン・クリスタルが目指す実験的、かつ探究的な劇による演劇の可能性の追求を大いに感じさせる舞台であった。
舞台照明を一切使用しないのも当時の舞台とまったく同じで、台詞と所作だけの劇に新鮮さを感じさせた。
当アンサンブルは、日本の各地を駆け足で公演して回り、演目も『マクベス』、『ロミオとジュリエット』と、この『ハムレット』の3作を、エリザベス朝のレパートリー形式(日替わり演目)で上演しているのも、当時の上演形式の再現の一つとして面白い方式であると感じたとともに、少人数でシンプルな舞台の上演がエリザベス朝の劇団が地方公演して回っているのを彷彿させた。
講演を含めて2時間半の貴重な体験を満喫させてくれた、明治大学の企画に感謝!!
主宰/ベン・クリスタル(劇団 Passion in Practice主宰者)
9月29日(日)17時開演、明治大学駿河台キャンパス・リバティータワー1F
【追 補】
明治大学文学部准教授井上優氏より、観劇日記を読まれて下記の補足を戴きましたので追記します。
・(アフタートークの質問で、あるダンスグループが用いていた手法を本番の中にも用いるようになったこのアンサンブル劇団特有の手法だと説明された。)
→実は通訳の小泉先生、ここの所、訳しきれていなくて(あとで聞いたら、知らなかったそうです)、もともとの説明では「フィジカル・シアターをやっているルコックの技法である」というようなことを言っておられたかと思います。そこをダンスカンパニーと訳されてしまったんです。Jacque lecoqで画像を検索してみると、その手の身体的技法の実践の写真が結構出てきます。
・開演に先立って主催者側の明治大学文学部長の合田正人の挨拶があったが、最後に引用したある哲学者の言葉、「哲学することはシェイクスピアすることである」が印象に残った。
→エマニュエル・レヴィナスの言葉です。
|