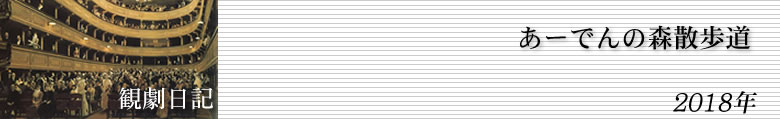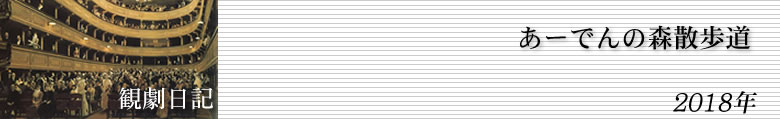― ホームレスの浮浪者たちが乙姫の前で『リア王』を演じる ―
冒頭の場面は、ゴーリキーの『どん底 』、あるいはブレヒトの『三文オペラ』を思い起こさせるドヤ街のような場所に浮浪者がたむろしており、その中心にポリのゴミ箱から残飯をあさって食べている男、そしてその周りには何人ものホームレスが寝転んでいる。
そこへ「浦島太郎」の乙姫が現われ、その浮浪者たちにより『リア王』の劇が展開されていく。
この劇は、タイトルが「浦島太郎」と『リア王』の結び付けに所以するように、ホームレスの浮浪者たち全員が竜宮城の中で演じ、逆浦島の物語としての、乙姫がホームレスたちによってもてなされる芝居とも解される。
芝居は90分と短く凝縮されているが、主だった登場人物の中では、ケントの役だけが登場しないものの、内容的にはシェイクスピアの原作に忠実に従って展開していく。
コーデリアが死ぬ最後の場面では、リアの求めに応じて胸のボタンを開けるのは、死んだとされている道化で、この道化役はコーデリアの役も兼ねているのがこの劇の構造として象徴的でもある。
リアは、乙姫から玉手箱を受け取るが、蓋を開けても煙は出ない。しかし、乙姫が箱を振ると中から紙ふぶきが飛び出し、リアはその紙ふぶきをあびて倒れ、死ぬ。
オールバニ公が「さしあたっての務めは国をあげて喪に服することだ。この悲しい時代の重荷にたえていくほかあるまい、云々」の台詞の途中から、賑やかな「東京音頭」の曲がかかってきて、台詞の声がかき消され、舞台には天井から吊るされた祭りの電灯の明かりが点滅し、やがて暗転する。
この終わり方で感じたことは、「芝居は祭り」だという自分の思いと一致したことだった。
劇団山の手事情社の舞台の特徴は、台詞と所作の様式化にあり、それがひとつの見どころでもあり、魅力でもあるのだが、今回はどういうわけか、観劇中、しっかり見ようとすればするほど、何度も睡魔に襲われてしまった。
舞台装置としては、中央の奥に、リアと道化が嵐に雨宿りする空間として使用されることになるビニール製の白い雨傘をいくつも組み合わせた大きなカボチャ型のオブジェと、その左手に橙色のビニール雨傘一つと祭りの飾りつけのようなものが木柵の枠に散然として散りばめられてあり、また、登場人物の出入りに合わせて、リアやグロスターのお抱え役をする登場人物が上げ下げする、畳4枚ほどの大きさのある筵に、一種の幕のような役割をもたせているのが特徴となっている。
出演は、リアに浦弘毅、ゴネリルに倉品淳子、リーガンに大久保美智子、コーデリアと道化に中川佐織、オールバニ公に斉木和洋、コーンウォール公に栗田直輝、グロスター伯に山本芳郎、エドガーに谷洋介、エドマンドに川村岳、乙姫に越谷真美、他、総勢20余名。
上演時間は、休憩なしの90分。
原作/ウィリアム・シェイクスピア『リア王』より、構成・演出/安田雅弘
10月19日(金)144時開演、東京芸術劇場・シアターウェスト、
チケット:4500円、座席:H列18番
|