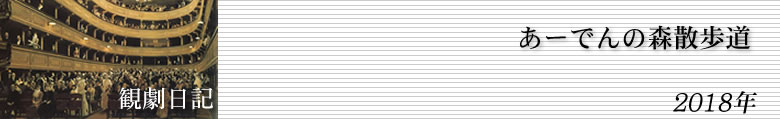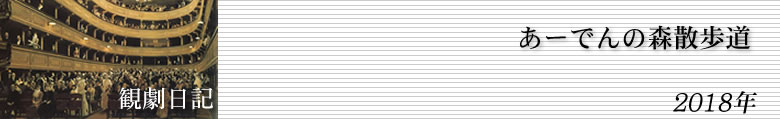舞台奥にはバックドロップの代わりに、モンドリアンのコンポジションを模した大きな衝立が一面の背景となっており、その前方に同じくコンポジションの色取りをした立方体のボックスが組み合わされて置かれ、今回の舞台を1960年代に時代設定したというモダンな雰囲気を漂わせている。
開幕の興味は、オーシーノ公爵の邸の場面から始めるのか、ヴァイオラがイリリアの海岸に漂着した場面から始めるのかにあるが、この演出では開幕と同時にヴァイオラとセバスチャンが舞台の両脇に無言のまま立った姿がシルエットのように垣間見せられ、すぐ続いてオーシーノ公爵の邸の場面に移った。
1960年代と言えばビートルズの時代で、音楽も60年代のそれに類した曲が多用され、オーシーノ公爵が聴いている音楽もいきなりそんな曲から始まる。
この場面ではオーシーノ公爵一人の登場で、廷臣たちの登場はなく、彼の一人舞台となっていて、憂鬱に沈む姿というよりは朗々とした台詞回しで、音楽を続けてくれと言いながらも直ぐにもう飽きたからやめろというあたりの台詞は、気まぐれで、気分屋で、すぐに気が変わるオーシーノの性格を打ち出していたところに特徴があった。
『十二夜』ではオリヴィアの執事マルヴォーリオが主人公だと思わせる演出が多いが、この舞台ではこのオーシーノと、後から出て来るオリヴィアが圧倒的に存在感を感じさせる台詞と演技となっていた。
舞台装置の面では、オリヴィアの邸の場面では、オリヴィアの姿を描いて切り取った発砲スチロールの板を2,3体並べ、衣装を飾るマネキンの胴体部が置かれてオーシーノの邸の場面との区別がされていた。
演出面で特に注目されたのが、シザーリオに男装したヴァイオラとセバスチャンの衣装が通常の演出では全く同じ衣装とされるのに、この演出では二人が異なる衣装であったことで、そのことがごく自然に感じられただけでなく、それでも二人が双子の兄妹である感じが出ていたことだった。
男装のヴァイオラに恋したオリヴィアはミニスカートでセクシーなスタイルで押し迫り、ヴァイオラとセバスチャンを取り間違えた場面では、セバスチャンが上半身裸で、ズボンを足首までずらしたパンツ一枚の姿で出て来て、二人の関係を暗示させることに見られるように、アグレッシブなオリヴィアとして表出されていた。
このオリヴィアとオーシーノの二人の間に挟まれたヴァイオラもセバスチャンも目立たないほどであった。
注目のマルヴォーリオ役は、黄色のストッキングに十文字のガーターを脚だけでなく、体全体を十文字のガーターで締めた姿に、前半での堅い執事を感じさせていた演技の反動のギャップが大いに笑いを誘った。
道化のフェステは、小柄な女性のスザンナ・タウンゼントが演じたが、全体的に声が細く聞き取りにくい箇所もあっただけでなく、台詞のカットのせいもあってフェステの面白みに欠けていて自分には少し不満足であった。
台詞のカットの面では、随所に自分が聞き逃したかと思われるような、カットして欲しくないような台詞のカットもかなりあった。
終幕の場面も気になるところであるが、ヴァイオラとセバスチャンの再会の大円団の後、フェステが、ストップモーション的に静止した登場人物たちを指でつつくと、その人物たちが二人一組ごとに退場していき、最後に一人残ったアントーニオも退場して、しめやかなフェステの唄で締めくくられた後、再び全員再登場し、音楽に乗ってのツイストダンスで華やかなフィナーレとなる。
全体的に、軽快で、笑いの詰まった、テンポの良い、楽しい演出の舞台であった。
上演時間は、途中15分間の休憩をはさんで、2時間30分。
演出/フレッド・ウィーナンド、出演/オックスフォード大学演劇協会(OUDS)
8月8日(水)13時30分開演、東京芸術劇場シアターウエスト
チケット:2300円(団体割引)、座席:F列19番
|