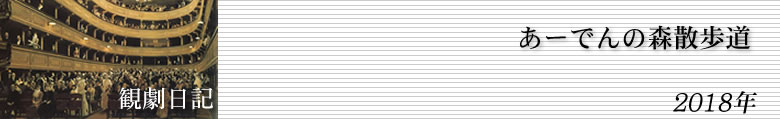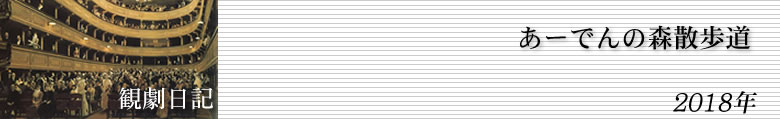~ 「歯もなく目もなく何もなし」 ~
タイトルからたぶん誰もが想像するのはベケットの『ゴドーを待ちながら』で、自分もそうであったが、この劇を観終わって感じた印象は、シェイクスピア劇俳優としての田代隆秀へのオマージュであった。
「ウィル」は第一義的にはシェイクスピアのことであるが、劇中では(田代隆秀の)遺書としてのウィル(will)をも意味し、「待ちながら」の「待つ」とは出番を待つ、出演の声がかかるのを待つ、という意味が込められていた。
この劇の構造は大きくは三層構造で、始まりと終わりの部分では田代がシェイクスピアの劇団の看板俳優だったリチャード・バーベッジ、髙山春夫がシェイクスピアを演じ、真ん中のあんこの部分では、二人がシェイクスピア劇の台詞を散りばめた寸劇をモザイク模様に散りばめ、このあんこの部分も『リア王』のエドガーとグロスターのドーヴァーへの道行き場面を3回繰り返す三層構造になっている。
プロローグとしてのシェイクスピアとバーベッジの場面では、シェイクスピアが次作の原稿が一向にはかどらず苦しんで、原稿にはただ、「歯もなく、目もなく、何もなし」だけで、それを見たバーベッジは「なんだ、タイトルだけじゃないか」と言っている間に舞台開演のベルが鳴り、暗転の後、二人芝居が始まる。
エドガー役の髙山が、フェステの道化の唄を歌っているグロスター役の田代が乗っている車椅子を押して登場し、グロスターがドーヴァーの崖から飛び降りて倒れ伏す場面までが演じられ、その後シェイクスピアの名台詞を散りばめたコント風な寸劇がいくつも演じられる。
二人はカセットコンロにかけた小鍋に実際に火をつけ、野村玲子(元劇団四季)の声を吹き込んだ『ロミオとジュリエット』の一場面をカセットで聞きながらなべ料理をつつき、シェイクスピア・シアター時代から劇団四季までを通して演じてきた田代の40数年にわたるシェイクスピア俳優としての半生を語り合う。
髙山は「勝負にならないよ」と言いながらも田代とシェイクスピアの台詞を言って作品名を当てるゲームをしたり、落語を演じたりする。髙山の言う通り、田代の知らない台詞は一つとしてないが、最後に髙山が台本の中から出した台詞だけが答えられなかった。
髙山は落語では、自分が行き倒れで死んだという粗忽者の熊こうの噺を演じ、田代は『ヴェニスの商人』の人肉裁判の場面を落語に仕立て、キリスト教徒に改宗させられたシャイロックが何と言ったかという最後のオチに、シャイロックの名前をもじって、シャイ=恥かしい、ロック=岩(いわ)から―「はずかしい・いわ」、「はずかしい・わ」と繰り返す。
シェイクスピアの台詞は、新たに加えられた『エドワード三世』、『二人の貴公子』、それに『トマス・モア』までの40作すべてを網羅して語られる。
これらの小話をはさんで、グロスターとエドガーのドーヴァーへの道行き場面が再度繰り返される。
その中で、二人が「ウィルを待っている」ことが口にされるのだが、劇中、田代が死ぬことになり、髙山は「ウィル」が遺書だったのかと覚る。
死んだ後にも、人はその人の心の中に生きている、だから忘れずに思い出して一緒に演じてくれというのが田代の遺書であった。
68歳になるという田代の切実な思いが感じられる台詞でもあった。
この劇は、2016年に同じ「こまばアゴラ劇場」で髙山が河合祥一郎訳での『ゴドーを待ちながら』のエストラゴンを演じた時、田代が『ゴドーを待ちながら』の状況で二人の役者がシェイクスピアの台詞を語っていく芝居が出来たら面白いのではないかという話から、河合が作り上げたものだという。
シェイクスピア劇を楽しむ者にとっては、劇中の台詞がどの作品に出てくるのかを想像し当てる楽しみもあるだけでなく、シェイクスピア劇をどっぷり演じてきた田代隆秀の台詞を聞く楽しみを十二分に満喫させてくれる舞台でもあった。何よりも、髙山との二人のコンビが抜群であった。
上演時間は、休憩なしで1時間45分。
作・演出/河合祥一郎
7月5日(木)14時開演、こまばアゴラ劇場、チケット:3500円、全席自由
|