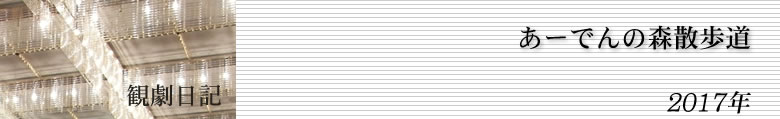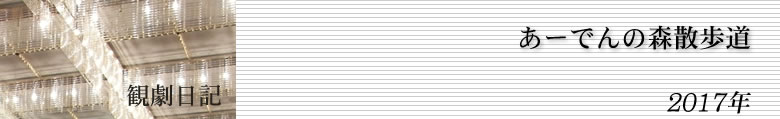昨年4月にSPH(シェイクスピア・プレイハウス)の活動を始めて、年3回の公演を今年も定期的に続け、年末最後の締めくくりは主宰者が「最も好きな」だけでなく、一番「上演したかった」作品『十二夜』で祝祭をフィーバー。喫茶客席の土間を舞台にして、通常は舞台用なっている高い場所を客席に変え、天井に張られたネット上には色とりどりの風船、客席から向かっての左手側面にはアニメ風の三日月の絵、前方カウンターの前にはミラーボールが吊るされ、正面にはDISCOの大きな文字が描かれ、小さな舞台空間ティーハウスは、さながらディスコハウス。
SPHのシェイクスピア劇の楽しみの一つに、毎回の演出コンセプトの変化があり、今回の『十二夜』は、昨夏の『夏の夜の夢』の公演に続く、出演者全員が猫の仮面をつけての猫芝居「にゃいとシリーズ」の第二弾。
観劇した当日は、今回10回あるステージの2日目で、土曜日のマチネと比較的客を呼べそうな日であったが、わずか6人と少し寂しい状態であったのが残念であった。
出演者はオーディションで選ばれた舞台経験の浅い若い人たちと、長年の舞台経験があるベテランとの混合。
開幕は、ディスコダンスで始まるが、この日のステージの出足は客足のせいか、今一つ盛り上がりに欠けていたが、後半部では次第に乗って来て盛り上がりを見せ、最後には観客も中に引きずり込まれて一丸となって踊らされ、フィーバーを締めくくった。
『十二夜』の出だしの演出には、大まかに二つのタイプがあるが、一つは原作通りオーシーノ公爵の邸の場面から始める演出と、1幕2場のヴァイオラがイリリアの海岸に漂着した場面から始める演出で、この場合多くはこの後にオーシーノ公爵の邸の1場の場面に戻ることが多いのだが、今回の演出では後者のタイプの演出ではあったが、1場のシーンはカットされたままで進行した。
出演者が7名ということで、全員が二役をこなし、キャスティングそのものの妙味も楽しむことができる。
双子のヴァイオラとセバスチャンにはアメリカでの舞台経験が豊富な東野遥、オーシーノ公爵とサー・トービーには篁朋生(演出家でもあり、振付もしている主宰者の俳優としての芸名)、マルヴォーリオとアントーニオは遠藤孝、サー・アンドルーと船長に吉田智、フェステとフェービアンに声楽科出身でバリトンの菊池春菊、オリヴィアとマライア、それに役人の役を、まだ現役の学生である照井瑞帆、そしてダンスと役人の役をダンサーの佐々木健。
双子のヴァイオラとセバスチャンの再会の場面では、ヴァイオラを演じる東野遥が、2匹の白い猫のぬいぐるみを使って声色を変えて演じるという趣向であった。
演技面では、マルヴォーリオを演じた遠藤孝は若手という年齢とは言えないが、格別のうまさがあるというわけではないものの、発声法や演劇を本格的に学んできているだけに、妙なる味わい深いものを感じさせた。
このSPHでは常連ともいえるダンサーの佐々木健は、これまでダンサーとしてのダンスしか見てこなかったが、今回は役人役も演じて、その台詞が非常にしっかりしていたことで意外な局面を見させてもらった。
劇中、唄う場面のあるフェステのキャスティングは、声楽科出身の菊池春菊であることはすぐ想像されるが、劇中ではその美声を何度か披露して楽しませてくれた。
主宰者が元劇団四季でのダンサーでもあったこともあって、SPHの演出の特徴はダンスを交えての音楽劇的要素をもたせたところにあるが、今回、作曲・演奏・音響・照明と一人何役を務める五十部裕明の場面とのミスマッチさせた選曲(アニメの「さざえさん」主題歌や、ベートーヴェンの「運命」など)が、面白く、楽しく、思わず笑ってしまう場面もあった。
上演時間は、途中10分の休憩を挟んで2時間40分。
訳/小田島雄志、演出/ホースボーン由美、12月2日(土)14時開演
玉川学園前・シェイクスピア・ティーハウス、チケット:3500円(アフタヌーンティーセット付き)
|