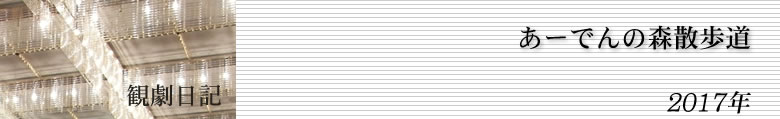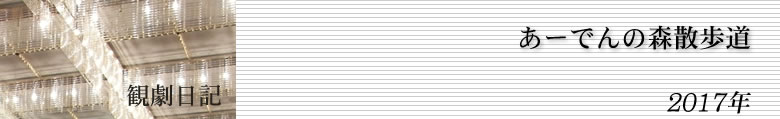スターティングは、やはりマチネ限定の、英国紅茶に手作りのサンドイッチ、スコーン、そして当日の演目に合わせた茶菓との三段重ねのセットのアフターヌーン・ティー・セットから始めるべきだろう。
一段目が、それぞれサーモン、ハム、胡瓜を挟んだミックスサンド、二段目がスコーン、三段目は今回イタリアを背景にした『テンペスト』ということで、手作りのティラミス、それにバラの香りを含んだゼリー状の砂糖菓子と小さな葡萄一房がデザートとなっていた。
サンドイッチのしゃっきりした食感、スコーンはお好みでジャムとクリームをつけ、最後にティラミスをスプーンでゆっくりかき混ぜその風味を味わいながら食し、最後に、舌先にとろけるようなピンクのゼリー、この茶菓セットと紅茶をゆっくり味わう開場30分前までの1時間は、朗読劇を楽しむ前の至福の時間でもあった。
提供される茶菓セットの皿や紅茶カップもお客の一人一人で異なり、店主の嗜好のセンスを味わうのも楽しみの一つである。
このアフターヌーン・ティー・セットの内容が毎回異なるように、SPH(シェイクスピア・プレイ・ハウス)の朗読劇の趣向も毎回異なっていて、今回は、シェイクスピア時代の音楽の雰囲気を持たせた古楽の演奏付きの朗読劇。
当初、案内のチラシを貰った時と、当日のプログラムに記載された出演者の違いが若干あった。
今回のステージは、7月21日(金)、22日(土)、23日(日)の3日間で、当初、22日の朗読者は篁朋生一人で、演奏者はバロックハープの久保田潤子とバロックバイオリンの平松晶子となっていたが、当日もらったプログラムでは22日の朗読者が篁と増留俊樹の二人になっていた。それに、最初のチラシではダンサーの名前はなかったが、21日と23日が岡田直樹、22日が池亀友紀也となっていた。
自分が観た23日は、古楽演奏者がバロックハープの久保田潤子とバロックギターの金井隆之、朗読者が東野遥と篁朋生、そしてダンサーが岡田直樹というメンバーであった。
今回の舞台では注目すべき点が多くあったが、特に注意を引いたのは舞台美術としてホリゾントに描かれたヨーロッパの地図が、今展覧会でも注目となっているアルチンボルドの人物画のような趣向で、各国を怪獣や魔女、人物像をはめ込んで作り上げており、たとえば、イングランドは魔女、ノルウェーとスエーデンは怪獣、ロシアは熊のような顔をした人物といった具合に具象化されており、舞台美術担当の石井美和がすべて手作りで描いたという。朗読者については、自分のうかつさにこれまでまったく気づかないでいた。
この日の朗読者は東野遥と篁朋生となっていて、登場してきたのは東野遥と、シェイクスピア・ティー・ハウスの店主でもある演出者のホースボーン・由美こと竹川由美であった。
篁朋生は竹川由美の竹にちなんだ芸名で、前回の一人芝居『アテネのタイモン』でも朗読者は篁朋生となっていたのに今回まで気づかずにいた。
つまり、彼女は演出者としてはホースボーン・由美として、俳優としては篁朋生を芸名にしているのだった。
朗読劇では、東野遥がプロスペローを演じ、篁朋生がその他の登場人物すべてを一人で演じ、最初はミランダ、そしてエアリエル、キャリバン、ファーディナンド、トリンキュロー、ステファノーと目まぐるしく演じ、後半部になってアロンゾーやゴンザーローなどの役を加えて所作、声色、立ち位置を変え、まさに八面六臂の大奮闘で、その変化を楽しませてもらった。
演出として注目すべき点は、プロスペロー役の東野遥が、最初はシェイクスピアとして舞台下手の机に座って鵞ペンを走らせては原稿を投げ捨てるというところから始まり、最後はプロスペローから再びシェイクスピアに戻って、この『テンペスト』を書き終え、観客の前に出て来てプロスペローのエピローグの台詞を語るという趣向であった。
久保田潤子と金井隆之は、古楽演奏だけでなくソプラノとテノールで素晴らしい歌声を堪能させてくれ、ダンサーの岡田直樹は、台詞のシャドーウィングをしているかのように劇中ずっと出ずっぱりの活躍であった。
他の注目点として、衣装の榎本百合江、そして音響・照明・舞台監督の小柳津暁生など制作スタッフの陰の力も強く感じさせる舞台であった。
この日は、アフターヌーン・ティー・セットも朗読劇の方も満席で、上演中は出演者の熱演と相まってエアコンも効かず、心も熱く、体も熱く、熱中して楽しませてもらった。
上演時間は、途中休憩10分を挟んで2時間20分。
訳/小田島雄志、演出/ホースボーン由美
7月23日(日)14時開演、玉川学園前・Shakespeare Tea House
観劇チケット:(アフターヌーン・ティー・セット付き)3500円
|