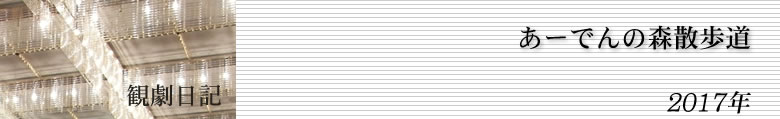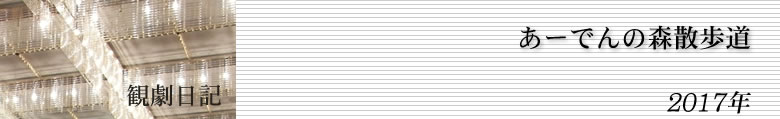森島朋美、田中智子制作による桜会の"シェイクスピア401年忌"として、三宅充の「座長マジック」に続いて、北村青子、倉橋秀美、白井真木による「リアの道化と3人の娘」、そして最後に阿部良の一人芝居「ハムレット論」。
昼間の豪雨も夕方にはあがって、6時過ぎには早くも当日の予約客が数名、受付でチケットを受け取っていた。
かくいう自分も6時過ぎには制作を当している受付の森島さんからチケットを受け取った。
森島さんはこの日初めてお会いし、それまでまったく存じ上げていない方であったが、チケットを受け取る際に自分の名前を告げると、「あーでんの森散歩道」を読んでいるということで自己紹介を受け、今回の制作者であることも知った次第だった。
最初の「座長マジック」の三宅充は、本来は俳優で、マジックはボランティアでやっているということであるが、見事なマジックほど拍手がないと本人が言われる通り、あまりの見事さに拍手を忘れる場面が結構多くあった。
一人だけ最前列に座っていた関係もあって、一部相手役もさせられ、マジックの種など楽しませてもらった。
● 朗読劇『リアの道化と3人の娘』
続く『リアの道化と3人の娘』は、自分が台本を構成したという関係からだけでなく、出演者の北村青子、倉橋秀美、白井真木の3人の劇読に大いに期待してのことであったが、チラシには載っていなかった尼理愛子が弾く薩摩琵琶の演奏で、ここでは登場しないリアの存在を見事に浮かび上がらせ、リアの3人の娘の実在感を一層感じさせた。
実はこの3人によるリアの娘の役は、4月の荒井良雄記念「日英シェイクスピアシェイクスピア祭2017」での新地球座公演による坪内逍遥訳『リア王―影法師リヤ―』とまったく同じ役で、しかも尼理愛子の薩摩琵琶演奏もついていたので、今回、松岡和子訳との違いでどのように変わるかという興味と関心も大いにあった。
台本は半年以上前に作っていた関係もあって自分で作っておきながら忘れていた部分も多いのだが、出演者たちによって多少変えられている部分もあって自分の台本である気がせず、まったく新たに聞く感じがした。
北村青子のゴネリルと倉橋秀美のリーガンのバトルは、両者の憎々しさの白熱の熱戦が見事としか言いようがない程素晴らしく、その憎々しい表情に見入ってしまった。
この二人の憎々しさが増す程に、白井真木の演じるコーデリアが逆比例して清純華憐に見え、またそれをうまく演じ切っていたのも見ごたえあるものであった。
コーデリアの出番が二人の姉に比べて少ないこともあって、台本作りに当たって、リアの道化を登場させ、それを白井真木に演じさせるようにしたのは、シェイクスピア当時にも、コーデリアを演じた少年俳優が道化も合わせて演じたことがあるという言い伝えがあることからでもあった。
この道化とコーデリアの二役を白井真木がうまく演じ分けたのも見どころの一つでもあった。
リアの3人の娘だけの登場では最後が尻切れトンボになってしまうので、シェイクスピアの元本に一つでもある『リア王年代記』やテイト版『リア王』のハッピーエンドの一部を採用してコーデリアを生かし、最後のエドガーの台詞(クオート版ではオルバニーの台詞)をコーデリアに言わせるように台本を作っていたのだが、この部分については3人がコーラスとして台詞を語るという手法を取って、見事なエンディングとなしていて感動した。
この最後の場面であるが、リーガン、ゴネリルが死んで引き下がった後、コーデリアの白井真木が舞台奥の中央でしばらくの間、沈黙の状態を保っていて、観ている方も行き詰ってくるような感じであったが、それだけにコーデリアがケントによって助けられたことを物語って、リアの死を嘆く場面が感動的となっていた。
そして、最後に3人が並んで、「この悲しい時代の重荷は、我々が背負って行かなければならない」以下の台詞をコーラスとして語り、すべてを語り終えると静かに背を向けて、退場していくのが何ともすがすがしかった。
ここまで見事に全体を自然な形に仕上げてもらうと、台本構成者として作者冥利に尽きると言わざるを得ない。
● 阿部良の一人芝居『ハムレット論』
チラシにはただ『ハムレット論』とあるだけで、出演も阿部良の名前があるだけであり、舞台が始まるまでどんなものか全く想像もつかなかったが、劇が始まってもまったく雲をつかむような感じであった。
舞台奥中央に折り畳み式のパイプ椅子があるだけで、舞台下手側から袖なしの粗布からなる粗末な衣装に草履を履いた一人のやせこけた老人が登場し、椅子に腰かけ、「清水港の次郎長」の唄をつぶやくようにぼそぼそと唄う。その後も脈絡を欠いたような話をぼそぼそとつぶやくだけで、『ハムレット』との接点が一向に見えてこない。
老人は、若いころ、同志社大学の学生で、女性との関係もかなりあったかのように女性の名前を色々とつぶやくが、卒業を前にして最後のデートで待ち合わせた女性がいくら待っても現れない。
と、待ち合わせの場所から少し離れた場所で何やら騒々しい光景が繰り広げられ、近づいて見ると倒れた女性の足が見え、その傍らにナイフが落ちており、人影が走り去るのが見える。そのナイフを拾ったために、自分が犯人と間違えられるが、近くにいた旅館の女将の証言で何とか釈放される。
卒業して東京に戻った彼は決まっていた就職先にも就職せず、インドに旅立つ。インドでは、途中小便がしたくなってバスから降りたらそのままバスが彼を残して走り去って、まったくの荒野に一人残され寝袋で一夜を過ごすことになる。この場面では「ここはお国を何百里」という軍歌が自らを鼓舞するように歌われた。
日本に戻ってからも定職につかないまま、あの事件から30年が過ぎ、或る日、六本木であの日目撃したナイフの持ち主、彼の友人でもあったが、その彼にばったり出会い、そのナイフのことを話すと反応を示す。彼はその友人を追い詰め、首を絞めるが途中で手を緩めてしまう。
その間、彼の思い出話として、学生時代の時、北欧から来た留学生の話として初めて『ハムレット』の話が出て来るが、そこで語られるハムレットは優柔不断の青年で、ここで初めて『ハムレット』との接点らしきものが見えてくる。それから数日後、二人の共通の友人から、ナイフの持ち主であった彼が30年ぶりにやって来ているということで一緒に会食しようと連絡が来る。
彼はその彼が宿泊しているホテルと部屋番号を聞いて、タクシーで一人そのホテルまで行き、教えてくれた友人の名前で彼の部屋までエレベーターで昇っていく。
部屋をノックし、彼が出てきたところで、彼が拾ったナイフで元の持ち主であるその彼を刺す。そして言った彼の言葉が、「生きる、死ぬ、それは問題ではない」であった。
舞台はここで終わりだが、当初、まったく『ハムレット』との接点がみ出せなかったものが、全体を振り返ってみると何となく『ハムレット』論に見えてきたから不思議である。
上演時間は、全体で1時間50分。
6月21日(水)19時開演、新宿3丁目・SPACE梟門
|