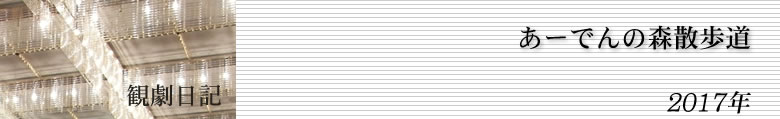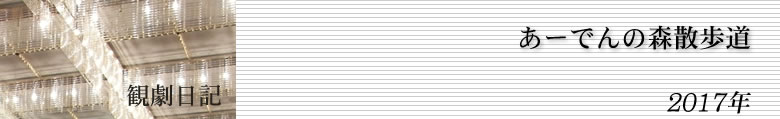10年ぶりの再演というチラシの言葉に、この劇の記憶がまったくなかったので観劇日記を振り返ってみた。するとこの話の内容をこと細かに記録しており、読み返すことで記憶がよみがえってきた。しかし、実際の舞台を観ると、まったくはじめて観る劇のようであった。
それは10年前とキャスティングがまったく異なっていたこともその理由の一つだったと思う。
前回出演し、今回も出演している役者もいるが役柄が一変している。
たとえば、前回ナバール王を演じた星和利は今回フランス側のボイエットの役で、キャサリンを演じた川久保州子は今回フランス王女の役を務めており、その他はまったく新メンバーである。
記録していないだけなのか、今回の演出が異なるのか今となっては不明だが、今回初めて観る劇のように感じた理由の第二として、初めと終わりの場面にあった。
冒頭の場面ではプロローグとして、ナバール王国の伝説の時代の王が長い戦いに勝利をおさめ、ローマのポンペイウスによってナバール国を賜り、抑圧を受けていた国の乙女を王妃として迎え、抑圧の悲しみから喜びへと変わる表象として「笑う月」のペンダントを彼女に贈るという短い場面があった。
このプロローグの場面の王と王妃の役を真延心得と笹本志穂が演じ、劇中では、真延は道化役としてアキテーヌの警察署長コスタードを演じ、笹本は聡明な小僧モスを演じ、この劇の最後の場面で二人はエピローグとしてこの劇を閉じる役をして同じ役者が異なる役柄で締めくくり、一種の円環構造を感じさせた。
劇中に出て来るゴッドハンド(神の手)は、この劇の初演時の10年前、遺跡物の捏造事件があって時代を映すトピックスでもあったが、今回は、加計学園の獣医学部新設問題での怪文書発言問題など似たような事件が発生しており、違った形でのトピックスとなっていたのも面白い皮肉として感じた。
話の面白さに加えて、キャスティングの妙味を十二分に楽しむことができた。
『から騒ぎ』のベネディックとベアトリスを思わせるビローンとロザラインにはかなやたけゆきと森由香、デュメーンとキャサリンは茂木泰徳と藤井由樹、ナバール王とフランス王女は大久保洋太郎と川久保州子で、いつもは軽妙なコミカルな役を演じて楽しませ得てくれる川久保州子が、しっとりと落ち着いたフランス王女を演じているその対照的演技を楽しませてくれた。
前回この役があったのかどうか記憶にないが、ナバールの乳母役ルーセッタを江戸馨がコミカルに演じたのも見ものであった。
劇の内容については前回の観劇日記で詳細に記しているのでここでは割愛する。
「鏡の向こうのシェイクスピア・シリーズ」は、メタ・シアター風に言えば、メタ( meta- =「後続」「後位」;「変性」;「超越」)の持つ意から、メタ・シェイクスピアと称してもいい。
上演時間は、休憩なしで2時間。
脚本/奥泉光、演出/江戸馨、作曲・演奏/佐藤圭一
6月11日(日)14時開演、下北沢・「劇」小劇場にて、全席自由
|