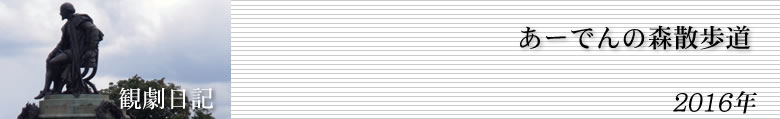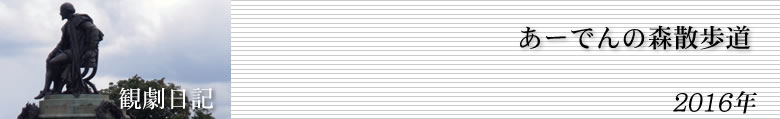|
成蹊学園が英国ケンブリッジ大学ペンブルック劇団を迎えての公演は、今回10周年を迎えるという。その記念すべき年に『ロミオとジュリエット』が上演された。
「演出家ノート」に、演劇における性別の平等性に基づいて、女性5名、男性5名の出演と、モンタギュー家、キャピュレット家の一族をまとめる家長をそれぞれ、モンタギュー夫人、キャピュレット夫人に融合し、大公の役割をパリスが担い、ジュリエットの恋敵でもある彼がロミオに追放を言い渡すことになるということが書かれていることに興味がわき、かなり期待して観た。
衣装は、若者たちが身につける現代服で、舞踏会のシーンもポップ音楽を用いた現代のパーティー形式となっていて、観客サービスも兼ねてか、このシーンは全体の中でもかなりの比重をかけていたように思われた。
開演とともに出演者全員が舞台に登場し、冒頭のプロローグの台詞が語られるとき、序詞役が一歩前に進み出て、その他の出演者は後ろ向きとなる。その序詞役を務めるのは、モンタギュー夫人を演じる黒人女優のローラ・オルフェミ。エピローグも、大公役を務めるパリスがロミオと闘って死んでいることから、彼女がその台詞を語ることでこの物語りの輪が結ばれることになる。
女性と男性の出演者の数を平等にしている関係から、ベンヴォーリオは女優のカトゥラ・モリシュが演じる。彼女はロミオの召使バルサザー役も演じるが、衣装を変えないのでバルサザーかベンヴォーリオなのか判然としないが、この演出ではジュリエットの死を知らせるのはベンヴォーリオとして見る方が自然な気がした。
上演時間が1時間20分程度ということもあって速いテンポで進み、そのため台詞や場面の省略が多かった。このテンポの速さは、最初のうちはスピード感があってプラスに感じて見ていたのだが、全体を通して見終わった感想は、台詞に余情感が乏しく、ダイジェスト版のような感じがした。特に最後のロミオとジュリエットの死の場面は付け足し的な演技で、感動的な場面としての見せ場もなく、何か拍子抜けした終わり方であった。
省略された場面はこの劇の展開をよく知っているだけに、その間のつなぎの台詞や場面を自分の頭のなかで補いながら見ている自分がいた。
台詞の中では、乳母がジュリエットの年齢を言うとき、16歳という言葉を繰り返していたのが耳についた。16歳と言えば高校生の年齢で、今風の感覚では13歳の少女よりリアルさが感じられるので、この年齢の変更は現代の若者という設定で意識的に変えたのであろうか。
現代の場面に置き換えているということもあって、修道士ロレンスがロミオと連絡を取ろうとするときスマホを使うが、この小道具の使い方は中途半端で一貫性に欠けていた。
修道士ロレンスを演じたウィリアム・アシュフォードは音楽専攻でカレッジの聖歌隊のメンバーでもあるということで、ロミオとジュリエットを結び合わせる場面では、その自慢の歌唱力披露で観客の耳を楽しませてくれた。
演技の「らしさ」としては、乳母役とこの修道士の役に物足りなさがあったが、マキューシオを演じたジャステイン・ブランチャードとベンヴォーリオのカトゥラの演技には好感を覚えた。
出足の部分で期待しながら観ていただけに、その反動で自分としては個々の点で辛い評価になってしまったが、演出の着眼点もいいと思うし、舞台全体としても楽しんで観させてもらったので、プラス評価。
演出/ジョージ・カン、9月25日(日)13時30分開演、成蹊大学4号館ホール
|