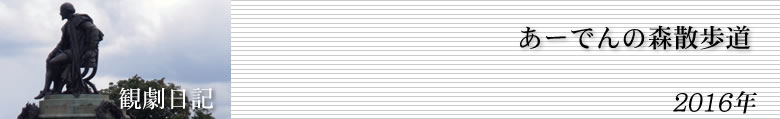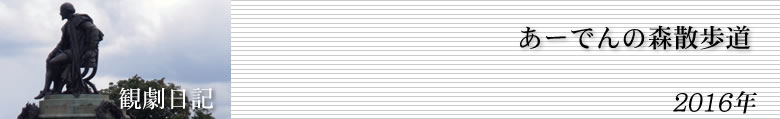|
大胆で刺激的な演出とダイナミックな演技で、これまで観てきたOUDS(オックスフォード大学演劇協会)来日公演の中でも最高の舞台の一つだったと思う。何よりも、楽しく、面白かったのがよい。
舞台が始まる前にエレキギターを伴奏に数曲のヴォーカルが披露され、これまでとは何となく違ったものになりそうな予兆を感じたが、その予感が的中した。
ヴォーカルが続く中、上手から5,6人登場してくるが、舞台上は依然として暗く、彼らの姿はシルエットとしての動きで、その所作は『ウェストサイド物語』の冒頭シーンを思い出させた。
彼らの動きがストップモーションとなったところで、突然、観客席側から二人の人物が叫喚しながら舞台上に駆け上ってきて舞台は明るくなり、動きの止まった彼らの顔を滑稽な表情に変えたリ、操り人形のように手足の位置を動かして遊ぶといういたずらをする。このように意表をついたところで一転させて、この劇の冒頭部であるシーシュースとヒポリタが登場する場面となる。
次に、この舞台の演出の特徴の一つにキャスティングの問題がある。
まず一番がダブルロールで、シーシュースと妖精の王オーベロンを一人二役とした場合、ヒポリタと妖精の女王タイテーニアもダブルロールにするのが普通であるが、この舞台ではヒポリタとタイテーニアは別の女優が演じた。
これには何となくキャスティング上の何らかの事情があったのではないかと勘繰りたくなる面があった。というのは、アマゾネスとしてのヒポリタ役はタイテーニアを演じたエマ・ヒューイットが二役演じたほうが適役に見えたからである。
登場人物の数の面で、台詞上からは少なくとも4人はいる妖精が、ダブルロールとしてフィロストレートを演じる蜘蛛、ヒポリタを演じる蛾の羽根の二人の妖精だけであり、アテネの職人たちも6人のところが5人で、指物師のスナッグが欠けていたが、彼が演じるライオンの役は月を演じるはずの仕立屋スターヴリングが演じ、月の役は劇中劇では省略される。
『夏の夜の夢』の多くの舞台がそうであるように、劇中劇を演じるアテネの職人たちの演技がこの劇の面白さを左右するといってもよいが、その演出と演技はここでも非常に楽しませてくれるものであった。
特に、ボトムを演じたトミー・サイマンとフルートを演じたアイザック・カルヴィンの演技は秀逸であった。略歴を見るとサイマンは11歳で『王様と私』のツアー公演でルイスを演じており、オックスフォード大学でも数々の舞台に出演し、その一方で音楽活動もしていて、オックスフォードでも最古の歴史を誇るアカペラ・グループの音楽監督を務めたとある。
キャスティングの中でもう一つ注目されたのが、妖精の王オーベロンよりも大柄な体格でパックを演じたアリ・ポーティアス。5歳で、スカーフ以外には一糸まとわぬ姿での演技の肉体表現演劇で初舞台、今回のパック役ではその大柄な体格にもかかわらず、肉体演劇のパーフォーマンスを活かした軽やかな身体演技を見せてくれた。
台詞回しとしては、貴族たちの発音に対して職人たちのアクセントには訛りを持たせ、その例の一つとして'love'の発音などでは貴族たちは「ラヴ」、職人たちは「ロヴ」と発音していたのも細かい演出の特徴の一つであった。
聞かせどころの台詞のカットがかなりあったが、ダイナミックで動きの速い所作で、逆に劇のテンポに弾みをつけていた。
来日公演でよく見られる光景だが、台詞の一部にちょっぴり日本語を取り入れる観客サービスも御多分に漏れず今回も織り込まれていて、4人の若者たちのヘレナをめぐっての喧嘩騒動の中で、「女神」や「森の妖精」などという日本語が耳に飛び込んで来た。
この劇の終わり方も劇の面白さ、楽しさを左右するが、職人たちの劇中劇も終わったところでボトムが「エピローグ」の口上を「見せましょうか」それとも「バーゴマスク・ダンス」を「聴かせましょうか」という台詞に、シーシュースはそのどちらも無用だとすげなく拒否するが、ヒポリタがバーゴマスク・ダンスを希望して職人たちが踊り始め、そのうちに貴族たち全員も加わっての賑やかな大円団となる。
その場からフィロストレート役のマドレーヌ・ウォ-カーが役の衣装を脱ぎ捨て、最初の場面でヴォーカルのパートを務めた場所で歌を歌う。
そのようにして、最後の妖精たちの登場はなく、バーゴマスク・ダンスの大円団の最中にパックが登場し、エピローグの台詞で舞台を結ぶという印象深い終わり方であった。
演出、演技ともに非常に楽しむことが出来た舞台であった。
演出/ウィル・フェルトン、8月13日(土)13時30分開演
東京芸術劇場・シアターイースト、 チケット:2300円(団体)、座席:D列11番
|