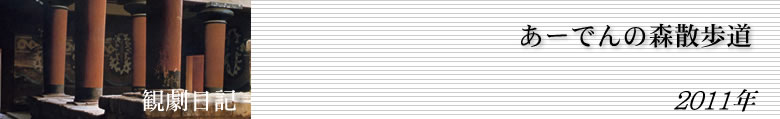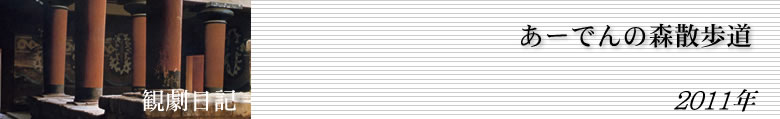|
シェイクスピアの『ヴェニスの商人』は、ある意味において不幸な作品である。
金貸しのシャイロックがユダヤ人であるということで、その時代における偏見と制約を受け、ナチスのホロコーストの後では、上演すらどこか憚るものがあるのもその一つだろう。
アーノルド・ウェスカ―の『シャイロック』は、彼が1973年に観た、シャイロックをローレンス・オリヴィエが演じ、ジョナサン・ミラーが演出した『ヴェニスの商人』への違和感から生まれた。
彼が知っているユダヤ人はシャイロックとは異なる。何かが間違っていると彼は思った。
肉一ポンドを切り取れないとポーシャから宣言されたとき、彼の知っているユダヤ人なら、人の命を奪うことから解放されて「神に感謝!」と叫んだであろうと彼は感じたという。それは彼自身がユダヤ人の生まれであるからこそ抱き得る違和感ではないだろうか。
ウェスカ―の眼を通して焼き直しされたシャイロックは、ユダヤ人問題以外にも劇中人物の問題点を異なった形であぶり出してくれたことで、この舞台は一段と興味あるものとなった。
シェイクスピアの時代であるヴェニスは、1516年に世界初のユダヤ人の居住を制限するゲットーが作られ、ユダヤ人は外部との接触を抑えられただけでなく、外出する際にはユダヤ人であることがわかるように黄色い帽子の着用が義務付けられていた。そのことがこの劇の大きな意味を持たせる。
ウェスカ―のシャイロックは、書物を愛し、娘を盲愛している。彼自身が十分な教育を受けられなかったことで娘のジェシカには何人もの家庭教師をつけて教育を受けさせた。
彼が書物を愛するのは、彼が十分な教育を受けられなかったことへのコンプレックスの裏返しでもある。
彼の誇りは、書物を大事にすることであり、教皇によるタルムード焚書命令(1553年)で焼き尽くされた書物を隠し持っていてそれを保存できたことである。その保存された書物をシャイロックの口実でアントウニオウが筆記しているところからこのドラマは始まる。
アントウニオウはシャイロックへの尊敬と限りない友愛を抱いており、もっと早く、もっと若いうちにシャイロックと出会っていたらと悔やんでいる。ふたりは初老の域に達している。
アントウニオウは今回の交易でビジネスから身を引く予定で、全財産をかけて船を世界各地に送り出している。そんな折に彼が名付け親となっている青年バサーニオウが訪ねて来る。
アントウニオウは名付け親となったことでそれまで面識もなかったバサーニオウと会うことを煩わしく思うが、結局は彼のために三千ダカットのお金を都合立てる。そのために彼はシャイロックから金を借りることになる。
シャイロックは二人の友情の中では、お金を貸すのに証文も保証も必要ないと言い張るが、アントウニオウはそれではヴェニスの法律に反するといって、頑なに証文を交わすことを主張する。
それならば、とシャイロックロックは自分らを拘束する法律をとことんからかってやろうと言う。
そこで借用書の証文として、約束の期限に約束の金額を支払えない時には、シャイロックはアントウニオウの身体から肉一ポンド、好きなところから切り取ることを、全くのジョークのつもりで契約の条項に入れる。
シェイクスピアのシャイロックでは、そこに隠された底意があるが、ここでは法律をからかうという目的だけであるが、法律を笑うものはその法律からしっぺ返しを食うのである。
約束が履行できなくなったアントウニオウはシャイロックから肉を切り取られることになるが、契約を守るということで自らの民族を守ろうとするシャイロックは、ヴェニスの総督が契約の実行を避けることができるように弁明の機会を与えるが沈黙を守り通す。
ここで話は少し戻るが、バサーニオウがプロポーズしたポーシャは普通の女性として描かれ、箱選びでバサーニオウが無事に正しい箱を選んでも、盲目的に彼を愛することはしない。
理知的さにおいては侍女のネリッサの方がしっかりした意見をはく。アントウニオウの裁判にポーシャに行くように焚きつけるのは彼女の方である。
沈黙を守って行き詰った裁判に決着をつけるのは、常識の眼で物事を見るポーシャによってである。
彼女はシェイクスピアのポーシャとは違って、裁判官に扮装して出てくるわけではなく、ただ契約書を読んでその矛盾に疑問を抱き、契約の無効を訴えるだけである。
契約書には肉一ポンドをきっかり切り取るとあるが、血を流さずに肉を切り取ることは不可能だからこの証文は無効である、それにきっかり一ポンドの肉を切り取ることも不可能であるから、この契約には実効性がないということで無効だと彼女は主張するのだった。
ポーシャの常識的な判断に救われた総督は契約の無効性によってアントウニオウを救うが、シャイロックに対しては、ヴェニスの市民の生命の危険を犯したということで、財産の没収、すなわち彼の蔵書すべてを没収することになる。シャイロックは、はじめは悲しむがむしろすっきりした気持となって、晴れやかに聖地エルサレムへの巡礼に出る。
アントウニオウの積荷も無事に戻り、すべてを虚しく思う彼の夢は商売を引退した後、エルサレムの地にシャイロックを訪れることである。
『シャイロック』についての主筋はざっとこんなものだが、脇筋も面白い。
初老のシャイロックとアントウニオウという旧世代と、バサーニオウとロレンゾウに代表される若者の世代、この両世代のものの考え方に対する対立が興味深い。
バサーニオウは商品取引という貿易ではなく、銀行を通しての金融取引で経済を動かしていくという次世代の眼をもっているが、人物としては打算的で、計算高い人間のように見え、好感をもてない人物である。
一方ロレンゾウは高等教育を受けながらも、若いということだけで、古い因習のもとに元老院に加われず、政治を動かすことにもできないことに体制への不満を抱いている。彼にできることはそういう不満を民衆にアジテートするだけであるが、根本にある彼の考え方はアントウニオウに指摘されるまでもなく、実は非常に保守的で、実に嫌味な人物であるが、それを演じた大多和民樹の嫌味たらしさが絶品。
シャイロックから高等教育を受けさせられ、それに反発するジェシカはロレンゾウのもう一つの側面である詩人的浪漫性には惹かれるが、彼の内なる倨傲、傲慢さに気付き、彼と駆け落ちしたものの、結局は結婚しないだろうことを予想させる。ジェシカはシャイロックに向かって言う。「お父さんを見捨てはしない」と。
ポルトガルの異端審査で迫害を受けているユダヤ人を救出する活動をしているレベッカをシャイロックが援助するが、そのこともこのドラマに膨らみを与えている。
また、シャイロックに人間性のふくらみを与えているのは、彼に姉リヴカを創造していることである。
リヴカはシャイロックがジェシカに高等教育を受けさせることを親のエゴだとして戒めるが、自分が正しいことをしていると信じているシャイロックにはそのことが通じない。
シャイロックは同胞や友人には包容力をもって接するが、一方で自説を曲げない頑なさを持っている。
シャイロックに松下重人、アントウニオウに竹口範顕、バサーニオウに公家義徳、ポーシャに清水優華、ジェシカに樋口祐歌、シャイロックの姉リヴカは志賀澤子が演じた。
全体的に緊張感のある、濃密な舞台で、この演劇集団の中心であった広渡常敏氏が亡くなって以来初めて観る劇となったが、これを機会にまたブレヒトの芝居小屋に通いたくなる気持を起させた。
作/アーノルド・ウェスカ―、翻訳/竹中昌宏、演出/入江洋佑
9月13日(火)19時開演、ブレヒトの芝居小屋、チケット:2500円、全席自由
|