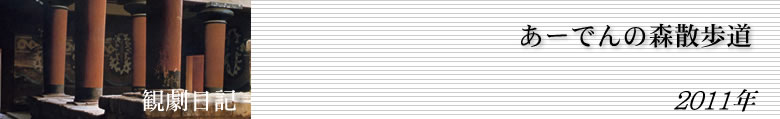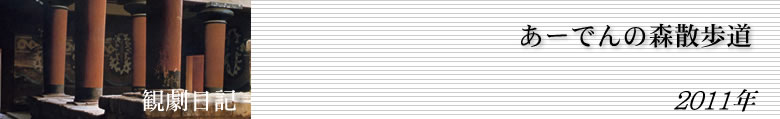|
平幹二朗のシャイロックということで期待感を持っていたが、宮城聰の劇を観た後では浅利慶太の演出が古びた化石のようにしか感じられなかった。
プログラムに寄せた浅利慶太の前口上「牽牛付会の『ヴェニス』論」も、1968年、日生劇場での劇団民藝提携公演のプログラムからの抜粋転載という付け足しのものでしかなく、そこになんら新しいものがなかった。
当時の公演を観ていないので再録自体はありがたいのだが、再録だけで今回の公演に当たっての新たな発信がないというのは、それだけ初演の演出に自信があって、変わらぬをよしとするのであろうか。
ここで改めてシャイロック論を弁じたいと思わないが、自分にとっては再演の意味をあまり感じない、というより、まったくといってよいほどに意義を感じないものでしかなかった。
全体の印象としても半世紀前の「赤毛もの」の劇を観ているようで、退屈であった。
野村玲子が演じるポーシャも、メルヘンチックなおとぎ話のような作りで、気恥ずかしくなるものだった。
浅利慶太は、台詞回し、特に発声法にこだわりを持つと言われているが、今回の劇を観ていて(というより、聴いていて)、俳優たちの発声が純粋培養されたような画一的な台詞回しで、人物像に特徴がなく、平面的な造形で、目をつむって聴いていると、登場人物の誰がしゃべっているのか分からない。
朝日新聞の劇評欄(6月9日)で山口宏子も「発音は明瞭だが言葉が平板に聞こえる俳優が目につくのが惜しい」と評しており、この点では一致した意見である。
さすがに平幹二朗の台詞には深みがあり、聞かせるものであったが、人物造形としては物足りなさを感じた。
何より不満を感じたのは台詞のカットである。山口宏子は「台本も刈りこんで、舞台はテンポよく進む」と好意的に評しているが、自分としては不満であった。
物語の流れを理解するのにはそれでよいのかも知れないが、ここでその台詞をカットするのかよ、というようなカットが多すぎた(カットの個所をいちいち挙げるには余りに多すぎるので省略)。
先日のSPACでの宮城聰のアフタートークでの言葉が現実のものとして甦ってくる。
台詞が情報過多で、「ああ、もういい、分かったからもうやめてくれ」という気持であった。
大御所の作品とは、えてしてこんなものかと思った。
翻訳/福田恆存、演出/浅利慶太、装置/金森馨・土屋茂昭
6月8日(水)18時30分開演、浜松町・自由劇場、チケット:(S席)7000円、座席:1階7列11番
|