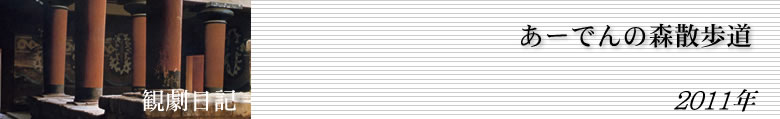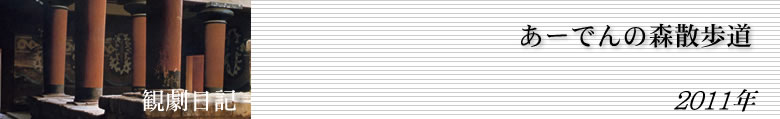|
― 演劇における「詩」の復権 ―
朝7時前に家を出て、西武新宿線、山手線と乗り継ぎ、品川から新幹線で三島まで。三島からはSPACの出迎えバスで劇場までおよそ1時間半。劇場に着いたのが12時少し前、ちょうど開場時間になるところであったので、周りの風景に親しむ間もなく、バスを降りて直行で劇場内に向かった。
最初に驚いたのが座席。前売りチケットで座席がL列7番となっていたのでかなり後部座席だろうと思っていたが、劇団員の案内でついて行くと、自分の席は前列から3番目であった。
舞台を見るとかなり前に張り出しているようだったので、前方の座席を取っ払って舞台にしてしまっているのかと思ったが、気がついてよく見ると前の列がMとなっており、列が通常の全く逆になっていて最後部がA列になっているのだった。この逆転の発想に、この静岡芸術劇場の思想を見る思いがした。
さらに劇場全体を見渡すと、全体がすり鉢状の構造で半円形をなしており、観客席が舞台を包み込むような形をしていて、心に温みを感じさせるものがあって、親密感を覚えた。
初めての劇場というものは刺激的で、興奮を感じることがあるものだ。この静岡芸術劇場がまさにそれであった。今回の観劇で二つの楽しみ、期待感があった。
一つは野田秀樹のシェイクスピア作品の潤色、『真夏の夜の夢』を見ることができるということ、今一つはク・ナウカ以来、久しぶりに宮城聰の演出を見ることができるということであった。
野田秀樹のシェイクスピア潤作劇は、『廻をしめたシェイクスピア』(1994年、新潮社刊)で、『真夏の夜の夢』、『から騒ぎ』、『三代目、りちゃあど』の三部作を読んだことがあるだけで実際の上演を観たことがなかったので、一度は是非観たいと常々思っていた。
今回、<ふじのくに/せかい演劇祭2011>で宮城聰が演出することで、一挙にその二つの願望がかなった。
しかも野田秀樹の『真夏の夜の夢』の場面は富士山を舞台にしているので上演の場所としてもこれほどふさわしいものはないだろう。
舞台の見どころとして、深沢襟による舞台装置が圧巻であった。
創業130年の割烹料理屋「ハナキン」の海鮮料理店をイメージするかのように、舞台全体が海底か、海辺のような礒の香りのする風景に、森の木々を表象する細いポールが林立し、うっそうとした混沌が覆っている。
後景の森は、暗い闇に包まれている。
そぼろが舞台下手から上手へと、一歩、一歩と歩みを確かめるような静かな足取りで、「不思議なことが起こると、それは夜のせいだとか、夏のせいだとか」という台詞を一語一語噛むように吐き出す。
だが肉体とその言葉はまったく別の世界に所属しているかのように言葉を紡ぎ出す。
突然のようにして、白い衣裳のときたまごが狂ったように、森の中を全力疾走で上手から下手へ、下手から上手へと二度、三度と走り抜ける。それはまるで白い妖精のように見える。
どういう舞台を観ても、まず初めの出足に注目してしまうのだが、始まり一つで、舞台のすべてが見えてくる。
台詞と所作を二人人役で演じるク・ナウカで用いた手法を、この劇ではひとりの俳優を分化させて、所作と台詞をあたかも別の者が演じるようにさせ、そのことによって言葉に「詩」としての響きを感じさせる。
宮城聰が演出において目指す演劇における「詩の復権」を、そのことで成就しようとする。
台詞と所作が分裂した状態では、それを聞くものにとってある種の緊張を感じ、そこに詩が生まれる。
対話の台詞も時に、相手に向かってではなく、お互いが距離を置いて、正面に向かって語りかけ、相手はまるで虚空にいるかのようで、そこはかとないポエジーの世界が広がる。
宮城聰が目指すもの、それは公演後の造形美術家の小谷元彦とのアフタートークの中でも明らかにされるが、彼が演劇に求めるものとして、第一に「詩」、そして「音楽」、最後に「世話」(物語性?)をあげる。
それが演劇における「詩の復権」であり、音楽は今回の劇にも見られるように「祝祭音楽劇」として展開される。
劇を「詩」化するために、言葉の情報化を避け、余分なものを削っていく。その結果が所作と台詞の分離となる。
肉体と言葉が分離して、遠い関係となり、そこに西脇順三郎のいうポエジーの世界が生じる。
出演の俳優が自ら楽器をもって演奏することで祝祭としての音楽劇を堪能させられる。
言葉や、語りについてこだわりを持つ宮城聰の格好の素材がここに集約されている。
野田秀樹の戯曲もシェイクスピアのように饒舌であるが、その饒舌を宮城聰は台詞を遮断し、語りをそぎ落としていくことで情報過多を抑え、劇を詩化する。
この劇を見て感じたことは、この劇の主人公とテーマは「そぼろ」と「メフィストフェレス」であるという強い印象と確信である。この二人の登場人物が「ことば」ということについて一番核心をついた台詞を口にする。
従って、この二人の台詞と所作の分離が一番際立っていた。
台詞の語りの魅力以外にも、出演者の身体表現の柔軟さと強靭さにも眼を見張る。
細いポール上の上で水平な姿勢を保ったり、ストップモーションで止められた動きの姿勢を長い間そのまま保っていたりするが、それが苦痛に感じられないような自然な状態であることに驚く。
そぼろのせいで「知られざる森」が燃える情景は、3・11の東日本大震災の後では象徴的にすら見える。
時期的にすれば、この劇の選択と3・11は直接的な関連性はないだろうが、森が燃える赤い情景を見ていると、いやでもそのことが思い浮かばれてくる。
終演後、小谷元彦と宮城聰のアフタートークは、この上演を理解する上でというより、二人の芸術的な姿勢を知る上で有意義なものであったが、トークの最後の方になると芸術論が一種の宗教的な高みにまで進んだ。
特に印象的だったのは、演劇は詩であるということについて表現するのに、隕石が落ちてきて、心にクレータの深い痕跡を残す、その衝撃が詩であるということについて共感を覚えた。
私の観劇評価: ★★★★★
原作/W. シェイクスピア、訳/小田島雄志、潤色/野田秀樹、演出/宮城聰、
6月5日(日)12時30分開演、静岡芸術劇場、チケット:(ゆうゆう割引)3400円、座席:1階L列7番
|