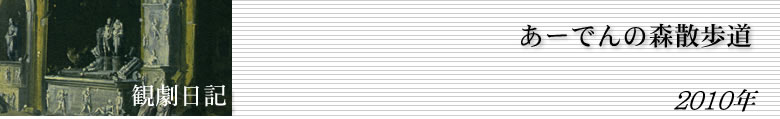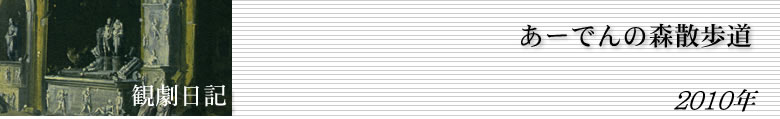|
― 英語・ドイツ語・韓国語・日本語上演 ―
4年前、新国立劇場(中劇場)でチェーホフ記念モスクワ芸術座による公演で鈴木忠志演出の『リア王』を観ているので、その観劇日記の記録を手繰ってみたが残念なことに記録していなかった。
プログラムを参照すると、使用する音楽がモスクワ芸術座の3曲(ヘンデルの「ラールゴ」、チャイコフスキーの「スペインの踊り」、ライバッハの「KRST」)に対し、4カ国語版ではそれに日本の中田章作曲・吉丸一昌作詞の「早春賦」が加わっている。美術(戸村孝子)、衣裳(岡本孝子)については変わっていない。
前回はモスクワ芸術座公演ということで、言葉としては当然ながらロシア語であった。
今回は、ドイツ語、英語、韓国語、そして日本語の4カ国語による上演であるが、印象としてはまったく違和感を覚えなかった。違和感がないのは鈴木忠志の演出に言語を超えた普遍性があるからだろう。
その演出については「初演の演出ノート」に<世界は病院である>と題して詳しく述べられているので、くどくどしく記録する必要もないが、人間の狂気というものについて考えさせられる。
車椅子に乗った老人(リア王)をドイツ人のゲッツ・アルグスが演じるが、仁王像のような風貌を感じた。
リア王の車椅子に寄り添う看護婦(男優)はリアに無関心に傍らで本を読んでいる。その看護婦が読んでいる本の内容が演じられ、進行していくという構造を直感的に感じる(それは前回にも感じたことである)。
『リア王』の物語の展開の中で、別の看護婦が登場し、精神病患者の老人としてのリア王と関わりを示すが、その看護婦自体が狂気の様態を感じさせる。
また、看護婦の一群が通過していく中で唱歌のように「早春賦」を歌うが、それが一部調子外れに歌われるので、歌に懐かしさを感じる半面、どこかまともでないことを感じさせるのだった。
鈴木忠志の演出は、台詞の語り様と所作に特徴があるが、それ以上に舞台の陰翳に美意識を感じる。
全体としては能舞台の荘厳な様式を感じる。
1時間40分という短い時間の中に濃密な世界が展開され、緊張を感じる舞台である。
終りに、シェイクスピア時代のジグ踊りに変わって、能の所作のような様式化された手の動きで示す踊りが 『リア王』の登場人物によって披露され、それがフィナーレとなるのも印象的だった。
鈴木忠志の舞台を観て感じることは、いつもながら演劇の在り方について考えさせられることだ。
演劇論が具現化された舞台とでもいうような、抽象性の高い演出だと思う。
演出/鈴木忠志
12月20日(月)19時開演、吉祥寺シアター、チケット:5000円、座席:F列14番
|