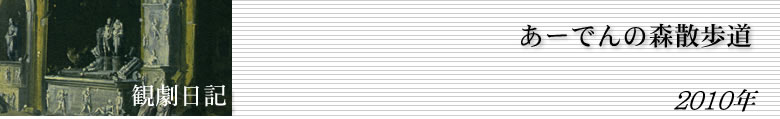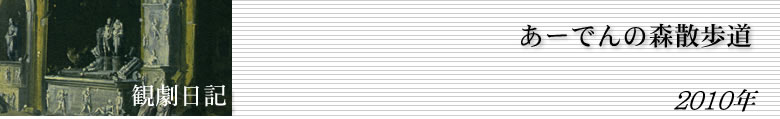このたびの本橋哲也先生主宰の英国観劇ツアー(11月26日〜12月6日)は、シェイクスピア劇3作とその他の劇3作の組み合わせで、その他の作品については本橋先生の選択の意図を想像するという興味がわいて、別の面白みがあった。
シェイクスピア劇は、『ハムレット』、『ウィンザーの陽気な女房たち』、『ロミオとジュリエット』、その他の作品は、アーサー・ミラー作『壊れたガラス』、テネシー・ウィリアムズ作『ガラスの動物園』、イプセン作『老建築師』であったが、ここではシェイクスピアを中心にまとめる。
●11月29日(月)夜、ナショナルシアター・オリヴィエ劇場にて 『ハムレット』
演出:ニコラス・ハイトナー、装置:ヴィッキ・モーティマー
舞台は水平に展開する構造で、城壁や室内の壁となる装置が可動式となっていて、前後左右に移動することで場面転換が速やかに進む。
全体的に装置はシンプルな構造で、色調は限りなくグレーであるのがこの劇の特徴を表象しているように感じる。
ハムレットは絶えず監視の目にさらされており、劇に緊張感が漂う。
冒頭の夜警の場面から転じて、クローディアスが先王ハムレットの哀悼の辞とガートルードとの結婚の披露を記者団のマイクを前にして演説する。
クローディアスの後ろには、哀悼の意を表すようにして、額縁に収められた先王ハムレットの肖像画が掲げられているが、その後の場面では室内に掲げられる肖像画はクローディアスを描いたものに変わる。
クローディアスの表情は、ロシアのプーチンを想起させる顔立ちをしているのも特徴であった。
クローディアスの記者会見の間中ハムレットは後方にいて、椅子に座ってじっとうずくまった姿勢を保つ。
ハムレットの背後の壁の反対側には、その壁を背にして両サイドに二人の男が盗聴器のイヤホンを耳に当てハムレットを監視している。
クローディアスの記者会見中、ガートルードは媚びるような笑みを憚りなく向けているのが娼婦的である。
彼女は王妃の服装ではなく、平服に近い現代の普通の洋装である。
ガートルード(クレア・ヒギンズ)はアル中気味ではないかと思うぐらい、ワイングラスを常に手にしているのも特徴的であった。
クローディアス(パトリック・マラハイド)は軍人というより、外交的手腕にすぐれた政治家、策謀家を演じる。
ポローニアス(デヴィッド・キャルダー)は人のよい単なる忠臣ではなく、スパイの元締めのような一面を示す。
息子のレアティーズの素行を調べるためにレイナルドをフランスに送り込むのはその一面を表わしている。
ポローニアスは雲を見て、鯨だ、イタチのようだなどとハムレットに同調して相槌を打つが、その表情に苦々しさを含んだ冷徹さが垣間見え、彼の諜報者としての側面が表れる。
そんなポローニアスを演じるデヴィッド・キャルダーが墓掘り人としての道化を演じる、そのコントラストが面白い。
亡霊ハムレットを演じるジェイムズ・ローレンソンが、劇中劇で国王役の役者を演じるダブリングも面白い趣向であると思った。
ハムレットとオフィーリアが出会う尼寺の場面では、オフィーリアの父親ポローニアスがどこにいるかを尋ねた時、家にいますと彼女が答えると、それまで抑えていた感情が爆発したかのようにオフィーリアが手にしていた本(祈祷書?)を奪いとって、それをマイクにして口に当て一気に呪いの言葉を吐きつける。
その呪いの言葉は表向きオフィーリアに向けたものであるが、ハムレットは自分が監視されていること、盗聴されていることを覚っていて、敢えてその挙に及んでいるのが見てとれるのだった。
話し終えた後その本を床に投げ捨てると本が開いて中から隠しマイクがポロリと転がり落ちるが、ハムレットにはそれは驚きではなく、周知のことでしかなく目もくれない。
ハイトナーの演出で凄味を感じたのは、狂気のオフィーリアが自殺ではなく、殺害を暗示させるようにして諜報部員が彼女を拉致していく場面であった。
この劇全体の印象が監視という大きなテーマに包まれているだけに、この場面は衝撃的でさえあった。
だが何と言ってもこの劇を最高に感じさせたものは、ハムレットを演じたロリー・キニアの演技と台詞力であった。
ハムレットという人格の多面性を演じ切っており、単に鬱な青年でもなく、躊躇する優柔不断者でもなく、かといって決断者というわけでもない、揺れ動く心情を語る独白も一本調子ではない、複雑性を出している。
タイムアウトの劇評で五つ星がついているが、演出の斬新さと新しいハムレット像にもろ手を挙げてその高評価に賛同する。
座席はAisle 2, C15 で、前列から3番目で比較的中央の席で申し分ない位置であった。
上演時間は、途中休憩をはさんで約3時間半。
私の観劇評価: ★★★★★
●11月30日(火)夜、リッチモンドシアターにて 『ウィンザーの陽気な女房たち』
演出:クリストファー・ラスコム(Christopher Luscombe)、美術・衣装:ジャネット・バード
タイムアウトの劇評では四つ星の評価で、見るからに面白そう、楽しそうな雰囲気として紹介されていてかなり期待していたが、時差ぼけの睡魔に襲われてほとんど眠ってしまって肝心の台詞を聞き逃すことしきりであった。
劇そのものは田園調的、牧歌的な明るい雰囲気で楽しいものであるが、それがいつの間にか寝入ってしまうのだった。
舞台美術と衣裳(ジャネット・バード)はシェイクスピアの時代を想像させ浮き浮きした楽しさを感じさせてくれるが、見やすい構造である開帳場(八百屋)風の舞台が、額縁舞台のためか奥行きがないので動きが単調で平板に感じてしまう。そのため感動がわいてこないのだった。
評価の高かったクリストファー・ベンジャミンのフォルスタッフの演技もなんとなく動きが鈍く感じられ、さほど印象に残っていないのが残念である。
印象度が強いのは、フォード夫人とペイジ夫人のお茶目で愛くるしい演技。
フォルスタッフにいたずらを仕掛け、それを面白がっては二人がお尻とお尻をくっつけあう仕草などほほえましい可愛さがあった。
目が覚めたのは、最後の全員で踊るジグダンス。これが一番楽しかった。
地元の観客らしき人たちの笑い声が絶えずどこからか聞こえたのは、この劇場のもつ雰囲気のようなものを感じさせた。
私の観劇評価: ★★★
●12月1日(水)夜、ラウンドハウスにて 『ロミオとジュリエット』
演出:ルパート・グールド、装置:トム・スカット
座席が第一の不幸であった。
大きく張り出した張り出し舞台の奥の端っこで一番隅の席だったため、舞台をほとんど後ろ側から見る形になるだけでなく、バルコニーシーンなどは上を見上げても、人物の動きがまったく分からなかった。座席の不満が演出のグロテスクさに余計に増幅され、観ているうちに腹の立つことしきりであった。
舞台の色調は漆黒の闇―ブラック。
冒頭のプロローグの部は、最初にイタリア語で話され、続いて英語の台詞が続く。
舞台では、現代の若者風の格好をしたロミオが一眼レフのカメラを首から下げてお上りさんのようにキョロキョロ動き回っているのも意味ありげにした演出と察するが、つまらない。
衣裳については、ロミオとジュリエットだけが現代服。その他の登場人物には当時のイタリア風衣裳を着させているが、その区別に意味のない作為性を感じる。
ところが最後の場面、ロミオとジュリエットが亡くなった後駆けつけてきた人物たちはいずれも現代服で、なかでも修道士ロレンスから状況を聞き取る人物は、刑事のような振る舞いでメモを取っており、これなども奇をてらった演出にしか感じなかった。
気になる演出、というか腹立たしい演出がいくつかある。
その最たるものがロミオとジュリエットの演技。
ジュリエットはブルーの半そでのワンピースを着て、ヨーヨーのようなものを振りまわし、不良少女のような仕草で、その姿に清純さを感じさせるものが全くなく、胸糞が悪くなった。
ロミオとジュリエットの出会いの舞踏会の場は、アフリカの土人の舞踊を思わせるような踊りで、巡礼の出会いのような清らかな雰囲気ではなく興ざめ。もっともヨーヨーをブンブン振りまわすようなジュリエットの姿を見た後では、聖者に感じることなどほど遠いだろう。
後朝のバルコニーシーンでは、二人の姿は自分の席からは見えず、ジュリエットがバルコニーに腰かけて足をぶらぶら揺らしている、その足だけが見え、情緒感など望むべくもないものだった。
乳母は黒人俳優のNoma Dumezweni が演じているが、これがまたひどい。主人の前で、長煙管の煙草をスパスパ吹かしてはのし歩く、傍若無人の態度である。朝食に出されたフルーツの皮をむいているので、それを主人に差し上げるのかと思うと、そうではなく自分でムシャムシャ食べている態度などは、使用人としては考えられないことだと思う。
今一つ気になった演出は、やたらと舞台に火を使うことであった。それもマジック的なようにして火を噴き出さすので、象徴としての火を感じさせるよりは、こけおどし的なものに感じてしまうものであった。
これがロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの『ロミオとジュリエット』かと思うと、腹立たしい以外に何もなかった。おまけに最低の席でありながら、今回のツアーでは一番高い料金(25ポンド)だったいうのも腹が立つ。
不満だらけの舞台であった。
私の観劇評価: ★ (むしろマイナス点をつけたいくらいだが、逆説的にいつまでも記憶に残りそうな舞台)
|