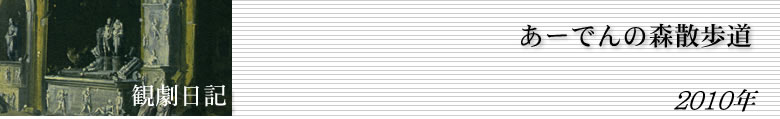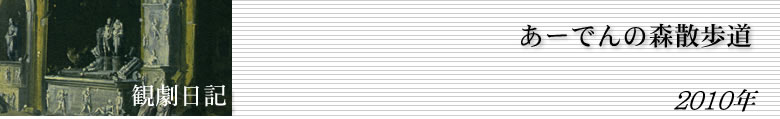― 喜劇はオールメイルがお似合い?! ―
喜劇はオールメイルがお似合い?!
蜷川幸雄の彩の国さいたま芸術劇場でのシェイクスピア上演は今回で23作目となるが、そのうちオールメイルによる上演は、2004年の『お気に召すまま』に始まって、『間違いの喜劇』(2006年)、『恋の骨折り損』(2007年)、『から騒ぎ』(2008年)に続いて、『じゃじゃ馬ならし』は第5作目となる。
開演前の舞台は幕の代わりに、舞台全面を額縁のようにしてシェイクスピア当時の建物形式である木材と漆喰でできた家の正面が舞台装置として表出され、窓には色とりどりの花が飾られていて、全体が明るい日差しに包まれたような陽気さを漂わせている。
下手側に扉があり、舞台が始まるとそこから居酒屋のおかみに追い出された鋳掛屋のスライが転がり出てくる。
蜷川幸雄の舞台で楽しみなのは、テクストに表現される台詞に忠実な演出であるということで、見る側としてもそれをどのように舞台化してくれるのかという期待がふくらむ。
鋳掛屋スライの序幕が省略される上演もあるだけに、序幕の2場面を丁寧に舞台化されているのを見ることができるという楽しみと、見終わってこの舞台全体の構造をとらまえるとき、この劇が劇中劇を演じているのかどうかという解釈の多様性を感じさせるものがあってそれが余韻とも余情ともなる。
序幕2では、舞台は変わって領主の館の居間、中央に天蓋のついた豪華な寝台、そしてあでやかな衣装を着せられたスライが眠りこけている。
部屋の壁面にはルネッサンス時代を感じさせる絵画がいくつも飾られている。
領主の館に役者の一行が現れるが、原作では使者が役者の到来を告げるだけだが、この演出では『ハムレット』で、役者たちが登場する場面を再現するかのように、実際に役者たちを登場させ、ハムレットが役者たちを迎えてねぎらう台詞を領主に語らせる。
その部分はテクストの改変となっているが、舞台を見ている時はそのことに気づかなくて、『ハムレット』の場面そっくりだな、という印象だった。
役者たちの芝居を観るためにスライと奥方に扮した小姓は観客席に座って、劇中劇が終わるまでそのまま劇を見続ける。
一幕一場の終わりに従者がスライに芝居が気に入ったかどうか尋ねる場面があるが、これも従者が観客席に降りて行って、スライに話しかけ省略されずに演じられたのが印象的であった。
話が前後するが、本舞台が始まる(劇中劇が始まる)前に、スライと小姓を除いた登場人物全員が勢ぞろいして、幕が下ろされた舞台の前方で音楽に合わせてステップを踏んで一周、二周と手を振り振り顔見せのようにして巡行し、お祭り気分へと誘い込む。
ここでもう観客はうきうきと芝居見物の気分になる。
本舞台は、舞台装置としては特に何もない。
舞台奥行きを台形にして、ボッティチェリの『春』の絵の垂れ幕がホリゾントと両側面の壁面として使用されている。
最初は『春』の全体が描かれたものであるが、場面転換ごとに、その絵の一部をそれぞれ拡大したものが使われて場所の変化を表わす。
シンプルなセットだが舞台変化、場所の変化としては分かりやすく、面白い工夫だと思った。
肝心な中身であるが、『じゃじゃ馬ならし』がフェミニズムの非難の的であるとか、一種の問題劇として捉えられることが多く、そのことがこの劇を上演する際の障害にもなっている面があると思うが、蜷川幸雄の演出は明解である。
蜷川幸雄は、それは「いかれた男女の恋愛」であり、全体が狂気であるとも言えると語っている。
それを表象化したのがキャタリーナを演じる市川亀治郎である。歌舞伎役者である市川亀治郎が演じるキャタリーナは、これまで観てきたキャタリーナとは全く異なったもので、そのじゃじゃ馬振りは所作、アクションにあるのではなく、動きを抑えたような様式化された所作と台詞回しに特徴が集約される。
たとえば、二幕一場キャタリーナが妹のビアンカを縄で縛って手荒く扱う場面では、ふつうキャタリーナがビアンカを縄で縛って引きずりまわすことが多いが、ここでは台詞の通りで、ビアンカは手を縛られた状態だけで、縄でつながれた状態ではなく、台詞通りの所作で、荒々しく激しい動きは一切ない。
キャタリーナに殴られたビアンカが気絶してしまって、駆けつけた父親のバプティスタが言う本来の台詞、「泣いているじゃないか」ではなく、「気絶しているじゃないか!」と言い換えている面白さに思わず笑ってしまった。
筧利夫が演じるペトルーチオが機関銃のようにしゃべくりまわる台詞と、それを受ける市川亀治郎のキャタリーナの台詞言い回しの位相差、ズレがおかしみを誘発する。
蜷川幸雄がテクストの台詞に忠実な面はいろんな場面で遭遇するが、キャタリーナとの結婚式の日のペトルーチオの衣裳と、いでたちもその好例だろう。
今夏、OUDSによる『じゃじゃ馬ならし』の公演があったが、そこではペトルーチオはなんと裸で登場という意表を突くものであったが、テクストの表現を忠実に表出した舞台がかえって新鮮に感じられたのは、この場面を表現するマンネリ化の反動の両作用だろう。
台本の元になっている翻訳者松岡和子がちくま文庫の「あとがき」に書いているが、原文の最後の2行、
HORTENSIO: Now go thy ways; thou tamed a curst shrew.
LUCENTIO: 'Tis a wonder, by your leave, she will be tamed so.
と下線部が現在完了形でなく、未来形になっている点が問題となる。
キャタリーナは馴らされてしまったのではなく、そうやって馴らされていくんだろうという未来に開かれた形になっている。この点に関して蜷川幸雄の演出に注目したのは、キャタリーナがペトルーチオの指示(命令)で二人の夫人、ビアンカと未亡人に妻たるものの務めを諭す台詞を語る時、キャタリーナは台詞の途中、ペトルーチオが腰に差している剣を抜きとって、ペトルーチオの咽喉元に着きつけるような仕草で剣を向ける。
一瞬はっとさせられる場面であった。
そのことをどのように解釈するかは観客個人のそれぞれの解釈に委ねられる。
私には、松岡和子が問題提起した未来形の問題とこの所作の解釈が重なってくる。
そしてこの場面が終わり、幕が下りると、登場者全員が役者一同としてこの劇中劇の始まりと同じことを繰り返す。
キャタリーナが舞台中央に突き立てた剣はその時抜きとられるが、だれが抜き取ったのか記憶が定かでないのが残念である。
観客席でこの劇を最初から最後まで観ていたスライと小姓も観客と一緒になって拍手を送ることで、この劇が劇中劇であったことを改めて感じさせた。
市川亀治郎演じるキャタリーナが、結果的には一番印象に残る舞台であった。
訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄、美術/中越司
10月15日(金)18時30分開演、彩の国さいたま芸術劇場、
チケット:(S席)9000円、座席:1階Q列17番
|