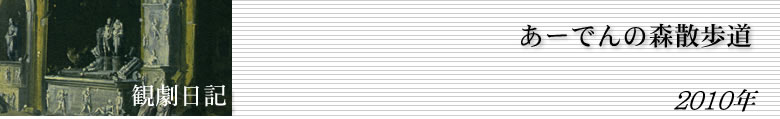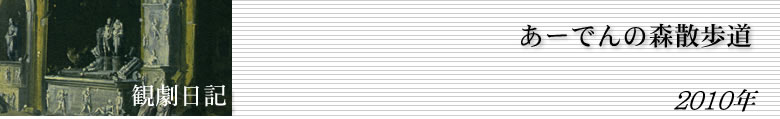OUDS(オックスフォード大学演劇協会)二年ぶりの来日公演。
今回の出し物『じゃじゃ馬ならし』は、2003年での来日公演以来(世田谷のシアタートラムにて上演)で比較の意味でも楽しみであった。
舞台作りは、この公演シリーズとしてはめずらしく、三方を観客席にした張り出し舞台。
三方が観客席ということで、俳優はしばしば観客席通路から登場し、舞台が動的であるだけでなく、観客をその舞台の一部にする、つまり観客も時にその劇に参加している雰囲気をもたらす効果があった。
舞台中央奥に、俳優たちが途中で身につける衣裳を吊るしたハンガーがあり、大小のトランク、それに腰かけ椅子が重ねて置かれているので、おおよその舞台構成が予想できる。
開演前の舞台の照明が淡い紫色でとても印象的であり、柔らかい雰囲気を感じた。
『じゃじゃ馬ならし』は、序幕をつけて劇中劇の構造をとっており、前回の公演では鋳掛屋のクリストファー・スライが劇中でペトルーチオを演じる趣向で、その転換が面白かったのを記憶している。
この序幕をどのように処理するか、また前回とどのように異なっているかが楽しみの一つでもあったが、今回はこの場面がすっかり省略されていたので、それが残念な気がした。
国内の上演でもよく省略されることがあるが、個人的にはこの場面を省略してほしくないという気持が強い。
開演とともに、ルーセンショーが観客席から勢いよく舞台に駆けあがってきて、あこがれのパデュアにやってきた喜びを全身で表現するところからこの舞台は始まる。
『じゃじゃ馬ならし』はガミガミ女を調教するということで、現代では問題喜劇として、ジェンダーの問題や、女性蔑視だのとかしましい論議があってなんだかわずらわしい気がするのだが、もっと気楽に楽しみたいというのが僕としての自然な気持であるが、おおむね女性にはこの劇は大変気に障るようである。ということもあってか、今回この劇を演出したアリス・ハミルトンは、その必要以上の議論のわずらわしさを回避して、劇の中心である恋愛模様をしっかりと描き出すため、劇中において劇中劇の形を入れこむという形式をとっている。
<演出家ノート>によれば、「過去と現在、現実と虚構をあいまいに融合させる」方法を取り入れているのだが、それはたとえば、ピザの老紳士ヴィセンショーの登場(観客席通路から登場)では、彼は観客席に登場したときには現代のスーツ姿であり、登場した場所から彼をこの劇の観客としてみなすこともできる。
舞台上のキャタリーナからいきなり美しいお嬢さんとして話しかけられ当惑するが、それは舞台の俳優から声をかけられた観客の当惑とも重なる。その彼がヴィセンショーとして舞台上に上がると、ペトルーチオから衣裳を渡され、そこで劇中人物と化身する。
ヴィセンショーが息子のルーセンショーを訪ねて偽物のヴィセンショーとの騒動の場では、ペトルーチオやキャタリーナたちは、それを座って眺める観客に化する。
最後に舞台の終わった後エピローグのようにルーセンショーが付け加える台詞も、この劇が劇であることを強調して、問題劇としての論議を忌避している表れであることが、アフタートークでルーセンショー演じたジョー・ロバートソンによって語られた。
演技の面においては、キャタリーナとの結婚式の場面でペトルーチオが下着のパンツ一枚の姿で登場し、召使のグルーミオも場違いな格好の海水浴場の姿で、サングラスをかけて登場するのが、意表を突いた。
キャタリーナを演じるエド・ピアースは、鬱屈した表情でガミガミ女としての内面性を表わしているのが感じられ印象的であった。
二人の女性、ホーテンショーの妻となった未亡人とルーセンショーの妻となった妹のビアンカを説得する場面では、単に夫への従順を説く台詞を言うだけでなく、二人の夫のもとで夫への従順さを表出する演技などは凝っていて、うまい演出だと思った。
シェイクスピアの場合は主役よりも脇役の方が結構面白いことが多いのだが、演技として面白く感じたのは、ホーテンショー、グルーミオ、それにカーティス(フィービー・トンプソンが帽子やと未亡人とカーティスの三役を演じた)。学生だけで演じる舞台なので、登場人物の年齢を演じるハンディはつきものだが、老け役のバプティスタやグレミオなどを演じた学生俳優は、それなりの老け役を出していて好演であったと思う。
最後のアフタートークでは、演出のアリスが観客の質問に答えて、今回来日公演での演目選定として、三つの喜劇の候補があったが、『夏の夜の夢』と『間違いの喜劇』は近年来日公演しているので、この『じゃじゃ馬ならし』を選んだということであった。
また日本での公演と本国イギリスでの上演の違いについては、日本ではこのように劇場で上演されたが、本国ではガーデン(庭園)や教会での上演であったので、登場の仕方からすべて異なっているのと、観客もイギリスでは演劇を勉強している学生などが批評的な目で見て気が抜けないが、日本では観客として暖かく演技を見てくれているので、最高な気分という感想が述べられた。
OUDSの公演で感じるのは、シェイクスピア劇を演出するのにそれなりのコンセプトを常に表出しようとする姿勢であるが、それは本国の観客である学生たちの鋭い観察眼や批評意識があってのことだということが、今回のアフタートークでよく分かり、そのことも興味深かった。
演出/アリス・ハミルトン
8月7日(土)18時30分開演、東京芸術劇場・小ホール2、チケット:(団体)2200円
|