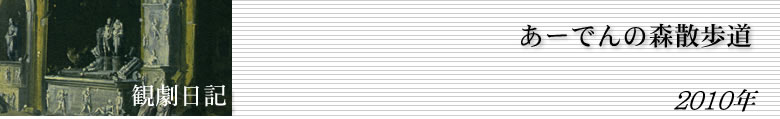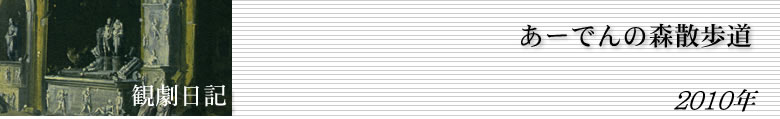|
早稲田大学校友会設立125周年を記念しての催し。
冒頭、早稲田大学坪内逍遥博士記念演劇博物館館長の竹本幹夫氏の挨拶に続いて、第一部がシェイクスピア・カンパニー主宰の下館和巳氏の講演「坪内逍遥のメッセージ」(30分)、第二部で「破無礼〜奥州幕末のハムレット」(90分)が上演された。そのどちらにも深い感銘を受けた。
下館氏の講演を聞いての感激と興奮の気持の高ぶりが鎮まる間もなく、休憩時間もなく始まった第二部の作品上演では、さらに感激と興奮の気持が渦巻いて、終わった後しばらくの間放心状態に陥った。
講演のマクラでは、早稲田大学校友会設立125周年という数字がどれほど意義深いものであるか、下館氏よりエピソードを織り交ぜて披露された。
まず、125という数字が早稲田大学設立の大隈重信公が125歳まで生きていたいと願っていた数字であり、次に大隈重信記念講堂の高さが125尺であることを紹介し、最後には「皆さんが座っている大隈記念講堂の椅子が125万円」というオチを付けられて聴衆の笑いを誘い、講演の始まりの硬さをほぐされた。
下館氏とシェイクスピアの初めての出会いは、オリヴィア・ハッシーの『ロミオとジュリエット』から始まり、映画を見た興奮ですぐに書店に駆け込み、シェイクスピアを下さいと言って『ロミオとジュリエット』を買うつもりが、田舎の書店に置いてあったのは木下順二訳の『ハムレット』しかなかったというエピソード、そしてイギリスのストラットフォードで初めて見たシェイクスピア劇がジュディ・ディンチとイアン・マッケランの『ロミオとジュリエット』という因縁話の披露をされた。
逍遥を語るにあたっては、倉橋健司会による木下順二の「逍遥」についての講演を、木下順二と逍遥の声色(逍遥の声は実際に聞いたことはないのにさも聞いたことがあるように)を使いながら、逍遥の功績について熱く語られた。
途中に井伏鱒二が登場してきたり、氏の語り口は落語を聞いているような、人を引き付ける魅力にあふれていた。
下館氏は、逍遥の全集を一度に買い求めるのでなく、一冊一冊買い求め、最後の一冊がどうしても手に入らなかったが、名古屋の出張でふと立ち寄った古本屋で、焼跡の訳ありの本として、その最後の本と出会って100円で購入したというエピソードなど、聞いているだけでわくわくした。
下館氏のシェイクスピア劇上演の原点は逍遥にあり、言葉を単に忠実に訳すという、横のものを縦に移すという作業ではなく、「心」を伝えるものでなければならないという、逍遥が氏の心に呼び掛ける声に耳を傾けての結果であることが語られた。
下館氏は、シェイクスピア劇は原文でも当時の方言が多分に入っているものであり、その雰囲気を「心」に伝えるものとして東北弁を使っての翻案に仕立て上げていることを説明された。
私はシェイクスピア・カンパニーの翻案劇を見るのはこれが3本目だが、いつも心に暖かいものを感じたのはそのせいだと思った。「心」が通っているのである。
今回、この早稲田の大隈記念講堂で上演された『破無礼』は、構想から5年がかりで上演にこぎつけたと語られた(初演は2006年。東京公演はその年の9月六行会ホールで行われた)。
当初は奥州仙台藩の伊達騒動にモチーフを用いようとしたが、原作を読むと『ハムレット』は当時でもインターナショナルの作品で、デンマークを舞台としながら、フランス、ノルウェー、ポーランド、ドイツと実に多彩な国々が登場する。そのため時代を変革期の明治初年の戊辰戦争に置き、奥州列藩同盟の背景に舞台設定したという。
シェイクスピア・カンパニーの特徴は、プロの集団ではないので、氏が何より大切にしているのは「舞台より生活を大事にし、無理をしない」ということをモットーに、なによりも団員の生活を最優先にして稽古をし、本公演をやってこられてきたということである。
個人的には、2006年の東京公演の『破無礼』は、たまたま海外出張と重なり見られなかったため、今回はこの上演を楽しみにしていた。
それが期待をはるかに上回って、感激でしばらく声も出ないほどだった。
仙台弁で聞く台詞は標準語の台詞に較べてはるかに心に染み通るものであり、温かみを感じるものであった。そこには生活を感じさせる、生身の人間の身近なものがあった。
仙台弁のすべてが理解できたわけではないが、分からないことでかえって原作に近しいものを感じさせた。
登場人物にも出来る限り原作の音に近づけた名前をつけて、ハムレットは奥州天馬藩の城主の息子、天馬破無礼、オフィーリアは真田依璃亜、クローディアスは天馬鞍有土、ガートルードは天馬雅藤(がとう)というように。
舞台の特徴として印象深かったのはいくつもあるが、語り部としてのホレイショー(この舞台では細谷帆礼)の立ち位置、旅役者は一人だけの登場で、そのため芝居は落語のように語られる演出、破無礼が依璃亜の葬儀の場で依璃亜への思いを言葉で語るのではなく、ただ一声悲嘆の雄叫びを叫ぶ姿で表現した演出、そしてエンディングの演出などが印象に残った。
帆礼が破無礼を藩主の息子としてのふさわしい葬儀を行ってくれるよう、凱旋してきた新政府軍に呼びかけ、舞台は暗転。沈黙の後、舞台奥の中央の黒いカーテンが一間の広さほどに開かれて、そこには天国を思わせる明るい世界が広がり、破無礼の父亡霊が、破無礼を招くようにしてそこに立っている。
倒れ伏していた破無礼がやおら立ち上がる。そこへ依璃亜が寄り添ってきて、二人はその明るい天国の世界へと向かっていくように歩みを進める。
これまでに見たことがない、何とも温かい演出法であった。
この最後の場面を見ただけで、すべての至福を得た気持になった。
脚本・翻訳・演出/下館和巳
6月19日(土)、早稲田大学大隈記念講堂
|