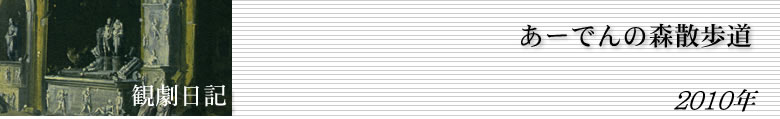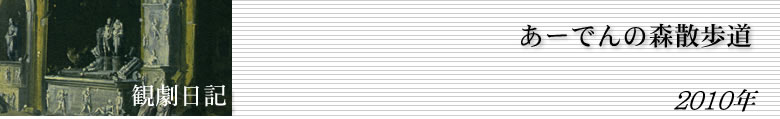|
― 三部作を二部構成に圧縮して一挙上演 ―
さて。何から書くべきか。
一口でいえば、圧倒されて、疲れたとしか言いようがない。
昨年末、新国立劇場で『ヘンリー六世』が三部作通しで上演されて間がないだけに、その比較の意味でも興味が尽きない。そのことはひとまず置いておいて、今回の舞台全体のことから記していこう。
まず座席のことだが、予約のチケットが送られてきた後、座席案内としてお知らせが送られてきて、今回、舞台の構成上、私の席(C列)は舞台上になるということであった。それでステージの上での観劇だと思っていたのだが、実際には通常の観客席との対面形態の座席で、私たちの座席は通常舞台である場所をピットにして、さらに後方には背後の舞台があるという構造であった。私たちの席は通常は舞台であるために、迷路のような仮ごしらえの通路を経由して座席にたどり着くことになる。
休憩時間に普通の観客席から舞台を眺めてみると、額縁を切り開いたような矩形の舞台をはさんで、観客席はすり鉢状にせりあがっているように見える。そして私たちの観客席は舞台の一部のように見え、最後部が城郭の高台となる舞台になっている。
舞台は全体が白一色で、舞台上は何もない空間である。
この純白の舞台は、同じこの劇場での『タイタス・アンドロニカス』の舞台を思い出させるものだった。
開演前では、その純白の舞台上に、大きな、真っ赤な血の跡が、この物語を予兆するように広がっている。
開演は何の合図もなく、始まる。
私たち観客席の通路を通って、シルバーセンターのおばさんたちのような格好をした、白いゴム長靴をはいた掃除婦が五人、掃除道具をもって、舞台上のその血痕をきれいに拭い始める。それもかなり入念に。
プログラムで確認すると、この掃除婦役は、さいたまゴールドシアターの劇団員の人たちということだった。
その清掃中、町の喧騒の音が聞こえ、それがやがて機銃掃射や爆撃音の音に変わっていく。
掃除婦たちは、掃除を終えて舞台上の側面の壁に、その音におびえたように佇み、やがて舞台上から、ドタッ、バタッ、とすさまじい音を立てて、肉塊が落ちてくる。
舞台から物をすさまじく落とす趣向は蜷川演出ではもうおなじみで、それほど驚くまでもないことだが、この垂直落下の動きと、舞台上の人物の水平の動きを交錯させて、物語の展開に変化を持たせている。
掃除婦たちはその肉塊もきれいに掃除して舞台上は平和を取り戻したかのように見えるのも束の間、今度は深紅のバラが上から落ちてくる。
舞台上手(私たちの席からでは下手になる)から、ガラスの柩に入ったヘンリー五世の亡骸が運び出されてくる。
さあ、物語の始まりである。
ここまでの導入の仕方は、ある意味で蜷川演出として常態化しているともいえるものだが、観客を引きつける醍醐味だと思う。様式美が、そこにあると思う。
たとえば、赤薔薇組(ランカスター家)の登場では赤薔薇を降らせ、白薔薇組(ヨーク家)の登場では白薔薇を降らせる。フランスが舞台になると、フランスの象徴である白百合を降らせる。
そのことで人物の相関関係や、状況を理解するのに象徴性を感じさせてくれる。
落ちた薔薇は、場面が変わるたびに掃除婦のおばさんが片付けることで、舞台のアクセントになっている。
新国立劇場の『ヘンリー六世』と異なり、蜷川演出は三部作を二部に圧縮し、途中の休憩時間を除いておよそ7時間にわたる一挙上演である。
午後1時に始まり、途中1時間の大休憩をはさんで、9時半までの上演であった。
前編と後編に分け、それぞれ途中15分間の小休憩を挟んでの長丁場である。
新国立劇場の『ヘンリー六世』も、三部作を一日で一挙上演する日があったが、カットなしなのでもっと長い時間がかかっている。
前篇は、第一部がヘンリー五世の葬儀の場から始まって、トールボットの孤立無援の壮絶な死で終わる。
トールボットの死に当たっては、この劇の始まりと同じように、肉塊が始まりの時のように、ドカドカと落ちてくる。
前篇第二部は、グロースター公爵(瑳川哲朗)が殺され、ヘンリー六世(上川隆也)によってサフォーク(池内博之)が追放され、マーガレット王妃(大竹しのぶ)がサフォークとの別れで悲嘆にくれる場面で終わる。
後編の第一部は、追放されたサフォークが予言通り、水に関連した名前を持つ海賊ウォーター・フィットモアに殺され、フランスでエドワード四世のために縁談を勧めていたウォリック伯が、エドワードの変心でグレイ夫人と結婚したことから恥をかかされ、ランカスター側に味方することになるところで終わる。
三部作を二部作に凝縮しているので当然省略はあるのだが、物語全体の流れの中ではその省略部分にあまり気付かない。もちろん細かく見れば多分に省略に気付くのだが、エッセンスの部分はしっかりと入っているので、それほど気にならない。
ここで当然のように、新国立劇場の鵜山仁演出の『ヘンリー六世』との比較をしてみたくなるというもの。
舞台装置は別にして、まず一番は人物造形。
特にヘンリー六世は対照的とまで言えるほど、その差が特徴的であった。
新国立のヘンリー六世(浦井健治)の衣裳は純白で、自己主張がとことん抑えられた人物として描かれ、清純そのものを感じさせる人物であったのに対し、蜷川演出では、ヘンリーはランカスター家の赤薔薇を象徴して、深紅の衣裳を身にまとっている。そして、時に、その衣裳の色のように激しい台詞を発する時があり、自己主張のある人物を感じさせた。
それぞれに特徴があり、どちらがいいというものでもないが、自分としては浦井健治のヘンリー六世の方が印象的であり、忘れがたいものを残してくれた。
しかしこれは時間がたってみるとまた変わるかもしれない。
蜷川ヘンリーで特筆すべきところは、乙女ジャンヌとマーガレット王妃を大竹しのぶが一人二役で演じる処にあったと思う。これは蜷川幸雄の独創ではなく、割と広くやられているようなのだが、大竹しのぶというキャラクターを通して見る時、鮮烈な印象があって、それだけでも見ごたえのあるものだった。
それぞれの登場人物を逐一比較して、その印象度の優劣をマルバツで勝敗表を付けるというお遊びも一興と思えるほど、どちらも豪華なキャスティングである。
蜷川ヘンリーを見ながら、鵜山ヘンリーのキャストと比較しながら見るという贅沢は、この両者の公演の時間的隔たりが短いだけにできることだった。
とにかく根をつめて見ていたので、見終わった後はその感動の重さに、どっと疲れを感じた。
この日がこの舞台の初日であったが、役者の人たちにとって、これから長丁場の始まりとなる。本当にお疲れ様、と言いたくなる舞台であった。
訳/松岡和子、構成/河合祥一郎、演出/蜷川幸雄、美術/中越司、衣裳/小峰リリー
3月11日(木)、彩の国さいたま芸術劇場・大ホール、
チケット:(S席通し券)19000円、座席:1階C列5番
|