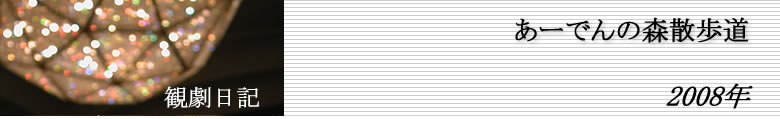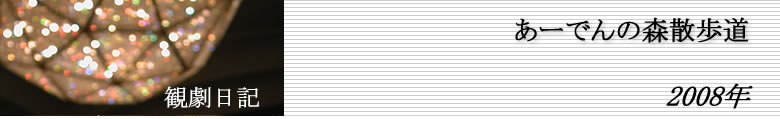|
客電が落ち、舞台は闇の中。
間をおきながら、沈んだ音で閑かな鐘の音・・・・
狐火のようなかがり火を捧げ、静かな足取りで「言霊」が二人一組、下手からと上手から登場。
言霊が、床に置かれた12個のフットボールより少し大きなサイズの雪洞(ぼんぼり)に、そのかがり火の火をおもむろに移していく。雪洞に移されたかがり火の明かりがあたたかく映し出される。
儀式的ともいえる導入で、劇が展開される。
マミリアス(横山道代)が母ハーマイオニ(山賀晴代)に、冬の夜話を始める・・・・
「昔、ある国の王様が外国のお友達の王様を自分の国に招きました」
このたびの『冬物語』は能舞台ではなく、劇場版として普通の舞台。
ヨーロッパツアーの上演用として、英語の字幕付である。
シシリアの背景はグレーで、ボヘミアの背景は茜色のホリゾントと場所で色が変わる。
05年の公演でレオンティーズを演じた谷田歩が今回も同じ役を演じる。
その谷田の演技が深みを帯びてきたように思う。
ハーマイオニがポリクシニィーズ(河内大和)を引き止めるのに説得する場面。
レオンティーズに嫉妬の妄想がわいてくる表情への移り変わりの内面的な心の変化をうまく表出している。
その葛藤がマグマとなって噴出するとき、口を大きく開けた無言の谷田の表情には、憤怒の増長天の凄みがある。
嫉妬の妄想に激情するレオンティーズと、自分の過ちを反省した後のレオンティーズの涸れた声の表情の差が、生きた彫像のハーマイオニとの再会の場面において、見ているものの感情を高揚させ、熱い涙を誘いだす。
前回同様、今回もアンティゴナスと羊飼いを演出の栗田芳宏が演じる。
この人の演技を見ていると、舞台のおいしいところを全部さらっていってしまうようなうまさがあって、見ていて心が浮き立つような気分になるから不思議だ。
役者をやっているときのシェイクスピアもきっとこんなではなかっただろうかと、そんな想像がちらりとよぎる。
今回もアンティゴナスから羊飼いに早や変わり芸を見せてくれ、それを楽しむことができた。
アンティゴナスの夢に現れてお告げをする台詞の場面では、ハーマイオニはマミリアスを伴って実際に舞台に登場して彼に告げる。
羊飼いが赤ん坊のパーディタを抱いて退場した後、舞台に留まっていたマミリアスが、コーラス役の「時」となって16年の歳月を一気に飛び越える説明をしたところで、前半部が終了し15分間の休憩となる。
休憩時間の間に、舞台上ではすでにハーマイオニの彫像が言霊の4体の塑像とともにホリゾントの場所に登場し、後半部の舞台展開の間ずーっと動かずにそこに位置している。
ハーマイオニは深井のような女面の能面をつけていて、彫像は、ちょうど鳥かごをイメージさせるような枠の中に納められている。
その鳥かごは、ハーマイオニが生きた彫像から生身の人間に立ち返るとき、言霊が歌う歌、
「か〜ごめ、かごめ、
籠の中の鳥は、いついつでや〜る」
という歌につられてハーマイオニが動き始めるとき、熱い感動を覚えるとともに、その鳥かごが意味していた象徴性をも感じることができる。
再会の抱擁は終始無言で一言の台詞も発せられない。
その無言で過ぎる時間がまるで時が止まってしまったかのようで、言葉では表わせない感動をじっくりと感じさせてくれる。
今回も前回の演出と同じくオートリカスは登場しない。
そのため羊飼いがパーディタの出生の秘密の証拠をポリクシニィーズに差し出すのを取り次ぐ役を引き受けるのは、オートリカスではなくカミロ(荒井和真)となるが、原作とは異なっていても物語の筋としての説得性が高く、納得できるうまい転換だと思った。
感動的なハーマイオニとレオンティーズ、パーディタとの一族再会の後、物語は再び元に還る。
今度は、マミリアスに変わって、パーディタがハーマイオニに語るのだった。
「昔、ある国の王様が外国のお友達の王様を自分の国に招きました」
舞台はそこで閉じる。
この終わりの場面が始まりに戻るという円環構造の演出は、栗田芳宏のおなじみの手法といえるが、余情豊かな終わりで、終わりというよりは、今までの展開を静かに反芻させられ、再び劇の始まりを予兆させる。
訳/松岡和子、構成・演出/栗田芳宏
8月31日(日)14時開演、池袋・あうるすぽっと、チケット:4000円、座席:D列21番
|