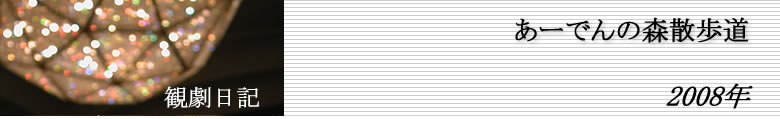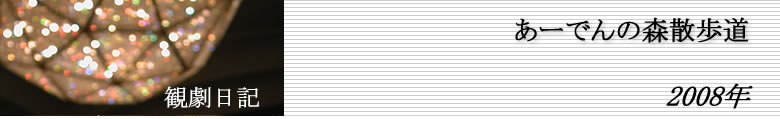|
若い恋人たちの純粋な愛というのは、時代を超えたピュアなものがあると思うのだが、今回の『ロミオとジュリエット』ではそれがまったく感じられなかったように思える。そんなことを考える自分が、彼らとのジェネレーションギャップなのだろうかと自分を疑いたくなった。
キャピュレット家の舞踏会でのロミオとジュリエットの最初の出会い、そしてバルコニーシーンの二人は、最近の若いカップルが電車の中で人目もはばからず抱き合ってキスをしている、そんな印象を受けるラブシーンばかりで、シェイクスピアの台詞の詩情の昂揚感というものが感じられなかった。
舞踏会の場面では、ロミオがジュリエットを見初める決定的瞬間があいまいで、二人の出会いの場は、彼らだけの時間となり、回りの人物の時間は静止して二人以外の動きは止まった演出となっている。
ロミオとジュリエットの「巡礼の手」のふれあいはなく、唇のふれあいばかりのような印象。
せっかくまわりの時間を静止させているのだから、ここは二人の台詞の詩情を出して欲しいものだ。
もっとも時代設定を1920年代にしていて、舞踏会の踊りもチャールストンのようなドタバタで、詩情的雰囲気など求めるべくもなかったのだが・・・・
バルコニーシーンではアップステージのセッティングがなく、テーブルや寝台として使用される台があるだけで、ジュリエットとロミオの二人の位置の距離がまったくない、平面的で、立体感のない舞台となっている。
二人の垂直的距離感があってこそ恋の焦燥感と詩的昂揚が伝わってくると思うのだが、ここでは二人はいとも簡単に口付けを交し合い、べたべたしあうだけで、またしても二人の台詞は塞がれてしまう。
このバルコニーシーンならぬキスシーンには少々うんざり。
ロミオが最後にジュリエットの横で毒をあおって死ぬ場面では、ロミオがその毒を飲んでまさに死ぬその瞬間にジュリエットが仮死状態から目覚めるという演出の工夫をしている。
ジュリエットが身を起こし、ロミオが入れ替わりに横たわるのだが、この決定的瞬間のふたりの状態がなんとも間が抜けた演技にしか見えず、そのためにむしろ滑稽な感じがした。
時代設定を1920年代に置いたからというわけでもないだろうが、ロミオがティボルトを殺すのにピストルを使っていて、全体の台詞と場面状況が合わない、ちぐはぐな所があったのも気になった。
また、修道士ロレンスが早朝薬草を摘んでいる場面の台詞では、ロレンスは薬草を摘むではなく、演説をしているかのような台詞まわしにも違和感があった。
全体的に詩的余情に欠けている。
一つ個人的に印象に残ったのは、昨年の『夏の夜の夢』で、ピーター・クインスとイージアス役を演じたショーン・パッセイが再来日して、今回キャピュレット役を好演したことだった。
全体の構造としては、キャピュレット家のメイドがプロローグの序詞役を務めるという斬新な設定で、この劇全体の流れを(キャピュレット家の)内側から見つめるような設定になっていて、最後の「許すべきは許し、罰すべきは罰するとしよう。世に数ある物語のなかで、ひときわあわれを呼ぶもの、それこそこのロミオとジュリエットの恋物語だ」(小田島雄志訳)、という大公の台詞も、この序詞役によって語られて幕を閉じることになる。
この最後の場面で、キャピュレット家とモンタギュー家の両家の和解がなされないままに終わらせる演出家の意図が気になるところ。
今回のOUDSの公演は、残念ながら少し不満の残るものだった。
ピアーズ・バークレー演出
8月10日(日)13時開演、東京芸術劇場・小ホール、料金:2200円(団体割引)、全席自由
|