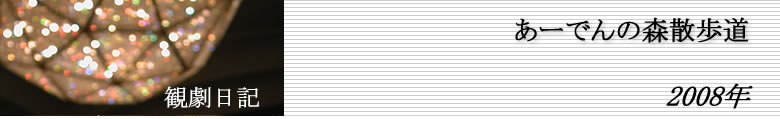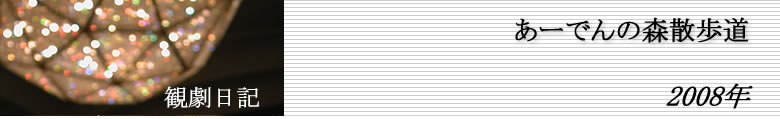|
― 平幹の演技を超えた台詞力に酔いしれる ―
台詞の力というものをまざまざと感じさせる舞台であった。
二度、泣かされた。
その台詞の力は演技を超えたもの、としか言いようがなかった。
その涙の第一は、リア王(平幹二朗)がドーヴァーで救出され、永い眠りの後目覚めて、コーデリア(内山理名)と再会する場面。
「お前の姉たちは、私にひどい仕打ちをした。お前にはそうする理由がある。あいつらにはない」というリアのせりふに、コーデリアは、「理由などありません」と答える、その場面である。
二人とも無垢の白い衣裳を身につけていて、リアとコーデリアは無言で額と額を寄せ合う。そのとき、じわ~んとした悲哀の涙が染み出てきて、抑えようがなくなったのだった。
そして、いま一つは、コーデリアの死の場面。
リアが死んだコーデリアを抱いて、「吼えろ、吼えろ、吼えろ!」登場してくる場面ではなく、リアがコーデリアの死を受け入れざるを得ないと諦念したときに発する、「コーデリア」という悲痛な一言・・・・涙が押し寄せてきて胸がつかえてならない。
どんなせりふ、演技も、この平幹二朗が演じるこのリアのひとことに及ぶ悲痛さはない。
「コーデリア」という平幹二朗の絞るような声を聞いて、声の出ない慟哭に咽んでしまう。
いつものことながら、蜷川幸雄の舞台を見るときには、舞台装置と最初の導入部について、いつも緊張して見入るのだけれど、今回、平幹二朗の『リア王』を見終わって深い感動を味わった後では、それをなぞるのは無為なことに思わないでもない。
しかし、この「観劇日記」が僕の記憶の心覚えのため、ということに端を発している以上、書き留めるべきことは書き残しておきたいと思う。
舞台は緞帳の代わりに、くすんだ平板が組み合わさって大きな一枚の幕板となっている。その幕板の前には、所どころに土饅頭の山が築かれている。
銅鑼のような音を合図に、深々とした毛皮のような衣裳をまとった貴族たちが上手、下手からぞくぞくと登場してくる。
ケント伯(瑳川哲朗)とグロスター伯(吉田鋼太郎)は、客席通路から話を交わしながら舞台の方へと進んでくる。グロスターの庶子エドマンド(池内博之)は舞台上の貴族たちの中に混じっている。
幕板が左右にスライドして開かれると、リア王が娘たちに囲まれて、奥舞台の玉座に座している。
リア王の姿は、初めはまわりの貴族たちにふさがれて見ることができない。
奥舞台は、後方が狭まった台形の形状をしていて、ホリゾントは能舞台の鏡板のように、一面に大きく松の木が描かれている。
両脇には、大きな素焼きの甕に植えられた紅梅と白梅が据えられている。
時代と場所は古代ブリテン王国でありながら、イメージとしてはすでに日本的な雰囲気の親近感をかもし出している。
手法的にはシェイクスピアを日本的なものに置き換えるという、蜷川幸雄の他のシェイクスピア劇に通じるものである。
蜷川幸雄の演出で感じるのは、テクストに忠実である、ということ。
演出の都合上せりふのカットはあっても、せりふの過剰な解釈の場面を作らない。そのことを今回一番感じたのは、道化の退場についてだった。
コーデリアが絞殺されてリア王が、「可哀相に、俺の阿呆めが絞め殺された!」と嘆く場面を先取りして、実際に舞台上で道化が首を括って死んでいる場面を演出することがあるが、蜷川幸雄はその方法を取らない。道化の退場は嵐の場面以後突然消えてしまう、それだけである。
しかし、今回平幹二朗のリア王が「俺の阿呆めが絞め殺された」というせりふを発したとき、道化が首を括って死んでいる演出を目にしたことがある僕にとっては、その情景がまざまざと浮かび上がってくるのだった。むしろそれを表出しないことでそのことを強く感じさせる、と言える。
その道化役であるが、僕にとっては初めての役者、山崎一がそれを演じている。彼の道化を一言で評すれば、平幹二朗のリア王との真剣勝負のような凄みを感じさせ、しかも道化としての「軽み」、軽快さを失っていないといえる。それは狂言回しのような軽みで、実際狂言回しの演技をするのだが、これまで見てきた道化とはまた一味違うものを感じた。
舞台が鏡板のある能舞台のような装置であるといわけでもないだろうが、エドガー(高橋洋)と両目を抉られたグロスター伯のドーヴァーへの道行場面は、笙の音が響いて能舞台の雰囲気をもたせている。
舞台の動きは水平的であるが、荒野の嵐の場面では、1999年のナイジェル・ホーソン主演で同じく、この彩の国さいたま芸術劇場で演出したものと同じ手法をとっている。
天空から、石を降らせる。水平的な動きが続く中で、この垂直的な落下は思考を寸断する効果をもっていると思う。しかし、その石の落とし方は、途切れ途切れで、しかもいつまでも続く。
今回が初舞台である内山理名のコーデリア、ベテランの銀粉蝶のゴネリル、円熟を感じさせるとよた真帆のリーガンの女性陣にもその特色を十分感じさせてくれた。
途中休憩20分を挟んで3時間40分を超える舞台であったが、終わってみれば瞬時のよう。
これまでに平幹二朗のリア王は「幹の会」公演で二度見ているが、あらためて彼のせりふの力を感じさせられた舞台であった。
訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄、美術/中越司、
1月20日(日)13時開演、彩の国さいたま芸術劇場・大ホール
チケット:(S席)10000円、座席:1階E列4番
|