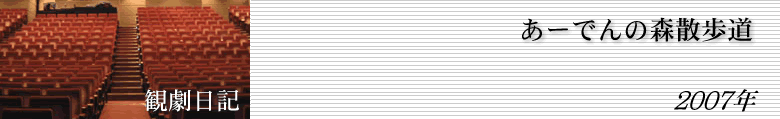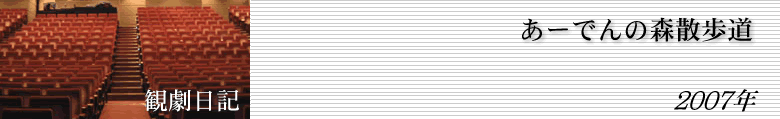|
~ 同性愛者アントーニオの寂寥 ~
先行予約でなく一般前売りの初日で、すでにS席は全ステージ満席。やむなく平日のマチネのA席を確保。
座席は3階席の舞台中央よりやや下手寄り、最後列のC列9番。
舞台は、自分の席からは、ちょうどギリシアの円形劇場を半分に割ったような形で、すり鉢の底をはるか下に見下ろす形である。裸眼ではとても、人物の表情は見えないのでオペラグラスが手放せない。
ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)のアソーシエイト・デイレクター、グレゴリー・ドーランを演出に迎えてのこの公演は、「天王洲銀河劇場」オープン1周年を記念しての企画。
この劇場は昨年3月までは、「天王洲アイル・アートスフィア」という名前で、14年間にわたってさまざまな舞台芸術の公演を行ってきたが、モスクワのユーゴザパード劇場の『マクベス』がその最後の公演となって、自分はそのとき以来はじめてこの劇場に足を運ぶことになった。
グレゴリー・ドーラン演出の舞台を見るのはこれで4回目となる。近くではまだ、その衝撃的な演出の記憶が残っている05年の『夏の夜の夢』、そして04年の『オセロー』、00年の『マクベス』の来日公演を見ている。
これまではRSCの来日公演であったが、今回の公演は、ドーランの演出によって日本人の俳優が日本語(河合祥一郎訳)で演じる。超人気俳優ともいうべき藤原竜也(チケットの入手が困難であった大きな理由の一つ)、ほかに市村正親、寺島しのぶなどの人気俳優、実力派の西岡德馬など豪勢なメンバーが出演。
ドーランの演出では、『夏の夜の夢』でも感じたが、オープニングが実にうまいと思う。つまり観客をうまく引き込んでいく手法が巧みで、「おやっ?!」と思わせながら観客を舞台に集中させていく。
海港都市ヴェニスの賑わい、喧騒をカーニバルで表出し、前半部はこのカーニバルの祭りの雰囲気が支配する。オープニングでは、このカーニバルでアントーニオ(西岡德馬)とサレーリオ(廣田高志)、ソラーニオ(鈴村近雄)が女装していて、そのカーニバルの喧騒が静まったところでアントーニオがガウンに着替えて女装を解く。
ヴェニスの街中と思っていたところが、アントーニオが部屋着であるガウンに着替えることで、そこがどうやらアントーニオの部屋の中だと分かる。アントーニオの台詞の第一声、「どうしてこんなに憂鬱なんだろう」というのがカーニバルの喧騒と対照的なだけにインパクトがある。
そこへバサーニオ(藤原竜也)がロレンゾー(横田栄司)とグラシアーノ(小林正寛)を共にしてやってくる。
アントーニオの「世の中は誰もが自分の役を演じる舞台だ」という言葉を受けて、グラシアーノは「俺は道化役がいい」というが、その台詞を準備するかのように、グラシアーノの衣裳はパッチワーク模様の道化風衣裳。
バサーニオはアントーニオと二人きりで早く話をしたいのだが、グラシアーノがとめどもなくおしゃべりしているので、少しいらいらしている。その様子が、椅子をつかんでいる手の指先を小刻みに震わせていることでよく表されている。そのような細かい仕草がバサーニオの気持をよく表現していて、うまいと思った。
自身がゲイであることを公言してはばからないドーランは、シェイクスピアがアントーニオとバサーニオの関係を「若い男に心奪われた同性愛者」として描いているという事実に目を向けた演出を考えたという。
アントーニオの憂鬱の原因が、女性への恋や、全財産を注ぎ込んでいる航海中の積荷の心配としか考えないソラーニオやサレーリオには、彼がゲイであることを多分知ってはいない。
自分の財産を放蕩で全部使い果たしただけでなく、アントーニオからもこれまでにも相当に借財しているバサーニオに対して、アントーニオは彼の要求に寛大に応える。それは単なる友情というものを超えた、特別な感情からであることが二人の関係から感じられる。バサーニオを演じる藤原竜也にはそれを感じさせる色気がある。
アントーニオがバサーニオを恨むことなく、シャイロックの手にかかって死ぬことも従容として受け入れるのは、バサーニオへの愛の自己充足でもある。むしろバサーニオのために死ねることを喜びとしている。アントーニオはそのとき憂鬱ではない。
アントーニオの憂鬱は、指輪騒動も無事解決し、彼の積荷を積んだ船が皆無事に戻ってきた喜びの知らせと、一同が円満な大円団を迎えたとき蘇る。それぞれのカップルがそれぞれの幸せに浸る。
グラシアーノとネリッサ(佐藤仁美)は早々と新床へと急いで引き込むが、バサーニオとポーシャの二人は、舞台中央の奥で沈黙のまま向かい合って見つめあい、それがシルエットとなって溶暗していく。
アントーニオはその二人を、というよりバサーニオを淋しく見つめて、自身の孤独を感じる。そのアントーニオの苦味を演じる西岡德馬が渋い。
この最後の場面では、もう一つの朗報である(はずの)ロレンゾーとジェシカ(京野ことみ)に、シャイロックの遺産相続の知らせがなされるのだが、ジェシカはその知らせの手紙を胸に、喜ぶというより、複雑な気持を秘めて舞台下手へと逃げるようにして退出する。
この、最後のアントーニオの寂寥感の姿と、ジェシカの複雑な哀しみの表情というのは、最近の演出の常套的なものに思われる。
先を急いで舞台の終わりを語ってしまったが、『ヴェニスの商人』には周知のように、3つの山場がある。
一つは「箱選び」であり、一番高い山がいわゆる「人肉裁判」で、最後が「指輪騒動」である。
そのつなぎのようにして、道化のランスロット・ゴボーの挿入的な場面がある。
それぞれの場面が、それぞれの面白さを味あわせてくれる。
市村正親が演じる、(人種)差別と偏見の象徴でもあるユダヤ人シャイロックは、思ったより大きく感じなかった。そこに当初は不満を感じたのだが、プログラム(1部1500円とちょっと高い)にある市村正親のメッセージを読むと、「僕は、シャイロックは、非常に小さな人間だと思う。小さな人間が抵抗を試みるんです。大きな人間だったら、お金を返してもらって済むと思う」とある。
『ヴェニスの商人』といえば、シャイロックというほど、この人物の存在感が大きいと思っているだけに、 ドラマの進行中は、市村正親のシャイロックに物足りなさを感じていたのだが、演技者のそれなりの読み込みというものに考えさせられるものがあった。
そんなわけで、今回のシャイロックには、僕は特別な発見がなかっただけでなく、シャイロックにそれほど強い印象を感じなかった。
ポーシャ(寺島しのぶ)の存在は、思えば『ヴェニスの商人』のすべての場面で中心的人物を演じている。
シェイクスピアの原作を読んでいると、このポーシャ、必ずしも好人物という感じがしない。ある意味では一番偏見の目を持っている人物という気がする。どちらかというとマイナスイオンに満ちている。
まず、「箱選び」の場面であるが、彼女の求婚者に対する人物判定は言うまでもなく偏見の目で評されている。
有名な「人肉裁判」の場面では、シャイロックに対して、彼をその名前で呼ぶことはなく、常に、「ユダヤ人」と呼びかけている。いわく、
「では、ユダヤ人が慈悲を施さねばならぬ」、
「ゆえに、ユダヤ人よ、おまえは正義を求めるが、考えてもみよ、・・・」、
「ゆえに法に従って、このユダヤ人は、その商人の心臓に最も近いところから切り取られた肉1ポンドの所有権を有することになる」、などなど。
ポーシャは一度だけシャイロックをその名で呼ぶ。
「シャイロック、この3倍の金が差し出されているのだぞ」と。
人を、その名で呼ばないということは、その人格を認めていないことであり、つまりは偏見の目で見ていることである。ポーシャの名判官ぶりの半面にこんなことを感じる。
「指輪騒動」も決してフェアな行いとは言えない。人を試すのは卑しい行為だと思う。だから好きになれない。
このように見てくると、ポーシャというのは実にいやな人間に見える。
ところが、である。寺島しのぶが演じるポーシャは、そんないやみな人間には見えない。
その理由も、プログラムにある彼女のメッセージを読むと、その辺のところがなんとなくわかる。
寺島しのぶもこの作品には共感できていなかったのだった。彼女の言葉を引用すると、
「実は私にとって『ヴェニスの商人』という作品には、矛盾が多くて納得できない、どうしても楽しみきれない作品、という印象がこれまでずっとありました」、「実はポーシャ像はまだはっきりとつかみ切れてはいません。彼女の浮世離れした人ならではの怖いもの知らずな感覚は、身に覚えのあることで理解はできるのです」。
彼女の分からないという感覚の自然体の演技が、ポーシャのいやみな部分を逆に愛らしいものに変えている。
少し変わったところでは、ラーンスロット・ゴボー(大川浩樹)が登場する場面で、彼の父親が登場しない。
これまで見てきた舞台では初めての経験である。ドーランに何か特別な意図があったのかどうか。
ラーンスロットが現在の主人であるシャロックのところから逃れて、バサーニオに仕えようかと思案する場面であるが、良心と悪魔が葛藤するのを二つの仮面(天使の表情をした顔の仮面と鬼の仮面)をつけることで表象している。
また、ラーンスロットはせむしの姿態を強調することでで、差別と偏見を表象している。
ホリゾントが海面の表情をしたり、ベルモンテの光洋とした原野の風景のようであったり、また星の輝く夜空に変じたりする舞台美術は、RSCほかイギリス国内外数多くの舞台美術、衣裳を手がけるマイケル・ヴェイル。
衣裳は、小峰リリー。バサーニオのようにとても現代風な服装であったり(藤原竜也がかっこよく着こなしている)、ウイッグをつけて17、8世紀風の服装をしていたり、時代の統一性はないが不思議と不自然さがないのは、前半部のカーニバルの雰囲気のせいだろうか。
座席の位置の関係で、あまりよく見えないだろうからと期待度は小さかったのだが、無理をしてでもチケットを確保しただけのことはあったのは救いであった。
上演時間は、途中15分間の休憩を入れて、3時間15分。
訳/河合祥一郎、演出/グレゴリー・ドーラン
8月23日(木)13時30分開演、天王洲銀河劇場、チケット:(A席)8400円、座席:3階C列9番 |
|