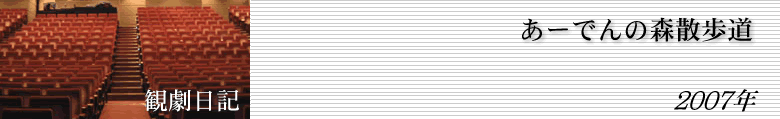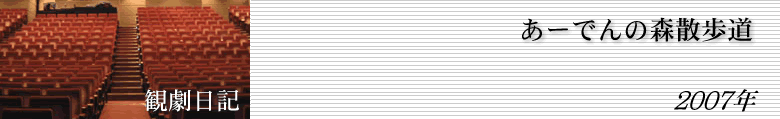|
― 森を自由に出入りできるのはアテネの職人たちだけ ―
オックスフォード大学演劇協会(OUDS)の東京芸術劇場での来日公演が今年で3年連続となり、昨年に続いて今年も皇太子殿下が日曜日のマチネ公演をご観覧された。
シェイクスピアの『夏の夜の夢』は毎年見るのにこと欠かないのだが、今年もITCL(International Theatre Company London)公演などの出色の舞台に出会うことができたが、このOUDSの公演にはまた違った期待感があった。全体の感想からいえばその期待感を満たしてくれるものであったといえる。
舞台はいつも通りシンプルな装置。ホリゾントは黒一色。宮廷を表象する白い円柱が5本。
舞台上手寄りに、直径が一間ほどの円盤状の開帳場(八百屋)。その開帳場はオセロゲームのように黒白が交互に碁盤の目になっている。このオセロゲームの開帳場はシンボリックである。すなわち、一瞬で白黒が入れ替わるということで、『夏の夜の夢』の展開を表象的に明示する。
開帳場の上に真っ白な椅子が2脚置かれている(シンボリックな意味を期待したが、それは単に即物的な道具でしかなかった。つまりただ腰掛けるためのものでしかなかったのは肩透かしを食ったよう)。
舞台中央の前方に白くて細い長四角の枠(ちょうどホッチキスのタマのような感じ)が直立している(これはあとでゲートボールのゲートであることが判明)。
シーシュースとヒポリタが下手より登場。腰の折れ曲がった姿をした老僕のフイロストレイトが後ろに控えている。シーシュースとヒポリタは無言のままでゲートボールに興じる。ヒポリタはゲートにタマを入れることに成功するが、シーシュースは外してしまう。
四日後に結婚式を控えたヒポリタの表情には明るさがなく、憂い顔である。この遊びは、剣で征服されたが、心はまだ閉ざしたままのヒポリタを懐柔しようとするものであろうか。ちょっと意味不明。
さて、パンフレットの「演出家ノート」を参照すると、この舞台の時代設定を1950年代とし、妖精たちの棲む森は「異界」としてではなく、現実世界の宮廷の延長として相互通行可能な世界とし、その橋渡しをしているのが、アテネの職人達(ただし、この演出ではアテネではなく、スコットランドの職人達となっている)である。
これは僕にとって新しい発見であったが、アテネの町と森を自由に往来しているのはこの職人達だけである。
ライサンダーをはじめとした四人の若者たちは、いったん森に足を踏み入れた後は眠りから覚めるまで森から抜け出ることが出来ない。ところが職人達は、芝居の稽古で森を自由に出入りしている。
演出家はそのことを、「彼らは社会化されているけれども、わざとらしく洗練されてはいない。シェイクスピアは職人達のような生きる生き方を擁護しているように思われ、これこそ私たち皆が憧れる何かなのである・・・・」と記している。それは一口で表せば、彼ら職人達は「自由人」であるということであろう。
森に入った若者たちは、立場が逆転する。オセロゲームのように一瞬で白黒がひっくり返るのである。
「女は愛を求められるもので、求めることはできない」と言うヘレナが逃げるデイミートリアスを追い回す。追いかけるのは女で、逃げるのは男。そして魔法の媚薬の仕業で二人の男に追いかけられることになるヘレナ。
それまで二人の男性から愛されていたハーミアは逆に疎んじられてしまう。
白黒の碁盤の目をもつ円形の開帳場が燦然と象徴的な輝きを示す、オセロゲーム。
森の中では、女性であるハーミアとヘレナが積極的となり、二人がやりあう前では、男たち二人は傍観者となって佇むだけとなる。男と女の立場の逆転。
この演出のもう一つの見所はキャストのダブリングにある。
僕はこのダブリングのことを知ったとき、シーシュースとオーベロン、ヒポリタとタイテーニアのダブリングはピーター・ブルック以来の常道なので、それ以外に期待したのは、パックの扱い。
今回、このOUDSの公演にそなえて久しぶりに原文の読み返しをしていて、冒頭の部分は声を出して読んでみたのだが、シーシュースがフイロストレイトに命じるところで、
'Go, Philostrate,
Stir up the Athenian youth to merriments,'
という台詞はオーベロンがパックに命令するときの語調そっくりであることに気がついた。
嬉しいことには、その予想が見事に的中した。反っ歯で腰の折れ曲がった姿のフイロストレイトがパックと同一の俳優であるというのは、意識をしていない限り気がつかないほどの見事な変身。
そのパックを演じるレオ‐マーカス・ワンはOUDSのCuppers Competitionでベスト・アクターに選ばれただけのことはある。パックの衣裳の上半身は紗のショールのようなものだけで、唐草模様のタトウ―が胸の辺りに描かれている。
ボトムと、イージアスをも演じるクインスを除いた他の職人達は、妖精達を演じるが、彼らは上半身裸で、やはり体に唐草のタトウ―が描かれている。その体に描かれた唐草模様が、全体として森を表象しているように見える。
マッチョな妖精達というのも意表をつく。
そのマッチョな妖精を従えているのが、妖精の女王タイテーニア。こちらは剣で征服された憂い顔のヒポリタと異なり、野生的で大胆な魅力で、妖精の王オーベロンと堂々と張り合う。
この演出家は意表をつくのが好きなようで、職人達の劇中劇を演じさせるのに、およそちぐはぐなことをやってのけさせる。シスビーを演じるふいごなおしのフルートはマッチョで、声色もごついままで女役を押し通す。
壁を演じる鋳掛け屋のスナウトはゲイで、観客である僕らに、彼がシスビーを演じるのだろうと思い込ませるような所作をする。うまい。実にうまい。
劇中劇の終わりに踊るバーゴマスクでは、踊りの最後で全員スカートの尻をめくり、パンツを見せる。そのパンツは、青地に白のX形十字旗。
この職人達はみなそれぞれ個性豊かな演技で、個々の演技のレベルは相当に高い印象を受けた。
ハーミアを演じたシャーロット・コックスは昨年、『恋の骨折り損』のフランス王女の役で来日しており、Cupper's Best Actressを受賞している。
上演時間は途中20分の休憩を挟んで、2時間15分。
終演後、劇場2階のカフェ&レストラン「コンチェルト」で、関場先生主宰の"シェイクスピアの森グループ"の観劇交流会で感想を談じ合う楽しいひと時を過ごし、劇を二度楽しむことができた。
演出/サラ・ブランスウエイト
8月12日(日)13時開演、東京芸術劇場・小ホール2、チケット:2200円(団体割引)
|