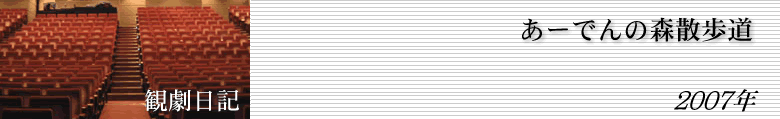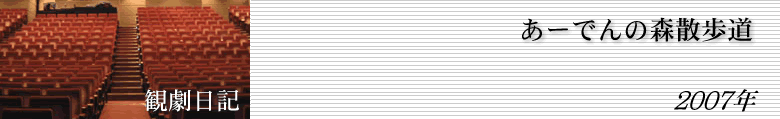|
コリオレイナスというローマの武人のことを考える。
彼は武将というより、やはり武人でしかないようである。全体が見えず、局部的な対処しかできない。必要なときに策略を考えることもできなければ、沈着にもなれない。それに比較すれば、戦争ではコリオレイナスに常に負け続けているオーフイデイアスのほうが策略家である。
執政官となる推薦を受けながらローマの市民の反感を買ってそれを取り消されようとするとき、彼の母親ヴォラムニアは、「戦争のときに、最善の目的のためとあらば、策略をもちいて本来の自分ではない姿を見せてもかえって名誉となるものなら、平和なときにも、策略が名誉と手をつないでなぜいけないのです?」と、彼を説得する。
しかし、コリオレイナスは戦争のときにも策略など用いることの出来ないただの武人でしかなかった。
ヴォルサイを攻めたとき単身でその城壁内に乗り込んでしまうことは、武将がなすべきことではなく、ただ無謀な振る舞いでしかない。コリオレイナスは母親の鋳型に嵌められて育ったそれだけの人物であって、それ以上でもそれ以下でもない。
母親にあって彼に欠けているものは武将として必要な「策略」のこころ。ヴォラムニアであれば、まず「権力」をつけることから始めるであろう。ヴォラムニアは言う。「私はまずおまえに権力を身につけてほしかったのです」と。
コリオレイナスにとっては父とも言える親友メニーニアスの、「この世に生きるにはあまりにも高潔すぎるのだ」という言葉は彼には過ぎたる評価である。高潔というより、ただ傲慢で視野が狭いだけでしかない。
コリオレイナスの人物を思い描くとき、彼は常に母親にほめてもらいたいと思っており、それだけが彼の行動の指針となっているのが見える。
刈り込んだ頭髪に、大きな三日月形の傷跡を残して武人の姿を強く印象付ける唐沢寿明の演じるコリオレイナスを見て、そのことをあらためて思い描いた。
コリオレイナスの人物像に対比して、蜷川幸雄が描き出す『コリオレイナス』は、一段とそのスケールが広がる。
貴族たちやコリオレイナスに造反する民衆を描き出すのに、舞台全体を鏡にして観客を群集として映し出す。
開演となって、舞台の照明は普通とは逆に、観客席に当てられる。暗い舞台の幕が開くと、それが一面の鏡となって観客席全体が大きく映し出される、そして民衆の喧騒とともに、舞台に照明が入り、鏡の向こうが透明になって舞台全貌が見えてくる。舞台は、階段となっていて、その最上段には仏像の四天王像が屹立している。そして舞台の奥は襖絵となっていて、それがすばやくスライドされて場面の転換を鮮やかにさせる。
階段という垂直な構造でヒエラルキーを暗示し、また舞台空間の動きを激しくさせ、襖絵のすばやい転換が水平的な時間軸のスピード感を感じさせる。舞台美術と照明は、いつもの中越司と原田保。
ローマの貴族、武将は薄墨色の、直垂のような衣装。それに対するヴォルサイの側の衣装は白一色。このコントラストが凄い。衣装は小峰リリー。
聴くシェイクスピアを見るシェイクスピアへと視覚化させる蜷川幸雄の手腕にあらためて見入った舞台であった。
ただ、最後のコリオレイナスとオーフイデイアスの二人の戦いで、オーフイデイアスがコリオレイナスの頚動脈を切って血しぶきを上げさせる場面は劇画調に過ぎた、というかサービス過剰の演出であったと思う。
衣装や舞台美術全体を含めて、ローマというよりアジア的な雰囲気を持つ舞台であったが、コリオレイナスの最後の場面などは、襖絵に浮かぶ般若心経の読経がコーランのように響いて無国籍的な哀調を感じさせた。
コリオレイナスの唐沢寿明、ヴォラムニアの白石加代子、オーフイデアスの勝村政信、メニーニアスの吉田鋼太郎、護民官シシニアスの嵯川哲朗など、豪華な顔ぶれも蜷川幸雄の舞台ならではであった。
*上演は松岡和子訳だが、本文中の引用は小田島雄志訳を使用した。
訳/松岡和子、演出/蜷川幸雄
2月4日(日)13時開演、彩の国さいたま芸術劇場・大ホール
チケット:(S席)9000円、座席:1階S列224番
|