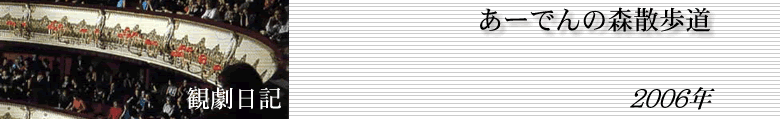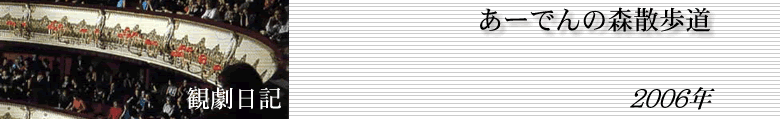プロに劣らぬ非常にレベルの高い演技、演出であったと感心する。
途中20分の休憩を挟んで約2時間40分の上演時間で、台詞も演出上の工夫のためと思われる一部を除いてほとんど省略なしであった。
冒頭のシーンから感じたのは、当たり前のことだが、シェイクスピア劇が「観る」劇である前に「聴く」劇であるというのを強く印象付けられた。それは何よりも彼らの台詞力が優れていることを示していることにほかならない。
19世紀の批評家ハズリットという人が、「もし万一シェイクスピアの喜劇の中でどれかを捨てなければならない破目になったら、この劇を選ぶだろう」と批評しているが、確かに読んでいるときに感じたのはそのことである。その不満は、中心となる核がないこと、登場人物も主人公が複数であり、ストーリーとしてもこれといって山場がないことから生じてくるように思われる。
ところが、OUDSの今回の上演を観てこの劇の面白さを思い直された。シェイクスピアの初期の作品、なかでも喜劇においては「言葉遊び」が多く目に付くが、なかでもこの『恋の骨折り損』は言葉遊びそのものが主人公のような働きをしている。残念ながらそれを全部聞き取るほどの英語力はないのだが、感じることだけはできた。
演出上の工夫でまず面白いと感じたのは、誰しも感じたであろうスペインの騎士アーマードーとその小姓モスの対称。これは僕の勝手な想像であるが、アーマードーはフォルスタッフのような人物のように思い描いていた。
小姓は'boy'と呼ばれるが、必ずしも「少年」ではなく若い召使に対して使われるものであるが、アーマードーの台詞からすればアーマードーより背が低い。ところがこのOUDSの演出では、アーマードーは登場人物の中でも一番背が低く、小姓のモスは反対にアーマードーを見下ろすぐらい背が高い。背を高く見せようと踵の高い靴を履き、威風を示そうとカイゼル髭をはやしてその存在を誇示する姿が愛嬌のあるユーモアを感じさせる。そしてそのスペイン訛りのアクセントがいっそう近しい存在に近づける。
登場人物のユニークさと英語の面白さでは、まずこのアーマードーが筆頭に上げられるだろうが、ナヴァール王に仕える貴族ビローン、そしてやたらとラテン語を振りかざす教師ホロファニーズの演技と台詞も大いに楽しませてくれる。ビローンの台詞の面白さは、一種のデベイトの面白さで、ああ言えばこう言うの類のその才気煥発の面白さである。一方ホロファニーズの方は、衒学的でスノビズムな皮肉屋の面白さを出していた。
一方で違和感を感じたのは、コスタード。これは「田舎者」として登場する道化であるが、ここでは縦縞のダークスーツでダンデイな若者として登場する。
逆説的にとらえれば田舎者が猿真似をしていることを表しているとも取れるが、劇全体の構造から言えば歪みも出ているように思える。たとえば、彼が釈放されるときあわてたために足を骨折するが、その際におけるアーマードーやモスとの一連の言葉遊びによる掛け合いの台詞の省略がそれである。
登場人物でうかつにも気がつかなかったのが、警吏ダルとフラン王女に仕える貴族ボイエットの二役。同じ人物が演じているというのに気がつかなかったのは、ダルをどちらかというと無口で、ボイエットは軽口をたたくという演技上の違いもあったせいかもしれない。
演出上のコンセプトとしてサゴスキーの「演出家ノート」の言葉を借りれば、この劇は「戦時下」にある設定となっているが、少なくとも今回のこの上演においてはそのような雰囲気は感じられなかった。
戦時下の設定という点ではケネス・ブラナー演出・主演の映画『恋の骨折り損』を思い出すが、映画の場合は台詞になくても映像でその工夫がなされるが、舞台では舞台装置でそれを表示するか台詞でそれを表現するかをしなければそのことを表出するのは無理だろう。しかしながら、そのようなコンセプトに関係なく、この演出は全体としてよくできていたと思う。
舞台装置は簡素ではあるが表意的なものであった。中央と左右に枠だけの戸口、そしてその戸口をつなぐ格子作りの壁は白一色で、南国的であるとともに異国風な雰囲気がよく出ていた。
この劇は喜劇といいながら、最後は結婚で終わるハッピーエンドではない。フランス王女一行を楽しませる「九人の英雄伝」の余興もたけなわのところで、フランスより使者マーケードがフランス王の死を伝えにやってくる。
ついでながらこのマーケードの役を皮肉屋なイメージを出していたホロファニーズ役の役者が演じていて、それもちょっとした余興に感じた。
ナヴァール王以下4人の若者たちはそれぞれの相手から1年間、結婚のお預けと誓いの行為を約束させられる。演出的にも、この最後の場面では照明が暗くなり、重苦しい雰囲気を伝える。
この劇の構造を螺旋的に円環状にとらえるならば、このドラマははじめに戻って3年間の学問のための禁欲生活の誓いに移すことができる。つまり、彼らはその約束を守れるはずがないというオチがつく。
このドラマは中身が問題ではなく、デベイトそのものに意味がある劇といえる。誓いを立てる口実についても、また誓いを破ったときにそれを言い訳することも、いかに相手を言葉の上で説得するか、言い負かすか。そこの言葉のやり取りを楽しむ劇であろう。
演出/キャサリン・サゴスキー
8月12日(土)13時開演、東京芸術劇場・小ホール2、チケット:2200円、座席:全席自由 |