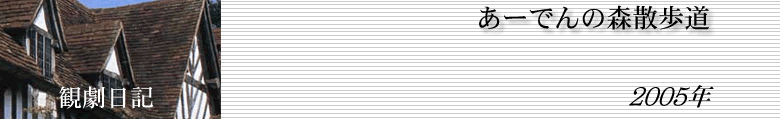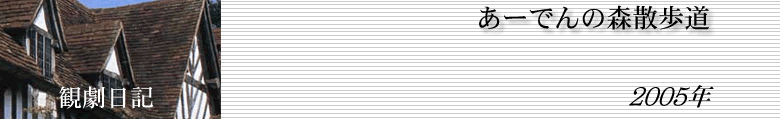非常に緻密に計算された演出である。
舞台下手前方の上方に、直径が1メートルもあろうかと思われる赤い月が浮かんでいるのが開演前からまず眼に入る。
『夏の夜の夢』は、4日間の出来事ということになっている。
冒頭のシーシアス公爵の台詞、
‘our nuptial hour/ Draws on apace; four happy days bring in/ Another moon’
から始まって、公爵とヒポリタの結婚、そしてアテネの若者たち二組のカップルの結婚式の夜に催される、アテネの職人たちの劇中劇で幕を閉じることから計算される。
その赤い月が、場面が変わっていくごとに、月の色を変えながら、少しずつ上手の方に移動していく。
ホリゾントは、クリーム色の壁面で巨大な衝立のような立体。中央に鋭利な切り込みをしたような出入り口。
二人の鎧をまとった剣士が、剣でもって戦っている場面から舞台は始まる。
ホリゾントは鈍い銀色の半円形の月面となり、そこに二人の剣士が戦う姿のシルエットが映し出される。眼前の実物の動きとは別に、それはあたかも月面世界での夢幻的な出来事のように見える。剣士が顔面を覆っている冑を取ると、ヒポリタとシーシアス公爵が戯れの試合をしていたことが分かる。シーシアスは剣でヒポリタを勝ち得たが、ここではヒポリタがシーシアスに勝つ。
鉛色の月面のホリゾントは、シーシウスの宮廷の場面で常に登場人物たちのシルエットを映し出し、そこに二重構造の世界を紡ぎ出す。
イージアスによって公爵の前に引き出されたライサンダーとハーミアは、ふてくされた表情をしていて、親の理不尽な強制には従わないという強い意志をにじませている。
イージアスはライサンダーからハーミアへの贈り物の数々が入った小箱を手にして、それをいちいち取り出しては見せる。細かい芸が新鮮。
公爵はハーミアとライサンダー二人を残してイージアス、デミートリアスに一緒に来るように命じ、ヒポリタの手をとって行こうとするが、ヒポリタはハーミアに同情して、公爵より先に一人でさっさと行ってしまう。ここらあたりの演出は特に目新しいわけでもないが、ヒポリタを演じるブリジッタ・ロイの全体の所作が印象的。
妖精たちの、夜の森の世界。
森は、オブジェの廃棄物の堆積場所のようで、このオブジェが擂り鉢状に半円形にせり上がっていて、その半円形に区切られたホリゾントが巨大な月そのものとして見える。
森の廃棄物の堆積は、現代の自然の荒廃を象徴している、ととることができる。
パックは、アテネの町の職人たちが集まるとき、掃除人の姿をして一瞬通り過ぎて行く。そのパックはどこか寂しげな孤独な姿である。
パックを演じるジョナサン・スリンガーの言葉を借りれば、「愛についてのこの物語で、パックに愛の対象となる存在は、王と道化の関係にあったものが、インドから来た少年のためにその関係が崩れてしまった。オーベロンの注意を引いて、その失った愛を取り返すために働くキャラクターとしてパックをとらえた」ということであるが、パックはオーベロンの命令を実行することで、二人の関係を取り戻しただけでなく、道化の自分より、「人間ってなんて馬鹿なんだ」と言って、森に迷う四人の若者の恋の茶番劇を自ら楽しむことになる。そしてパックとオーベロンの関係は、オーベロンがインドの少年をタイテーニアから首尾よく手に入れたことにより、その修復が完成される。
インドの少年とは何を意味するのであろうか。
インドの少年については、まったく登場させない場合と、実際に色の黒い(インド人?)少年を登場させる演出がこれまでのパターンとしてあるが、今回グレゴリー・ドーランの演出では、彼自身の経験である文楽の印象に基づいて、文楽の人形を使っての演出となっている。生身の人間ではないということによって、表象的な暗示を引き出す効果がそれによって生まれていると思う。
表の世界=人間の世界では、シーシウスがアマゾン族の首領ヒポリタを征服し、結婚する。
裏の世界=森の妖精の世界では、インドの少年をめぐって、妖精の王オーベロンと女王タイテーニアが争い、最後にはオーベロンが少年を得る。
オーベロンを新興国家イングランドの表象というとらえ方でみるならば、インドの少年は、オーベロンとタイテーニアの争いが大航海時代における東洋の香料の権益をめぐる旧大国=スペインと、新興国家=イングランドとの覇権争いという見方もできるのではないか。つまりインドの少年は、東洋の貴重品である香料をシンボライズしていると考えることができる。
インドの少年を、人間ではなく人形を使うことによってその象徴性の想像力の幅を広げることが可能にできたのではないかと思う。
森の中で、アテネの若者たちは時間の経過とともに、妖精たちの仕業によって、次第にその持ち物や衣服を剥ぎ取られていく。最後には四人の若者は下着姿1枚になってしまうが、舞台という制約でなければおそらく全裸の状態となっているだろう。マイケル・ホフマン監督映画のように。
衣服を剥ぎ取られていくことは、夢の世界において深層意識の皮層が剥ぎ取られていくプロセスにも擬せられる。そしてそれは浄化作用にも似ている。夢の世界から目覚めたとき、四人の若者は、本来の望みが成就され、ライサンダーはハーミアと、ヘレナはデミートリアスとめでたく結ばれることになる。そこに至るまでの、夢の中での神聖な儀式のプロセスとしての浄化作用といえる。
タイテーニアを演じるアマンダ・ハリスが、ジュデイ・デインチを思わせるような大胆な演技で非常に印象的であったし、オーベロンのジョー・デイクソンも印象深った。パックのジョナサン・スリンガーも朴訥然とした面白みがあった。
この舞台の演出効果を最大限に発揮しているのが、ステイーブン・B・ルイスの舞台装置。グレゴリー・ドーランの緻密な演出は、彼の舞台装置によって、想像を喚起する表象性を可能としているといっても過言ではない。
ピーター・ブルックへのオマージュとして、またひとつの伝説が生まれた、という最大限の賛辞を最後に贈りたい。
(演出/グレゴリー・ドーラン、12月11日(日)、東京芸術劇場・中ホールにて観劇)
|