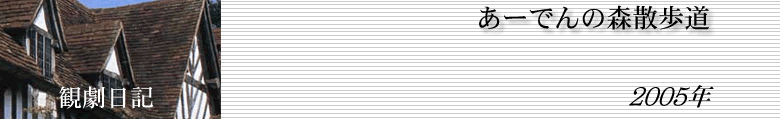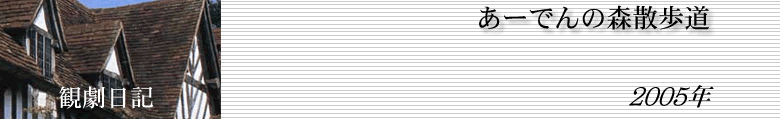謎めいた作品である。
上演の機会も非常に少ない。記録を持たないので正確なことは言えないが、国内では1972年の文学座アトリエ公演、ジェフリー・リーブス+出口典雄演出と、シェイクスピア・シアターによるシェイクスピア全作品快挙の中で78年に渋谷のジャン・ジャンで上演されたものぐらいしかないのではないだろうか。
私が唯一観ているのは、94年、ジャテインダー・ヴァーマー演出により、パナソニック・グローブ座(当時)で上演された英国のタラ・アーツ劇団による公演のみである。
上演史をひもといても、初めから謎めいているらしい。初演の記録が残っていないばかりか、17−8世紀にシェイクスピアのこの作品が上演された記録がまったくないという。
第二次世界大戦後になってからはこの作品の現代性が見直されてしばしば上演されるようになって話題を提供しているということである(白水社ブックス、小田島雄志のシェイクスピア全集、『トロイラスとクレシダ』の巻末、蒲池美鶴の解説による)。
原作を読んでもこの作品はなんだかはっきりしない。悲劇でも喜劇でもない、そこで「問題作」の範疇にいれられているようだ。作品の性格がはっきりしない理由の大きな原因が、その終わり方にある。
このドラマのタイトルとなっているヒーローのトロイラスが恋人クレシダに裏切られた復讐をとげるわけでもなく、ヒロインのクレシダが死んでしまうわけでもない。
悲劇性という点では、ヘクトルの妹カッサンドラの予言が的中するヘクトルの戦死によるトロイ王国の滅亡の予兆にある。
喜劇性という点では、トロイ戦争の発端を通して見られる全体の構造に見られる。
周知のようにトロイ戦争の発端は、トロイの王子パリスがスパルタ王メネラオスの妻ヘレネを奪ったことに始まる。戦争の大義は愛と名誉の問題である。そしてこの『トロイラスとクレシダ』では、トロイの王子トロイラスがギリシアの武将デイオメデスにクレシダを奪われる。奪われた女たちは、元の夫や恋人を裏切って(?)新しい恋人に夢中である。ここでは男の愛も名誉の問題も茶番でしかない。戦争も茶番でしかない。そこが喜劇的である。
今回観ることのできた俳優座の上演で、この作品の分かりにくさをいっそう分かりにくくしていたのは、キャステイングのダブリング。
秋間登がトロイ側の武将プリアモスとギリシアの武将ネストルに、脇田康弘がパリスとアキレウスに、林宏和がアイアスとアイアスを演じる。トロイ側とギリシア側ではその衣裳の色分けをしているのでそれに気付けば問題ないのであるが、最初は面食らった。ただでさえ我々にはなじみの薄い名前の登場人物なので、区別をするのに何もない舞台では台詞と衣裳だけが頼りである。
1999年のナショナル・シアターでのトレヴァー・ナンによる演出は、トロイ軍を全員黒人にして白衣の衣装を着せ、一方ギリシア軍は全員白人で衣裳は古びた皮のコートを着させ、はっきり区別させたという。
今回の演出では衣裳だけがその区別で、しかも両方の陣営の登場人物をダブルキャステイングしているので余計に分かりにくい。
演出の意図が今ひとつ不消化に終わったのは、プロローグと、トロイ軍とギリシア軍の合戦場面での空爆の音。古代の戦争に現代の空爆の音響を用いるにはそこに何らかの表象性があると思うのだが、それが見えてこない。
今ひとつ馬鹿げた行為に見えたのは、トロイ軍との戦いの最中、甲冑姿のアガメムノン(田中茂弘)が甲冑につけたビールの缶を飲み干しては投げ散らかす。最初は手榴弾でも投げているのかと思わせたのであるが、ただ単にビールを飲んでは空き缶を放り投げているだけである。これは何なんだ?と思った。
今回の演出で強調されて見えたのは、クレシダの叔父でトロイラスとクレシダの仲立ちをするパンダロス(中野誠也)とギリシアのアキレウス(脇田康弘)の部下であるテルシテス(立川三貴)の道化役。この二人の道化役によって舞台は引き回されている。
パンダロスを演じる中野誠也は、プロローグ役も務める。プロローグで登場するとき、その台詞にあるような甲冑姿ではなく、旅行かばんとステッキを持った、くたびれたようなモーニング服姿である。そのだぶだぶのズボンが道化役を予兆する。甲冑姿でないので、台詞には当然「甲冑姿であらわれた」という箇所が省略されている。
プロローグの口上の後、戦争を表象する空爆の音。コーラーの自動販売機を模した大きな布で身を隠す。空爆と自動販売機という現代性。が、それが何を表示しようとするのか、私には見えてこなかった。
パンダロスは舞台の終わりでエピローグとしての台詞を語り、ギリシア劇のコロスのような役割を思わせる。その背後ではテルシテスが、ヘクトルの惨殺を表象した赤い紐を身体と顔中に巻きつけた後、蓑虫のように舞台中央奥でまるまって死ぬ。原作にはない演出である。この舞台全体を表象する暗示的なエンデイングである。
この舞台の登場人物の名前が今ひとつ分かりにくかった点の一つに、小田島雄志訳と松岡和子訳の違いがある(これは小田島訳を先に読んでいることによる当惑)。最も大きな違いは、ギリシア軍の武将でヘクトルの従兄弟アイアス(松岡和子訳)。小田島訳ではエージャックスとなっている。また道化テルシテスは、小田島訳ではサーサイテイーズとなっている。小田島訳で読んでいると、まずここでつまずく。発音表記からも察せられるように、小田島訳は原文の英語に忠実で、松岡訳ではギリシア語表記に準じているようだ。
テアトル・ド・シーニユー/日欧舞台芸術交流会公演は、昨年10周年を迎え今年は11年目になるが、私が観てきた舞台は(ここ数年でしかないけれども)、一様に背景が暗い、黒を基調にした舞台である。
舞台装置は簡素で特にこれといった大道具はない。今回も柱を模した黒の網状に織られた布が4本(であったか3本であったか記憶が曖昧)あるだけの舞台で、その布柱を隠れにして覗き見をしたりするのに使われる。
もともとが中途半端な印象を与える作品ではあるが、トロイラス(小川剛生)とクレシダ(小川敦子)の印象も妙に薄く感じられた。この作品を愛と不実をテーマにして描こうとすれば、ヘレネとクレシダをもっと強調対比させてもいいのではないかと思うが、ヘレネ(山本順子)とパリス(脇田康弘)の愛撫のシーンもなんとなく取ってつけたようなドタバタの印象でしかない。ヘレネのはすっぱな行為も、対比という点では重要な要素であるが、それがうまくいかされていない。
愚かな(?)発端による戦争をテーマに描こうとするのであれば、空爆の音響を生かした現代を風刺するアレゴリーがあって然るべきだろう。
原作にはないテルシテスの死のエンデイングも消化不良に終わる。
見終わった感想もどことなく消化不良の気がするのは、この劇がはらんでいる宿命だろうか?
訳/松岡和子、演出/高瀬久雄
11月26日(土)14時開演、俳優座劇場、チケット:4000円、座席:5列17番
|