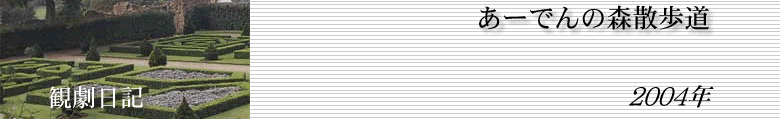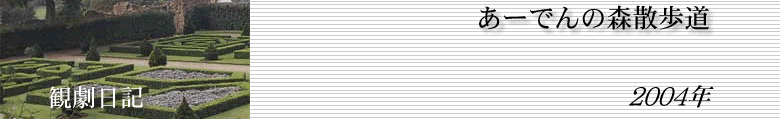~ 鏡の向こうのシェイクスピア・シリーズ ~
「馬をくれ、馬を!代わりに俺の王国をくれてやる!」
左肩がよじれ、足はねじれてびっこをひいた醜悪な姿のリチャード(井出泉)が、「馬をくれ」という『リチャード三世』終焉の場面からこの劇は始まる。そしてこの台詞とともに場面は暗転し、舞台はがらりと趣を変えていく。
そこは、とある田舎の森の中。二人の少年が一生懸命にキノコ採りをしている。この二人の少年は、エドワード四世の遺児エドワード(清水まゆみ)と弟のヨーク(川久保州子)である。バッキンガム(大久保洋太郎)が二人の叔父であるリチャードの暗殺の手から逃れさせるため、身分を隠して農婦(奈良谷優季)の家に預かってもらっているのである。打続く戦乱で夫を戦場に取られた農婦は、食い扶持を稼がせるために二人にキノコ刈りをさせているのである。
二人の会話から、バッキンガムが、彼らの前に修道院にもう一人の人物を連れてきていることが知れる。
彼女は王妃マーガレット(牧野くみこ)である。しかし彼らはお互いに身分や正体を知らない。
そこへバッキンガムはさらにもう一人の人物を連れてくる。それはボズワースの戦いでリッチモンドに敗れて戦死したはずのリチャードである。しかし、リチャードはまったく記憶を喪失しており、自分が誰であったのか覚えていない。バッキンガムはリチャードが犯した悪事の数々を並べ立てて、必死に彼の記憶を取り戻させようと努力するが、リチャードには覚えがなく、出てくる言葉は聖人君子のような言葉ばかりで、徒労に終わる。
このリチャードは、手足も正常であるばかりでなく、心もまったく邪なところがない敬虔な人物となっている。修道院で毎日の祈祷だけでなく、牛小屋の掃除から、水汲み、薪割りなどの一切の雑務を日課としてこなしている。
エドワード王子やマーガレットは、このリチャードがリチャード三世であることを知って、復讐を図って何度も殺そうと試みるがその都度失敗する。記憶を失くしたとはいえ武人としての本能の働きは残っているのだった。
リチャードはそんな彼らに対して、万聖節の休みの日には栗拾いに行こうと誘う。憎むべき相手であるリチャードであるが、今は善意の塊のようにようになっている彼の言葉に、王子たちは頷いて承知する。
万聖節の日には村に旅役者が来て芝居が行われることになっていたのが、この戦乱で役者達が来られなくなり、代わってバッキンガムやリチャードたちが芝居をすることなった。
バッキンガムはそこでリチャードの記憶を取り戻す手段として、リチャードに彼自身を演じさせることを思いつく。
芝居の稽古がいよいよ始まる。
「さあ、俺たちの不満の冬は終わった、栄光の夏を呼んだ太陽はヨークの長男エドワード」(註1)
正常な身体をしたリチャードは、この芝居では、左手が麻痺して、足もびっこの不具の恰好で、『リチャード三世』の冒頭の有名な台詞を朗々と演じる。
稽古に立ち会った修道院の院長(ヲトメ)は、それを見ていて村祭りの出し物にふさわしくないように思い異議を挟むが、一緒に見物していた農婦の、「ともかく見てみましょう」という言葉で、稽古はそのまま続けられることになった。
次の場面はリチャードがアンを口説くところである。
葬儀の場面で、しかも敵の男から口説かれる場面が不謹慎であると、修道院の院長は憤るが、マーガレットの演じるアンが、リチャードに唾を吐きかけるのだと聞いて、それならよろしい、といったん引き下がる。しかし、アンがいよいよリチャードに口説き落とされるに及んで、院長は、リチャードに対して「地獄などありません」と言っていた言葉とは裏腹に、二人に向かって「地獄に落ちてしまえ!!!」と絶叫して気絶してしまう。
この場面は、これまで冷静沈着に装ってきた院長であるだけに、コミカルに感じる。院長役のヲトメが好演。
マーガレットが、二人の少年が自分の敵方であるヨーク家のものであると分かって殺そうと図るが、二人にリチャードから誘われた栗拾いに一緒に行こうと言われ、その殺意も泡となって消えていく。
この森は癒しの森となって、人々を善意に導いていくようである。しかし、そこへ二人の王子の暗殺者が現れる(実際には舞台には登場せず、場面は暗転し、あとでマーガレットの台詞から二人の王子の運命が明らかになる)。
稽古が再開され、今度はリチャードが王位に就いて、バッキンガムに二人の王子の暗殺をもちかける場面となる。バッキンガムが自らの役と、暗殺者ティレルの役を演じる。と、そこへ院長がやってきて、二人の王子が殺されたことを知らせる。
今までリチャードを演じていたリチャードが、二人を殺したのは自分だと告白する。リチャードは自分の役を芝居で演じていて、自分が誰であったか記憶を取り返したのである。
バッキンガムには、どちらが本当のリチャードか今では分からなくなっている。自分はリチャードの目を覗いたことがなかったことに気づく。リチャードに言われて彼の目を覗くが、本当に自分は彼の目を覗いてみたのであろうかと自問する。ガラスの向こうは透明で、何もない。はたして、どれが本物のリチャードなのか?!
記憶を取り戻したリチャードは、ボズワースの戦場へと引き返す。
舞台背景から、「馬をくれ、馬を!!」の声、そして暗転。
このままで終われば、舞台は円環構造を取り、循環的に永遠に繰り返すことができる。
しかし、暗転の後、舞台でキノコ採りをしているのは王子たちを世話していた農婦であり、彼女に声をかけてくるのは修道院の院長。そして今ではシスターとなったマーガレットが登場する。
マーガレットは二人の王子の運命に対し、毎日安らぎのお祈りをあげている。院長は彼女に対し、もうそんな必要はないのですよ、二人の王子は無事で、遠くに匿われていることを告げる。敵を欺くにはまず味方からという、だから今まで黙っていたと言う。
二人に手紙を書いてもいいでしょうか、とマーガレットは尋ねるが、院長は二人の王子とマーガレットの息子エドワードの三人が鳥となって、そこに会いに来ていると空を指差す。
この言葉は意味深長で暗示的に響く。史実としての二人の王子の運命ははっきりしておらず、一説には田舎で無事一生を終えたという話も残っており、院長の台詞もそれを肯定しているようでありながら、鳥になって会いに来たなどと言っているので、生きているというのは口実のようにさえ聞こえてしまう。
院長とマーガレットの場面で終わることによって、このドラマの循環構造が微妙にずれて、螺旋構造となる。
この劇は、いわゆるリカーデイアン(リチャード三世を擁護する人々)へのオマージュともいうべき作品である。
リチャード三世が鏡の向こうの世界に入り込んで、現実とは正反対の状態になった彼自身を照らし出すことによって、リチャードの善玉性を浮かび上がらせるというドラマの構造をなしている。
現実のリチャードと鏡の向こうのリチャードは、悪⇔善、醜⇔美、不均衡⇔均衡、不具⇔正常という姿を映し出している。リチャードは一瞬の間、夢をみていたようである。
「馬」の代わりに、鏡の向こうの自分を夢見ていた、そんな気持にさせるドラマであった。
(註1) 本文は、松岡和子訳を使用。このドラマの台詞とは多少異なる。
作/奥泉光、原案・演出/江戸馨
10月2日(土)14時開演、蔵前・アドリブ小劇場、チケット:3900円、座席:B3
|