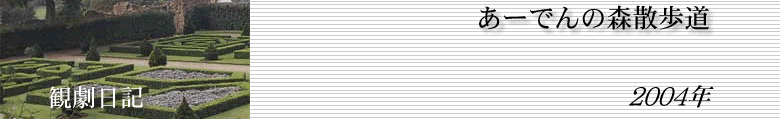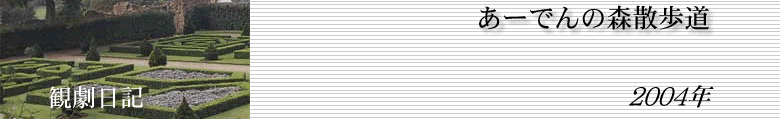~ 噴火口に飛び込むようにして死ぬ道化 ~
薄墨色の紗幕を通して、舞台全面に階段が見え、その頂上あたりに聖なる燭台の蝋燭の火が揺らめいている。開演前からこの劇の古代の祭礼的な雰囲気を感じさせ、この劇の始まりに期待の気持でわくわくさせられる。
この日はプレヴュー公演の二日目にして最後のプレヴューであり、演出家の佐藤信が開演前に挨拶の口上が あった。プレヴューの意味合いについての説明と、明日からの本舞台がこの日の観客の反響次第で本日の舞台と変わりうることの断りがあった。一般的にプレヴュー公演はチケット代が安いこともあってこれまでにもよく利用しているが、このような口上は初めてだったので新鮮な感じがした。
プレヴュー公演は、稽古の総ざらいを公演の形で観客に披露することで、その反響次第で本公演の変更手直しもありうるものである。だからといって本公演と異なるかといえば、必ずしもそうではなく、そのままの場合も大いにある。演出家と俳優の立場から言えば、観客の反応によって劇の完成度をはかる場でもあり、むしろ緊張の度合いが高いかも知れない。
石橋蓮司のリア王は、自分にとってはイメージ的に予想外のキャステイングで、それだけにどんなリア王となるのか楽しみであった。石橋蓮司のリア王は、自分が想像しているリア王のイメージを体現しているもので最高のうちの一人に数えることができる。しかしながら、様式的に見事に体現されているのというのは石橋蓮司にとっては反語的ともいえる。
途中休憩15分間を挟んで3時間半という長丁場のドラマは、特に開幕の1幕1場、リア王の国の分割と3人の娘への譲渡の場面がたっぷりと時間をかけて非常に丁寧に演じられていた。
紗幕を通して作り上げられていた古代の祭礼的雰囲気は、開幕の場面において十分に体現される。ケント伯とグロースター伯の会話の後続いて登場するリア王とその娘3人たち、およびその夫たちの衣装は和様を感じさせる重厚な衣装で、十二単(ひとえ)をマントにしたようなものである。その色調からしてエキゾチックであった。
3人の娘のそれは赤を基調にし、二人の夫をはじめとする貴族たちの衣装は、玉虫色的など色とりどりであった。
舞台全体が階段状の構造になっているので、俳優の動きは大きな制約を受け、そこにひとつの様式美が生まれているように感じられ、それが衣装の様式美と融合していた。
その様式美はプラスでもあるが、マイナス面としては嵐の場面に感じられた。
リアが嵐に向かって叫ぶ場面は、形だけがあって中身がなく、空疎な響きにしか聞こえなかった。
アンリアル、現実でないうつろな響きであった。舞台階段の頂上の背景は大きなスクリーンをなしていて、場面展開を映像で表現しており、嵐の場面では暗雲立ち込める雷鳴の映像の中で、リア王が階段の頂点で叫ぶのであるが、台詞が作り上げる想像力の魅力が映像によって希薄化されていた。
映像を用いた場面背景は視覚的な効果もあるが、シェイクスピアの場合、台詞が作り上げる想像力の魅力を喪失させる危険もはらんでいるようだ。シェイクスピアは台詞自体で場面情景を説明しており、それを映像化してしまうことで想像力を限定してしまうというマイナスがあり、映像で場面をリアルにすればするほど台詞の魅力が小さくなることがある。
作られたリアルの幻滅感は、死んだコーデリアを抱いたリア王にも感じられた。急な階段状の舞台であり、実際の人間を抱いてその階段を上るのは危険でもあるだろうが、石橋蓮司が抱いたコーデリアは、なんと本物そっくりに作られた人形であった。
リアの「泣け、泣け、」というこの台詞の場面では、本当に涙が出る演出も何度か見ているだけに、この場面の期待度は高いのだが、残念ながら嵐の場面同様に、その叫びは空疎に感じられた。
しかしながら、この舞台の様式美はリア王の死によって完成される。コーデリアの死で、リアは狂想と神経の衰弱でその命を閉じる。リアの死骸は台座に載せられ、兵士たちによって階段の頂上へと運ばれ、そこに安 置される。忠節の士ケントがその階段を上っていき、リアの死骸の台座を前にして、「霊魂をお苦しめするな、安らかに逝かせよう・・・私は間もなく旅に発たねばならぬからだ、否とは言えないのです、ご主君のお召しとあらば」(註)と別れの言葉を告げるとき、リアの死が高揚される。
すべてが終わったとき、舞台は静止し、リアの道化がコーデリアの人形の死骸を抱いて奈落から階段を上ってきて、舞台前面に現れる。登場人物一同がその階段の高低に身分の高さを象徴する形でそれぞれの位置を占める。そして場面は一旦暗転し、同じ構成で、今度は道化が抱いたコーデリアが本物のコーデリアとなって道化と並ぶ。横たわっていたリアは階段の中央部に下りてきて、両手を逆八に開いて高々と上げ、無言のままに天を仰ぐ。
リアに一条の光が射し、その静寂の中に舞台は閉じる。
舞台の和式の様式美を感じさせたのは衣装だけでなく、音楽集団「鼓童」の太鼓と笙の鋭い響きがその和様性を増幅する。特に笙の響きは抉るような緊張感と想像力を強く煽り立てる。
『リア王』での見所の一つに道化役がある。『リア王の悲劇』では、手塚とおるが目の周りに青黒い隈取をして、手には道化の台詞のシンボルともいえる大きな鶏の首の人形を持っている。台詞は斜めから射すようなクールさがある。鋭角の鋭さではないが、鈍角でもない、ブーメランのように、相手に投げていながら自分の手元に帰ってくるような台詞まわしである。道化の死も時にシンボリックであるが、手塚とおるの道化は、嵐の日にリア王と離れて、ひとり階段の頂上まで上りつめ、背景のスクリーンが赤く燃え上がる噴火口の映像となり、道化はその中に飛び込むようにして消えていく。
このたびの『リア王の悲劇』は近藤弘幸の新訳になるもので、『リア王』ではなく、『リア王の悲劇』とした所以を彼自身が語っているが、それはこれまでの折衷版ではなく、日本で初めてのフォリオ版完全再現ということを強く意識してである。手元にその翻訳をもっていないので比較参考はできないが、気になる台詞として、リアの3人の娘、ゴネリル、リーガン、コーデリアに、「余」というロイヤル・ウイを意識した言い回しをさせていることである。これは台詞に自然さがなく、非常に気になった。
(註)本文中の台詞は小田島雄志訳を使用しているので、今回の翻訳とは異なる。
翻訳/近藤弘幸、演出・美術/佐藤信
9月26日(日)15時開演、世田谷パブリックシアター、チケット:(A席)5500円、座席:1階A列18番
|