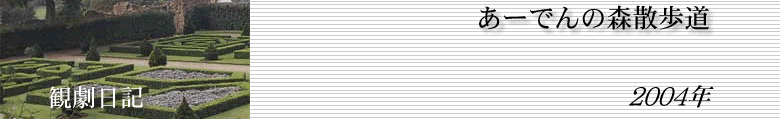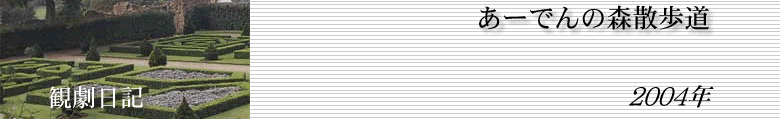〜 今日性を表象する舞台 〜
それは一発の轟音の砲声で始まり、一発の轟音で終った。
間に15分の休憩を挟んで3時間10分の舞台が、その轟音に象徴されるかのように、早いテンポで進んだ。
その轟音は、衣装によって表現された1950年代という『オセロ』の時代設定を超えて、イラクやアルバニア、そしてパレスチナという現代の国際紛争の現在性を感じさせるものであるが、ドラマの展開としては、そういった政治性とは違った印象、すなわち『オセロ』という本来の悲劇性を強く感じた。
舞台はストラットフォードのスワン座の公演を踏襲しているのであろう、ル・テアトル銀座の舞台は張出舞台に作られ、舞台前方は三方向から囲まれる形で観劇される。
◆ エミリアの死に涙
大学で初めて『オセロ』を読んだ時には、柳の木の唄を歌うデズデモーナに涙が出たが、この舞台では、エミリアがデズデモーナの死に伏すベッドにもたれて死ぬ場面で思わず涙がにじんできた。
その涙は、エミリアを演じるアマンダ・ハリスの演技力にもよるのであろうが、涙の原因を自分なりの解釈を加えてみると、デズデモーナは、自分がなんの罪で死ぬのか(殺されるのか)分からないまま死ぬが、エミリアは、自分が知らずして犯した過ちの重大さに気付いて死ぬ(殺される)。
その、悔いても悔いきれない罪の悔恨に同情心が移るのであろう。グレゴリー・ドーランが描くエミリア像は、最も興味深い人物の一人として登場する。エミリアの最初の登場は、嵐の海からデズデモーナの付き添いとしてキプロス島に到着した時からである。
この登場の仕方でエミリアの人物像が決定づけされる。
エミリアは、アメリカ占領軍の兵士の妻のような印象である。占領軍の士官の妻、勝者の側としての傲慢さが内在している。それは後に、キプロス島現地出身のビアンカに対する態度に顕著に表われる。余談ながら、娼婦ビアンカは、占領された側の悲しい生き様の表象としてとらえられる。
キプロス島に到着するやいなや、エミリアはまずハンドバッグからウィスキーの瀟洒な小ビンを取り出して、ラッパ飲みして気付けをする。そして自分が飲んだそのビンを他の兵士にも回す。そうして落ち着いたところで、今度はタバコを吸うのだが、そのタバコに火をつけてもらうのに、キャシオが気を利かせるのを催促するように待っている。そこへ、キプロス駐留の兵士が暖かいコーヒーを運んでくる。その兵士がコーヒーを最初に渡すのがエミリア。将軍であるオセロの妻デズデモーナより先に差し出されたのであるが、エミリアは当然のようにしてそれを受け取る。そして自分のコーヒーにウィスキーを少量たらした後、デズデモーナのコーヒーにも同じようにウィスキーを注ぐ。
エミリアの人物像は、この場面によって決定づけられ、観客に対して造形化される。
エミリアは、デズデモーナの付き添いの役をしているが、それは普通の侍女としてではない。夫の上官の妻としての敬意を払いながらも、どこかで対等な気持をもっている。
デズデモーナに必ずしも忠実でないのは、彼女が落としたハンカチを拾って返さず、夫イアーゴのために取っておくことにも表われている。そのハンカチがデズデモーナにとっていかに大事なものであるかを知っていながら。世界をくれるというのなら、夫の出世のために不義も躊躇しないというエミリアであるから、ここでは主人であるデズデモーナより夫イアーゴの頼みが優先される。
それゆえに、夫から裏切られたことに気付き、自分がどんなに取り返しのつかない過ちを犯したかが分かって、すべての不条理を背負って死ぬエミリアの死に涙が出たのだった。
◆ オセロの悲劇性
オセロの悲劇は、キプロス島に到着した時、出迎えるデズデモーナとの再会の場で、すでに集約されている。
オセロは、嵐の海から無事到着して、自分より先に着いていたデズデモーナとの再会に、周囲への配慮もなく、軍事に優先して私的な感情に溺れてしまっている。
デズデモーナとの再会の場面におけるオセロに、悲劇は起こるべくして起こったという必然性を感じた。
カ・ヌクーベの演じるオセロは堂々とした体躯の職業軍人というイメージが造形されている。オセロはその 表面とは裏腹に内面にコンプレックスを抱いた人物であるがゆえに、イアーゴは、そのコンプレックスをオセロに自覚させるだけで悲劇に陥落させるのに十分であった。コンプレックスに火をつけて、あとは煽るだけでいい。火は自らを燃え立たせていく。
その火の熱さに耐えかねて、オセロは大地を固く、強く踏み鳴らす。
その地団太を踏む姿は、アフリカの民族的儀式の様相をすら感じさせる。
イアーゴの言葉に操られて嫉妬に狂うオセロは、熊のように舞台を大きく円を描きながら動き回る。
オセロはデズデモーナの殺害を決行する時に、それまでの軍服を脱いで、彼の出自であるアフリカの民族衣装をまとって、自己回帰する。このとき彼は、キプロスの将軍であることも、職業軍人(傭兵)であることもやめて、個人に戻っている。民族衣装は自己完結の準備でもある。
オセロの悲劇は、個を殺して自分の民族性を抑え、決して同化されることのない白人の世界に自らを同等化しようとした錯覚にあった。デズデモーナに対する嫉妬は、錯覚の崩壊でもあった。
◆ 舞台装置の象徴性と小道具の巧妙な使い方
キプロス島のヴェニスの軍隊の用地には、有刺鉄線の張られた金網のフェンスで、こちら側とあちら側に仕切られている。占領地帯の表象として、それが現代的な感じを与え、そのことゆえに現在の国際紛争を強く連想させる。
デズデモーナのハンカチをエミリアから奪い取ったイアーゴが、オセロの嫉妬を煽り立てている時汗をかいて、その汗を拭おうとしてデズデモーナのハンカチを思わず取り出してしまい、慌ててズボンのポケットに引っ込める。これなどは、ちょっとした観客サービスである。
オセロの締めているネクタイの色が緑色であるのは、イアーゴの台詞に出てくる嫉妬の怪物の目は緑色をしているということで、分かりやすい象徴性の具現であるが、このことはロンドンで先に観られた鈴木真理さんの、『オセロ』の見所としても紹介されていたので、注意して観ることができた。
キプロス島の最初の場面で出てくるジプシーは、その後も場面転換のきっかけとして再三登場するが、これも鈴木さんの指摘のあるように、占領地から追い払われる現地人としての体現としてとらえることができるだろう。
キプロス島での夜警の酒盛りの場面で、キャシオが酔っ払うが、兵士達がキャシオを敷物に担いで、ぐるぐる回しをする。こんなことをすれば酔いが回るのはてき面である。これなども念のいった演出であると思ったし、この場面にふさわしい演出法でもあった。
◆ ドーランの演出と出演者について
最初にも書いたが、ドーランの演出はテンポの早いものであった。
そのテンポの早さは贅肉を削ぎ落とした舞台の進行にあった。その例の一つとして、キプロスに到着した翌 朝、オセロとデズデモーナの寝室の前での楽士の音楽や道化の登場のカットなどがある。
出演者については、エミリア役のアマンダ・ハリスがやはり一番印象的だった。
セロ・マーク・カ・ヌクーベのオセロも印象深い。RSC初めてのアフリカ出身のオセロ役ということも特色であろうが、その訛りのあるアクセントがムーア人であるオセロを身近に感じさせた。
リサ・デイロンのデズデモーナには、清純さと可憐さと芯の強さを感じた。カ・ヌクーベとともに、彼女もこの『オセロ』がRSC初デビューだそうである(鈴木さんの情報)。
最後になったが、イアーゴを演じたアントニー・シャーは事前情報も多く、多くが語られているので、いまさら自分がここで書くこともないが、あえて言うなれば、彼の演技力があって、カ・ヌクーベのオセロがありえたといえば、その賞賛になるであろうか。
演出/グレゴリー・ドーラン
4月18日(日)13時開演、ル・テアトル銀座、チケット:(S席)10000円、座席:4列18番
【付 記】
海外からの来日公演としては1998年1月に、ロイヤル・ナショナル・シアターによる、サム・メンデス演出、サイモン・ラッセル・ビールのイアーゴーの『オセロー』を銀座セゾン劇場で観劇している。
|